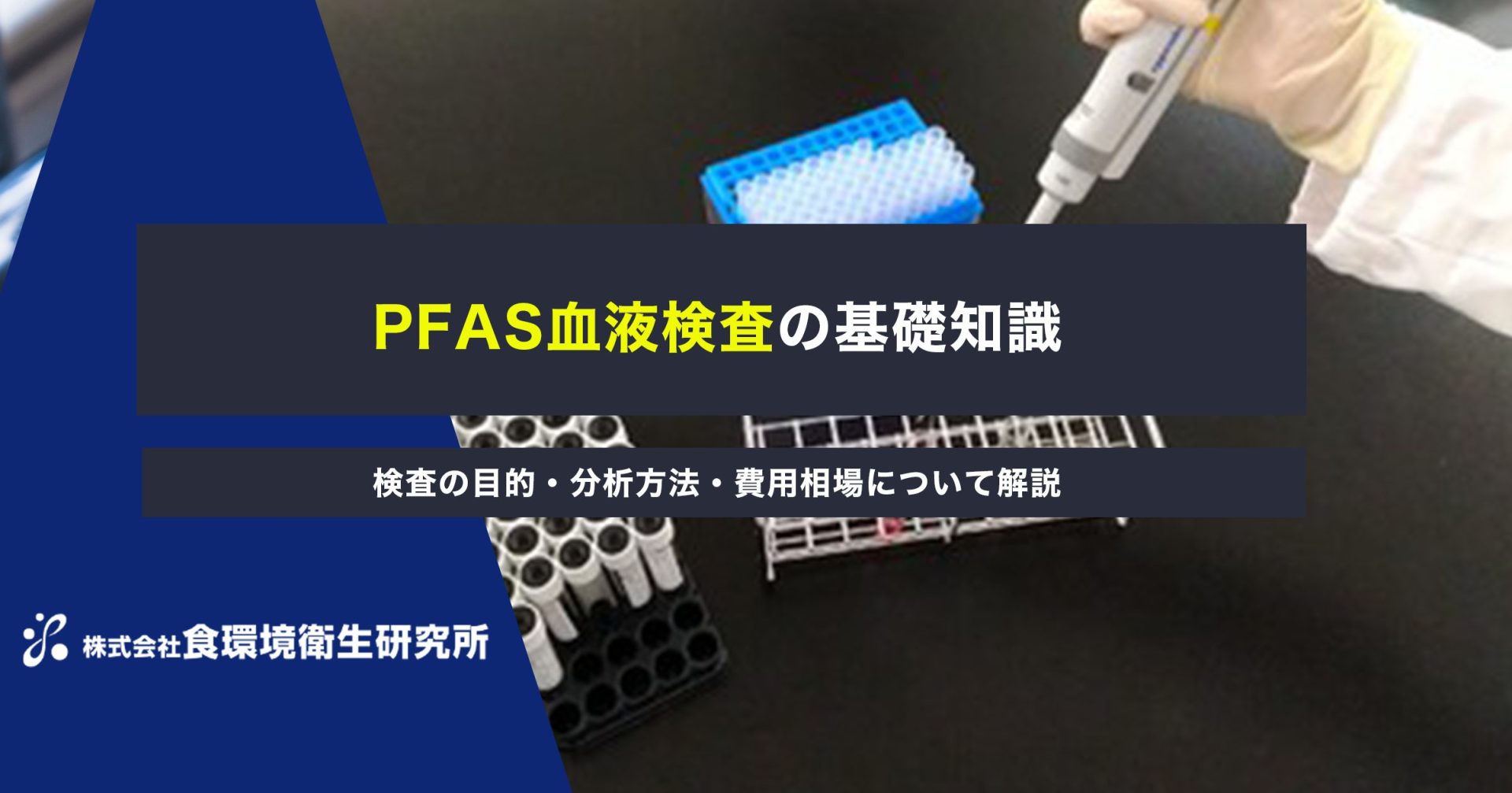PFAS血液検査の目的と重要性
そもそもPFAS(ピーファス)とは、人工的に合成された有機フッ素化合物の総称のことです。防水性・耐熱性・耐薬品性などに優れていることから、食品包装や調理器具、衣類、消火剤など幅広い用途で利用されてきました。
しかし、極めて分解されにくい特徴からPFASは「永遠の化学物質(Forever Chemicals)」とも呼ばれ、自然環境や人体に長期間残留することが近年問題視されています。
とくに飲料水や食品などを通じて体内に取り込まれたPFASが蓄積することで、腎臓疾患、高コレステロール、甲状腺機能障害、免疫機能の低下、さらには一部のがんとの関連も指摘されており、国際的にも規制強化や健康影響の調査が進められてるのが現状です。
そして、このような背景からPFAS血液検査が重要になります。血液検査を行うことで、自身の体内にどの程度PFASが蓄積しているかを検査することができ、以下のような目的を持って実施されます。
| 目的 | 概要 |
|---|---|
| 曝露の有無と程度を把握するため | 汚染地域に住んでいたり、PFASを使用する製品・産業に関わっていたりする場合、無自覚のうちに曝露している可能性がある。 |
| 健康リスクを判断する材料になるため | PFASの血中濃度と健康リスクの関連については、国内外の研究が進められており、濃度が高い場合には医療機関での経過観察や生活習慣の見直しが推奨されている。 |
| 環境や生活習慣の見直しに活かすため | 高濃度が検出された場合、飲料水の安全性や日用品の使用状況、居住環境の確認など、日常生活のリスク要因を見直すきっかけになる。 |
PFAS血液検査は、「自分の体の中にどれだけPFASが蓄積しているか」を知り、今後の健康管理や生活環境の改善に役立ちます。PFAS問題が取り沙汰されている地域に居住している方や、PFASとの接点が多い職種の方にとっては、積極的な検査の検討が望まれます。
PFAS血液検査の方法と測定対象物質
PFAS血液検査は、血液中に含まれるPFASの濃度を直接測定するもので、現在の曝露状況を把握するために最も信頼性の高い方法とされています。PFASは体内に蓄積されやすく、尿などの排泄物からの測定では正確な評価が難しいため、血液検査が標準的な手法とされています。
検査・分析を行う会社によって血液検査の方法は異なりますが、日本国内においては「液体クロマトグラフ質量分析法(LC-MS/MS)」が一般的な方法となります。
LC-MS/MS法では、採取した血清からPFAS成分を抽出し、ろ過や濃縮などの処理を行います。わずかな量であっても検出が可能であり、複数種のPFASを同時に測定できる点が特長です。
1,000種類以上存在するとされているPFASの場合、複数種を同時に測定できるLC-MS/MS法が有効とされているのです。
なお、血液検査で測定されるPFASは、健康リスクに関する研究が進んでいる主要な化合物が中心です。具体的には、以下のような物質が対象となることが一般的です:
| 化合物名 | 用途の例 | 概要 |
|---|---|---|
| PFOA(ペルフルオロオクタン酸) | フライパンのコーティング剤、撥水加工 | 肝機能やがんとの関連が指摘される |
| PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸) | 消火剤、撥水スプレー | 免疫系・甲状腺への影響が報告されている |
| PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸) | 難燃剤、布地処理 | 半減期が長く、長期残留しやすい |
PFASの血中濃度の指標
PFASは体内に取り込まれると分解されにくく、数年単位で血液中に残留するとされています。そのため、血中濃度を測定することは、PFASへの曝露状況を把握する有効な手段とされています。
とはいえ、現時点では日本国内において「この数値を超えたら健康被害がある」といった明確な基準値は存在しません。これは、PFASが持つ性質の複雑さや、ヒトへの影響が個人差や化合物ごとに異なること、長期的なデータの蓄積がまだ不十分であるためです。
そのため、現時点でPFASの血中濃度の指標となるのは、参考値や統計値です。これらはあくまで自分の血中濃度が一般的な水準と比べて高いか低いかを判断するための目安に過ぎませんが、生活環境や健康管理を見直すうえで有効な情報となります。
ここからは、国内および海外におけるPFASの指標として参考値や統計値を解説していきます。
国内におけるPFASの血中濃度の指標
日本国内では、環境省が実施している「化学物質の人への暴露実態把握調査」により、一般市民の血中PFAS濃度が調査・公表されています。これは「バイオモニタリング調査」とも呼ばれ、PFASを含む複数の化学物質について、年齢・性別・地域などを考慮した全国的な曝露状況を把握するものです。
たとえば、「日本人における化学物質のばく露量について2025」では、PFASに分類される物質について中央値が報告されています。その一例は下記のとおりです。
| 物質 | 中央値(単位:ng/mL) |
|---|---|
| PFOA(ペルフルオロオクタン酸) | 1.2 |
| PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸) | 3.3 |
| PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸) | 0.52 |
あくまで中央値にすぎませんが、この数値は一定の割合の人がこの値より高い・低い血中濃度を持っていることを意味します。
また、沖縄県、埼玉県、岐阜県など、過去に水源汚染や軍事基地周辺のPFAS検出が報告された地域では、平均を大きく上回る血中濃度が確認された事例もあります。地域による曝露差がある点には留意が必要です。
海外におけるPFASの血中濃度の指標
海外では、PFASの健康影響に関する研究が日本よりも先行している国もあり、血中濃度に基づいた健康指標がすでに明確になっている国もあります。
| 概要 | |
|---|---|
| 米国 |
疾病予防管理センター(CDC)が「NHANES(国民健康栄養調査)」を通じて、全国レベルのPFAS血中濃度データを定期的に公表している。2017年〜2018年の調査によると、「PFOS:約4.7 ng/mL」「PFOA:約1.4 ng/mL」が中央値であると報告されている。 また、米国環境保護庁(EPA)は2022年に、PFOAとPFOSの生涯健康勧告値をそれぞれ 0.004 ng/L および 0.02 ng/Lと定めている。 |
| 欧州 | 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年に、「PFOA、PFOS、PFNA、PFHxSの4物質の合計血中濃度が約6.9 ng/mLを超えると、免疫機能に悪影響を及ぼす可能性がある」との科学的見解を示した。 |
このように、PFASの血中濃度は国によって基準や判断が異なりますが、いずれも「できる限り曝露を減らすべき」という姿勢を基本としています。血液検査を通じて自分の値を把握し、それをもとに適切な生活上の対策を講じることが大切です。
PFASが体内に溜まってしまう原因と生活上の対策
PFASは、化学的に非常に安定しており、環境中でも体内でも分解されにくいという特徴があります。一度曝露されると、長期間にわたって体内に蓄積されてしまうリスクがあります。
そのため、健康を守るためにも、PFASを体内に溜めないための対策を講じておくことが大切です。あくまで一例にすぎませんが、PFASが体内に溜まってしまう原因と、それに応じた生活上の対策をまとめましたので参考にしてみてください。
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 飲料水・食品による曝露 | 安全な水の選択と食生活の見直しをする |
| 大気や環境からの吸入による蓄積 | 換気や空気清浄で室内環境を整える |
| 日用品や調理器具からの接触 | PFAS含有製品の使用を控える |
| 体内での難分解性による蓄積 | 早期検査と専門医への相談を行う |
飲料水・食品による曝露|安全な水の選択と食生活の見直しをする
PFASが体内に入る経路の1つが、飲料水や食品を通じた経口摂取です。
とくにPFASは水に溶けやすい性質があり、地下水や河川が汚染された地域では水道水が汚染源となるリスクがあります。また、PFASを使用した食品包装や調理器具などから、食品へ成分が移行することもあります。
このようなリスクに対しては、浄水器の利用や水の利用方法の見直しが有効です。たとえば、逆浸透膜(RO)を搭載した浄水器はPFAS除去に対応しているため、PFAS対策には使用を推奨されています。
また、パッケージやコーティングにPFASを含まない食品や調理器具を選ぶことも、日々の摂取リスクを下げる工夫となります。
加工食品やインスタント食品の多くには、PFASを使用した包装材が使われていることもあるため、可能であれば素材を中心とした食生活に切り替えることも有効な対策といえるでしょう。
大気や環境からの吸入による蓄積|換気や空気清浄で室内環境を整える
PFASは空気中の微粒子やハウスダストに付着し、知らぬ間に吸入してしまうこともあります。
とくに「テフロン加工などの調理器具」「防水スプレーや消火剤、フッ素系ワックス」といった製品を多用している環境では、PFASの吸入に注意が必要です。
このリスクを減らすには、定期的な換気と空気清浄機の導入が有効です。HEPAフィルターを搭載した空気清浄機は微粒子レベルの汚染物質を除去する能力が高いため、室内環境を整えるうえで有効です。
また、新しく家具やカーペットを購入する際には、PFASを含まない素材であるかどうかを確認することも大切です。
日常の掃除も軽視できません。ハウスダストに含まれる化学物質の再浮遊を防ぐために、こまめな掃除や拭き取りを意識的に行うよう心がけましょう。
日用品や調理器具からの接触|PFAS含有製品の使用を控える
PFASは、その撥水性や耐油性といった特性から、日常的に使用する製品にも幅広く含まれています。代表的なものとしては、テフロン加工のフライパン、防水加工された衣類、撥水スプレー、化粧品などが挙げられます。
これらを通じて皮膚から経皮吸収されたり、調理中に食品へ成分が移行したりする可能性があります。
調理器具については、表面に傷がついたテフロン製フライパンなどは特にリスクが高まるとされており、定期的に買い替えるか、PFASを使用していない製品への切り替えが望ましいです。
また、化粧品やスキンケア製品に含まれる成分表示を確認し、「フルオロ」や「PTFE」といったフッ素化合物が含まれていない製品を選ぶことも対策の1つです。
体内での難分解性による蓄積|早期検査と専門医への相談を行う
PFASの問題は、いったん体内に取り込まれると自然にはなかなか排出されず、血中に数年溜まってしまうリスクがあることです。そのため、PFASの蓄積を予防することも大切ではありますが、蓄積を早期に把握することも重要となります。
そこで、PFASの蓄積量を知るためには、血液検査を受けることが有効となります。検査の結果、通常より高い濃度が確認された場合には、その要因を見直すとともに、専門医に相談することで対策を一緒に考えることができます。
さらに、生活習慣病のリスク管理や、飲料水・日用品の見直しを徹底することで、将来的な健康リスクを最小限に抑えることが期待できるのです。
PFAS血液検査にかかる費用の目安
PFASの血中濃度を測定する血液検査は、国内で広く普及しているとはいえず、現時点でも限られた医療機関や民間の検査センターで実施されています。そのため、検査費用が高額になる傾向があります。
実際の費用は検査機関によって異なりますが、あくまで目安としては1回のPFAS血液検査でおおよそ3万円〜5万円前後の費用がかかるケースが多いです。この金額には、検体の採取や分析、および結果報告書の作成までを含むのが一般的です。
また、測定対象となるPFASの種類などによっても費用は変動します。たとえば、PFOSやPFOAに加えてPFHxSやPFNAなど複数の化合物を同時に測定する場合には、費用が追加されることもあります。
なお、PFAS血液検査は保険適用外の自由診療となるため、健康保険を利用して費用を軽減することはできません。そのため、検査を受ける前に料金体系や含まれるサービス、測定項目の内容などを事前に確認しておくことが大切です。
今後、社会的な関心の高まりとともに、検査可能な施設が増え、費用の適正化が進むことが期待されますが、現時点では専門性の高い精密分析が必要であることを踏まえて、慎重に検討することが望ましいと言えます。
弊社が実施しているPFAS血液検査について
株式会社 食環境衛生研究所では、「食環境の検査・分析を通じて 「食」の安全な未来を守る」という理念のもと、PFASを含めたさまざまな成分の検査・分析を実施しております。
PFASの血液検査も実施しているため、「PFASが体内に溜まっているかが不安」「健康を守るためにも血液検査をしておきたい」といった場合には検討してみてください。
なお、弊社が実施しているPFAS血液検査について、費用や分析方法などをまとめましたので参考にしてみてください。
| 検査項目 | 分析方法 | 費用 | 検査期間 |
|---|---|---|---|
| PFOS及びPFOA 生体成分検査・分析(血漿・血清) | LC/MS/MS法 | 33,000円(税込) | 10営業日 |
| PFOS、PFOA、PFHxS及びPFNA 生体成分検査・分析(血漿・血清) | LC/MS/MS法 | 44,000円(税込) | 10営業日 |
| PFOS及びPFOA 生体成分検査・分析(全血) | LC/MS/MS法 | 34,100円(税込) | 10営業日 |
| PFOS、PFOA、PFHxS及びPFNA 生体成分検査・分析(全血) | LC/MS/MS法 | 45,100円(税込) | 10営業日 |
※弊社が行うPFAS検査の詳細については、こちらを参考にしてみてください。
まとめ
PFASは、その高い安定性と難分解性ゆえに、身の回りに広く存在し、知らないうちに体内へ取り込まれている可能性があります。飲料水や食品、日用品といった日常的な経路からの曝露は避けにくく、一度体内に入ると長期間にわたって蓄積されてしまうという特徴があります。
こうしたリスクに対して、自身のPFAS血中濃度を把握することは、健康リスクを見直す第一歩となります。血液検査を通じて現在の曝露状況を数値として把握すれば、日常生活のなかで見直すべき点や、必要な対策が明確になるでしょう。
また、検査結果をもとに専門医と相談しながら適切な健康管理を行うことで、将来的なリスクを抑えることにもつながります。
現在、PFAS血液検査は限られた医療機関・検査センターで実施されており、費用も自由診療の範囲で設定されていますが、社会的な関心の高まりにより、今後はより多くの選択肢が整備されていくことが期待されています。
PFASに不安を感じている方こそ、まずは正確な情報をもとに現状を知ることが大切です。そして、日々の生活のなかでできる対策をひとつずつ積み重ねていくことが、PFASから自分自身と家族の健康を守るための実践的な第一歩です。