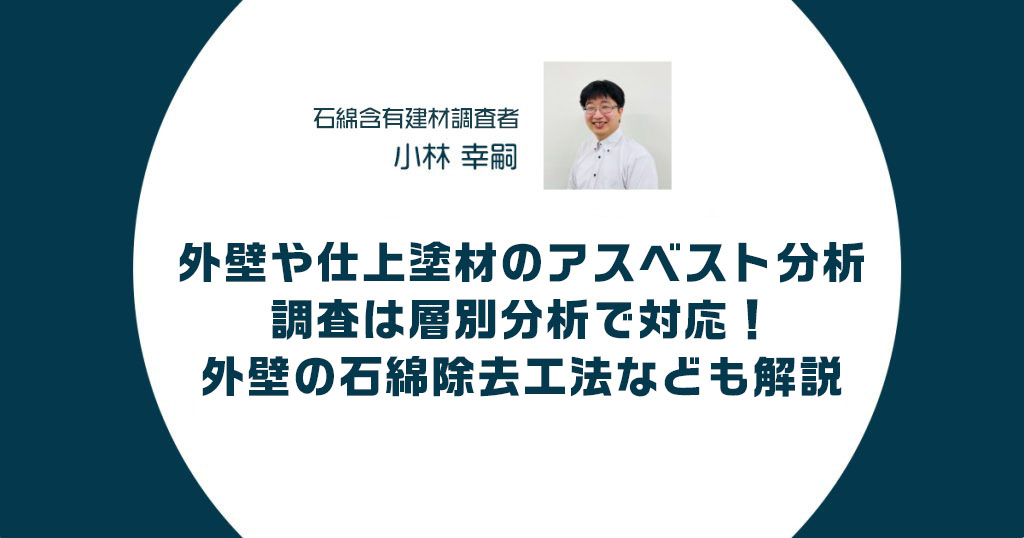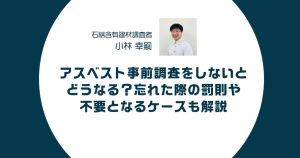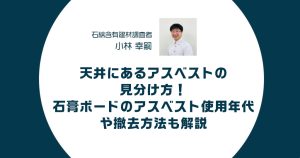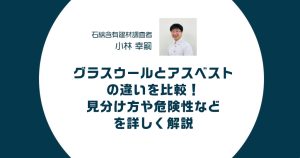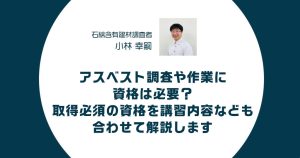築年数が経っている住宅やビルでは、外壁にアスベストが含まれている可能性があり、リフォームや解体工事の際には資格保有者による適切な調査と対処が必要です。
また、外壁材には層がいくつかあり、どこの層にアスベストが含まれるかで除去工法も変わるので、アスベスト含有が疑われる際には専門機関へ分析調査に出すことが望ましいです。
この記事では、外壁のアスベストの見分け方や分析方法、除去工法を分かりやすく解説します。
また外壁に含まれるアスベストのレベルや届出の対象についても説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
【安い・即日対応可・全国対応可】アスベスト定性分析 5営業日 当サイト経由なら11,400円(税抜)
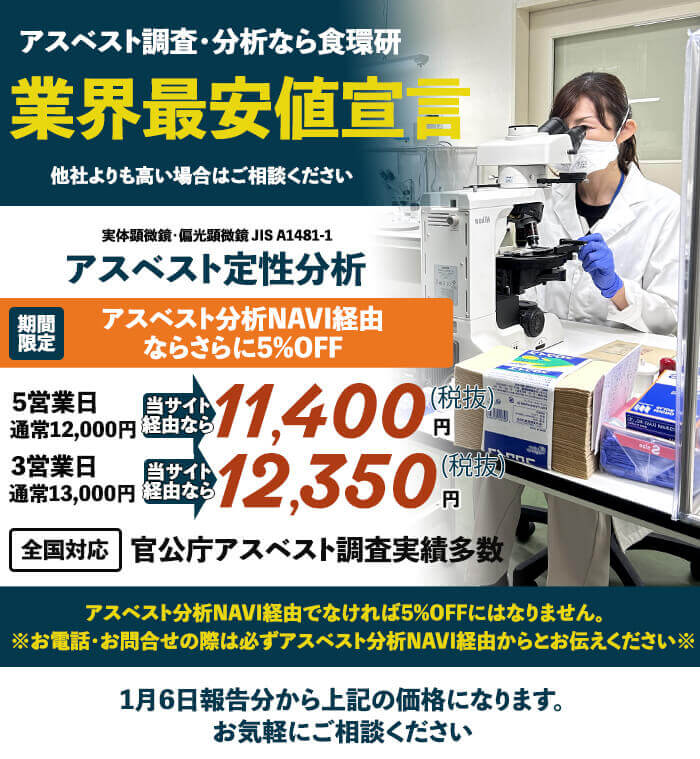

アスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFF
アスベスト分析・事前調査なら食環境衛生研究所にお任せください。お客様のおかげ弊社は設立し、26年間経ちました。そこで感謝の気持ちを込めて、このたび期間限定でアスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFFを開催させていただく運びとなりました。 金額は以下のとおりです。| 検査項目・期間 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 5営業日 | 11,400円 |
| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 3営業日 | 12,350円 |
| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 特急 | 19,000円 |
| 調査・採取 | 5万円〜※1 |
アスベスト材が使われている可能性のある外壁材の例
建築物の外壁には、さまざまな素材が使用されていますが、過去には耐久性や耐火性を高める目的でアスベスト(石綿)を含む外壁材が使用されていたことがあります。
特に、昭和から平成初期にかけて建設された建物では、アスベストが含まれている可能性があるため、リフォームや解体を行う際には注意が必要です。
この項目では、アスベスト含有の可能性がある外壁材をいくつかピックアップしてみました。
まずは以下を参考に、どんな外壁材にアスベストが含まれているのか、知っておくと良いでしょう。
| 外壁材の種類 | アスベスト含有の可能性 | 備考 |
|---|---|---|
| サイディング | 高い | 窯業系サイディングはアスベスト含有の可能性が高く、2004年(平成16年)に製造終了。複合金属系サイディングも1990年に製造禁止。 |
| 押出成形セメント板 | 高い | セメント板の一部には補強材としてアスベストが混入されていました。 |
| フレキシブルボード(スレートボード) | 高い | アスベスト含有のスレートボードは2004年(平成16年)に製造終了。 |
| ケイ酸カルシウム板第1種 | 可能性あり | 種類によってはアスベストを含有している場合があります。 |
| スレート波板 | 高い | セメントとアスベストを混ぜて作られたスレート波板は、アスベスト含有の可能性が高いです。 |
これらの外壁材は、見た目だけではアスベストの含有を判断することは困難です。
そのため築年数などの情報も照らし合わせた上で、専門機関に分析調査を依頼するのが望ましいといえます。
また上記以外にも、外壁の仕上げ材や下地調整剤にもアスベストが含まれている可能性があります。
サイディング

画像引用:目で見るアスベスト|国土交通省
サイディングは建物の外壁に使用される外装材の一種で主に外壁を保護し見た目を整える用途で使われます。
木材、金属、ビニール、セメント、石材などさまざまな素材で作られており、外部の風雨や温度変化、紫外線から建物を守る役割を果たします。
サイディングは耐火性のあるアスベストと混合されて活用されていたこともあり、「石綿含有建材複合金属系サイディング」「石綿含有窯業系(ようぎょうけい)サイディング」などの外壁材が過去にありました。
押出成形セメント板

画像引用:目で見るアスベスト|国土交通省
押出成形セメント板とは、セメントと補強繊維を混ぜ合わせ、押出成形機で成形して作られる建材のことです。
主に外壁や間仕切り壁、軒天などに使用されており、強度や耐久性に優れていることから、多くの建築物で広く使われていました。
1980年代から2000年代初期にかけて製造された押出成形セメント板の中には、補強材としてアスベスト(石綿)が含め、耐火性などを高めて活用されていました。
フレキシブルボード(スレートボード)

画像引用:目で見るアスベスト|国土交通省
フレキシブルボード(スレートボード)は、セメントを主成分とし、補強繊維を混ぜて成形した建材です。
柔軟性があり加工しやすいことから、外壁材や軒天材、内装材など幅広い用途で使用されてきました。
湿度にも強かったので浴室の壁・天井、台所の壁など一般住宅の内装にも多く使用されていました。
ケイ酸カルシウム板第1種

画像引用:目で見るアスベスト|国土交通省
ケイ酸カルシウム板は、ケイ酸質材料(シリカ)と石灰質材料(カルシウム)を主成分とし、補強繊維を加えて高圧成形・硬化させた建材です。
建築物の内装や外装、天井、間仕切り壁などに使用されることが多く、耐火性・耐湿性に優れています。
ケイ酸カルシウム板には第1種と第2種があり、第1種は主に内装ボードや天井材などで使用されました。
また、石綿含有ケイ酸カルシウム板第1種はアスベストレベル3、第2種はレベル2とアスベストレベルも異なります。
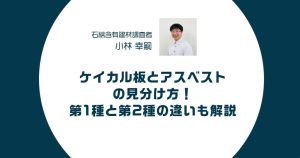
スレート波板

画像引用:目で見るアスベスト|国土交通省
スレート波板は、セメントと補強繊維を主成分とした波型の建材で、主に屋根や外壁に使用されました。
耐久性や耐火性に優れており、主に工場や倉庫、農業施設、仮設建築物などで広く使われてきました。住宅の屋根などにも使用されていたことがあります。
錆びや腐食にも強く、今現在でも昔のまま工場に使用されていることがあります。
外壁仕上塗材・下地調整剤にもアスベスト含有の可能性がある
外壁のアスベスト含有について考える際、外壁材そのものだけでなく、仕上塗材や下地調整剤にもアスベストが含まれている可能性があることを念頭に置いておくことが大切です。
特に、築年数の古い建物では、これら塗材・調整材にアスベストが使用されていたケースも事例として見られます。
アスベスト含有の可能性のある仕上塗材や下地調整剤の例としては、以下のようなものがあります。
| 材料名 | アスベスト含有の可能性 | 備考 |
|---|---|---|
| 吹き付けアスベスト含有塗料 | 高い | 過去に広く使用されていたため、注意が必要です。 |
| ケイ酸カルシウム系塗料(一部) | ありうる | 製造時期によってはアスベストが含まれている可能性があります。 |
| アスベスト含有下地調整剤 | 高い | 古い建物では、下地調整剤にアスベストが使用されていた可能性があります。 |
上記に関しても、見た目だけではアスベストの有無を判断することができないので、専門業者による分析が不可欠です。
また塗材や下地などの分析には、偏光顕微鏡法やX線回折法などの手法が用いられます。
外壁・仕上塗材のアスベストレベルは3に該当する
アスベストが含まれる外壁や仕上塗材の多くは、2021年4月の大気汚染防止法改正によりアスベストレベル3に分類されることとなりました。
その理由のひとつには、外壁等のアスベスト建材はアスベスト含有量が比較的低く、固形物なので通常の使用状態では飛散リスクが低いとされます。
前述した「サイディング」「押出成形セメント板」「スレート波板」などはどれもアスベストレベル3の建材となります。
除去時には原則そのまま取り外すなどの決まりがあります。
しかし、これらの建材がアスベストレベル3であっても、解体や改修工事などの際にアスベストが飛散する可能性があり、作業員の健康被害につながるリスクもあります。
また仕上塗材の中にはレベル1に該当するものもあるので、必ず分析調査を行なって、適切に対処する必要があります。
参考:目で見るアスベスト建材|厚生労働省
参考:特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材) 除去等作業時の石綿飛散防止|環境省
仕上塗材でもレベル1に該当するものがある
仕上塗材の中には吹付け施工によって表面に塗られるものがあり、それらはアスベストレベル1として取り扱うよう定められています。
具体的には石綿含有吹付パーライト、石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)などは法改正後も変わらずレベル1とみなし、各種届出と徹底した飛散防止対策が必要となります。
参考:大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正内容 |堺市公式HP
外壁・仕上塗材のアスベスト届出対象や基準
外壁や仕上塗材のアスベストに関する届出は、建物の規模やアスベスト含有量、工事の内容などによって異なります。
例えば、前述した吹付け工法による仕上塗材においてはレベル1とみなすので、石綿障害予防規則の届出対象となります。
吹付け工法ではない、手塗りやローラー工法の場合は届出の対象にはなりません。
また、下地調整材なども基本的に届出対象ではないですが、吹付け工法だと設計図書などから判明した場合などは届出対象となります。
このように、届出対象か否かの判定は様々ありますが、分かりやすく説明すると吹付け工法のもの、または疑われるものについては届出が必要ということになります。
参考:石綿含有建築用仕上塗材の石綿則等の適用について|中央労働災害防止協会安全衛生情報センター
外壁に使われるアスベストの見分け方
外壁にアスベストが含まれているかどうかを判断するのは、見た目だけでは非常に困難です。
そのため、いくつかの手がかりからアスベスト含有の可能性を推測し、専門家による分析調査を依頼することが重要です。
この項目では、外壁のアスベストを見分けるための方法を解説していきます。
アスベスト含有の可能性がある年代と建築年代を照らし合わせる
アスベストは、1970年代後半から2006年の全面禁止まで、様々な建築資材に使用されていました。そのため、建築年代が古いほど、アスベストが含まれている可能性が高くなります。
特に、1980年代以前の建築物では、アスベスト含有建材の使用率が高かったとされています。
| 建築年代 | アスベスト含有の可能性 | 備考 |
|---|---|---|
| 1980年代以前 | 高い | アスベスト含有建材が多く使用されていた時期 |
| 1980年代~2000年代前半 | 中程度 | アスベストの使用が減少傾向にあった時期 |
| 2000年代後半以降 | 低い | アスベストの使用が全面禁止された後の時期 |
建築年代は、建物の設計図書や登記簿などを確認することで判明します。
また、使用建材の販売期間も確認することで、アスベスト含有製品か否かも分かります。
外壁材の種類や製品名を調べる
アスベストは、サイディング、スレート屋根、押出成形セメント板など様々な外壁材に使用されていましたが、アスベストが含まれる年代のものかどうかは製品名などをみなければ判明できないケースもあります。
そのため、外壁材の種類に加えて製品名なども特定することで、アスベスト含有の有無を判定することができます。
外壁材の種類は、建物の外観や材質を直接確認するか、設計図書などを参照することで判別できます。
分析調査をおこなう
外壁のアスベストを見分けるためには最終的に専門機関に分析調査を依頼することで、アスベスト含有の有無を確実に判断できます。
まず主に顕微鏡を使用した分析となり、JIS規格に準拠した分析「JIS A 1481-1(偏光顕微鏡法)」と「JIS A 1481-2(X線回折法)」によって有無や濃度を正確に測定します。
外壁特有の仕上塗材や下地調整材の層がいくつか重なっている状態においても、層別分析(JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法のみ可能)で層ごとのアスベスト含有判定ができます。
これらの分析方法を次の項目で詳しく解説します。
外壁に使われるアスベスト分析の方法
外壁材にアスベストが含まれているかどうかを判断する主な分析方法は、JIS A 1481規格群に準拠した分析方法が用いられます。
代表的な方法として、偏光顕微鏡法とX線回折法がありますが外壁のアスベスト分析調査ではJIS A 1481-1(偏光顕微鏡法)を用いて分析を進めます。
JIS A 1481-1(偏光顕微鏡法)を用いた層別分析を検討
JIS A 1481-1は、偏光顕微鏡を用いた定性分析方法です。
アスベストは偏光に対して特有の光学的性質を示すため、この性質を利用してアスベストの有無を調べます。
具体的には、試料からアスベストと疑われる繊維を抽出し、偏光顕微鏡下で観察します。
分散色、消光角、伸長の正負、多色性などの光学的特性を調べ、アスベストの種類を特定します。鉱物の形態をしっかり見分けられ、誤分析が少ない分析方法ともいえます。
また、JIS A 1481-1は層別分析を行うことが可能で、アスベスト含有が疑われる層の特定も可能になります。
ただし、人の目で判定するので、含有の有無は分かりますが詳しい含有量は判定できません。
- 簡便で迅速な分析が可能
- 定量分析には不向き
- 比較的低コスト
- 熟練した技術者の経験が必要
- アスベストの種類特定が可能
- 微量なアスベストの検出が困難な場合がある
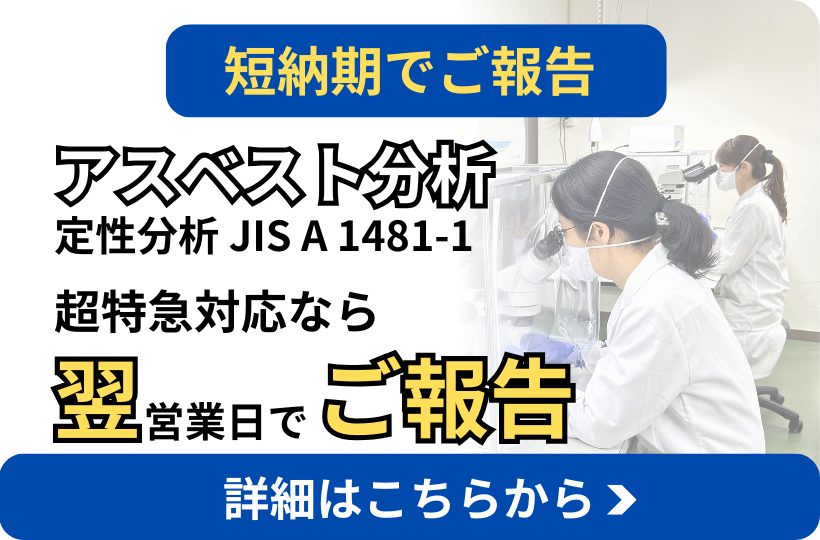
「JIS A 1481-1」での分析後は定量分析(JIS A 1481-2)を省略できる
まず、JIS A 1481-1(偏光顕微鏡法)はアスベストの有無を、JIS A 1481-2(X線回折法)はアスベストの含有量を調べます。
実際には「アスベストが含まれているかどうか」が重要で、含まれているなら含有量に関わらず適切に除去するというのが一般的なのでJIS A 1481-1(偏光顕微鏡法)のみで十分なケースが多いです。
アスベストが検出された場合や、より正確な含有量を知りたい場合は定量分析も必要となりますが、定量分析に関しては義務にはなっていません。
では、定量分析の必要性は何かというと、定量分析の結果における除去工法や費用算出に役立ちます。
ただ、定性分析でアスベストが検出されなかった場合は定量分析は不要となります。
また、注意点として定量分析(JIS A 1481-2)は検体を粉砕するため層別分析ができません。
そのため、今回のテーマである外壁のアスベスト調査では向いていない分析方法となり、省略が可能となっています。
外壁アスベストの除去前には分析調査を
外壁のアスベスト除去工事は、高額な費用と複雑な作業を伴います。
そのため、安易に工事を始める前に、必ずアスベストの分析調査を実施することが重要です。
分析調査によってアスベストの有無、種類、含有量を正確に把握することで、適切な除去工法の選定、安全な作業計画の立案が可能になります。
アスベスト含有層の場所によって除去工法が変わる
アスベスト含有層の位置や状態によって、最適な除去工法は大きく異なります。
例えば、外壁表面にアスベスト含有塗料が塗布されている場合と、外壁材自体にアスベストが含まれている場合では、除去方法が全く異なります。
工期も変わってくるので、除去作業前の分析調査は必須ともいえるでしょう。
分析調査によって複数の層に含まれるアスベストの含有場所を特定することで、より効率的かつ安全な除去工法を選択できます。
| アスベスト含有層の位置 | 考えられる除去工法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 外壁表面の塗料 | ウォータークリーン工法、剥離工法など | 塗料の厚さ、接着力などを考慮する必要がある |
| 外壁材内部 | 解体工法など | 周辺へのアスベスト飛散防止対策を徹底する必要がある |
| 外壁材と下地材の間 | 層別剥離工法など | 下地材へのダメージを最小限に抑える必要がある |
分析のタイミングの一例「改修・解体工事の設計段階での分析実施」
アスベスト分析調査は、前述した通り、除去作業の工事着手前に実施することが理想的です。
特に、設計段階で分析調査を実施することで、より適切なアスベスト対策を設計に織り込むことが可能になり、工期短縮やコスト削減にも繋がります。
また、後工程でのトラブルを未然に防ぎ、スムーズに工事を進めることができるでしょう。
もし、改修・解体工事の設計後に分析を行なった場合、分析結果でアスベストが検出された際には設計変更が必要になる可能性があります。
設計変更に伴って、工期の遅延や追加費用発生のリスクも生まれるので、やはり設計前に分析調査をおこなうのが良いでしょう。
外壁アスベストの除去工法
外壁のアスベスト除去は、アスベストの種類や含有量、外壁材の種類、建物の構造など、様々な条件を考慮して最適な工法を選定する必要があります。
また、塗材にアスベストの含有が認められる場合、含有される層がどこかによっても工法が変わります。
まずは、代表的な2つの除去工法「ウォータークリーン工法」と「剥離工法」についてそれぞれ解説します。
※どちらの工法を選択するかは、アスベストの含有量、外壁材の種類、建物の構造、予算、環境への配慮など、様々な要因を総合的に判断して決定する必要があります。
ウォータークリーン工法(高圧水)
ウォータークリーン工法は、高圧の水を噴射してアスベストを含む塗膜や外壁材を剥離・除去する工法です。
集塵装置と併用することで、アスベスト飛散のリスクを最小限に抑え、作業員の安全性も確保して作業ができます。
実際の使用方法としては、機械を壁に押し当てて高圧の水を噴射しつつ外壁を剥離し、剥離物は洗浄水と一緒にそのまま装置に吸引される仕組みになっています。
廃棄物量が少なく、環境への負担も軽減できる点がメリットで、作業効率も高いため工期の短縮にも繋がっている点も評価すべき点といえるでしょう。
ただし、高圧洗浄をおこなうので全てのアスベスト含有材に適用できるわけではなく、建材の種類や劣化状況によっては、他の工法を選択しなければならないケースがあります。
- 粉塵飛散を低減
- 水のみを使用するので環境にやさしい
- 吸引した廃棄物の処理が簡単
- 高圧洗浄機が必要
- 洗浄できない建材がある
- 水による建材への影響の可能性
- 下地処理が必要な場合がある
剥離工法(剥離剤の使用)
剥離工法は、アスベスト含有材に剥離剤を塗布し、塗膜を柔らかくしてから除去する工法です。
この工法は、ウォータークリーン工法では除去が難しい、複雑な形状の建材や、脆い建材にも対応できるのが特徴です。
剥離材を塗ると、スクレーパーなどの手工具でペラっと剥がれていくので大掛かりな装置が必要ありません。またウォータークリーン工法のような作業時の騒音が無いのも良い点です。
ただし、外壁の仕上材と剥離剤の相性によっては、剥離効果が期待できないこともあるので、どの剥離剤なら有効かを前もって決めておくことが大切です。
- 複雑な形状の建材にも対応可能
- アスベスト飛散リスクの低減(適切な対策を講じた場合)
- 脆い建材にも対応可能
- 騒音などが出ない
- 作業工程が複雑
- 剥離剤による環境への影響
- 熟練した技術が必要
外壁のアスベスト分析はどこに依頼する?選ぶポイントは?
外壁のアスベスト分析は、専門知識と顕微鏡などの分析設備を備えた機関に依頼することが重要です。
特に定性分析などに関しては、アスベストの特性などに熟知している人の分析判定が必要なのと、そもそも「JIS規格」に対応しているというかどうかも外せないポイントです。
外壁のアスベスト分析機関をどう選べば良いかを詳しく解説していきます。
分析機関を選ぶ際には、以下の点を考慮しましょう。
- 分析調査の資格があり認定を受けているか
- JIS規格の定性・定量分析をおこなっているか
- 外壁のアスベスト分析における実績や経験
- 分析費用や納期のスピード感
- 分析調査機関のエリア
- 分析調査結果の報告書の質
- アフターフォロー
分析調査の資格があり認定を受けているか
JIS A 1481に準拠した分析を実施できる資格や認定を受けている機関を選びましょう。
ISO/IEC 17025などの国際規格に適合した分析機関であれば、より信頼性が高いので安心です。
JIS規格の定性・定量分析をおこなっているか
JIS A 1481-1(偏光顕微鏡法)定性分析とJIS A 1481-2(X線回折法)定量分析の両方に対応している機関が理想的です。
また、分析対象となる外壁材の種類や状況に応じて適切な分析方法を判断、選択できる知識を持っている調査者がいるかも重要です。
アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社食環境衛生研究所までお問い合わせください。
外壁のアスベスト分析における実績や経験
外壁材のアスベスト分析の実績が豊富で、様々な種類の建材に対応できる経験を持つ機関を選びましょう。
過去の事例や分析結果の精度などを確認すると安心です。
分析費用や納期のスピード感
費用と納期は事前に確認しましょう。
相場は3~5万円程度とされていますが、分析方法やサンプル数、分析項目によって変動します。複雑な分析や大規模な調査の場合は、費用や納期が長くなる可能性があります。
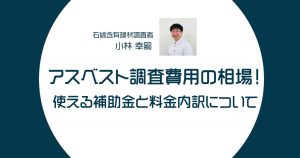
分析調査機関のエリア
依頼する地域で対応可能な機関を選びましょう。遠方の機関に依頼すると、サンプルの輸送費用や時間がかかります。
分析調査結果の報告書の質
分析結果を分かりやすくまとめた報告書を作成してくれるか確認しましょう。
報告書の内容は、今後の対策を検討する上で非常に重要です。
アフターフォロー
分析結果に関する相談や質問に丁寧に対応してくれる体制が整っているか確認しましょう。
例えば、分析結果に疑問がある際に迅速かつ丁寧に対応してくれる分析機関だと安心です。
不明な点があれば、すぐに相談できる体制が整っていることも大切なポイントです。
まとめ
外壁のアスベストは見た目だけで判断することが難しいです。
また仕上塗材・下地調整剤などが使われているので、層の内部にアスベストが存在する可能性もあります。
そのため、外壁アスベストを調査する際にはより詳細な分析調査が必要で、さらに層別分析でどこの層にアスベストが含まれているのかも判定しておかなければなりません。
このことから、JIS規格の分析調査が行える専門機関に依頼することが望ましいといえます。
分析調査を依頼する際には複数の分析機関に見積もりを依頼し、比較検討しておくのが良いでしょう。
費用だけでなく、分析規格や対応の迅速さ、報告書の対応様式や分かりやすさ、アフターフォロー体制なども考慮して、最適な分析機関を選びましょう。
早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。
アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。