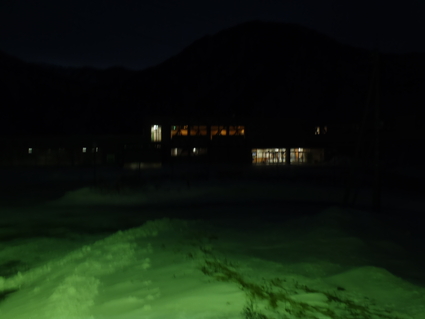今年は例年より寒い日が続くような今日この頃、
いかがお過ごしですか?
「寒い」から家を出たくないという気持ちもわかりますが、
ここ群馬には「寒い」からこそ見ることができる絶景も多くあります。
私が最近はまっているのは、「滝巡り」。
夏場の水量の多い「ドーッ」っとダイナミックに流れ落ちる滝も好きですが、
凍結して氷柱状になっている滝もまた幻想的であります。
最初の画像は南牧村の「像ヶ滝」30M級の滝です。
群馬県と長野県の堺に位置する南牧村は、その特殊な地形から、
数多くの大きな滝が存在し、滝マニアとしては有数のスポットです。
次の画像は「麻苧(あさお)の滝」40M級の滝です。
安中の碓氷峠から妙義山(丁須の頭)に登る途中にある滝です。
よく画像を見ると滝の下の方に人の姿があるので、
この滝がどれだけ高いかがわかります。
冬の散歩に是非オススメです。
写真だと伝わりづらいと思いますが、音もない静かな新雪の中、
朝日に照らされた巨大な氷柱が、きらきらと輝く姿はまさに圧巻ですよ。
(場所により歩道が凍結している所もあるので、
お出かけの際は十分にお気をつけ下さい。)
食環研登山部として、本当は雪山の高山にも挑戦したいのですが、
まだ装備が不十分なので、まずは低山で滝巡りなど愉しみつつ、
体力作りをしている今日この頃です。
もし、オススメの滝や洞窟など面白い自然スポットなどをご存じであれば、
来週にでも愛車(二輪)で攻めに行くので、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。