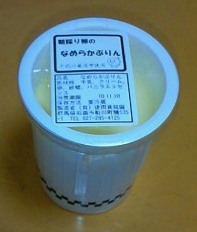宮崎県で今年2例目となる鳥インフルエンザウイルスの感染が確認された。宮崎県新富町の採卵養鶏農場で23日、高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いのある鶏が見つかり、遺伝子検査で高病原性の「H5亜型」ウイルスと確認された。
鳥インフルエンザ感染は宮崎市の農場に続き同県では今年2例目です。
この農場は県内最大規模の養鶏団地の一角に位置し、農林水産省の対策本部は感染拡大を防ぐため、団地の約41万羽すべてを殺処分する方針を決定しました。
先日、北海道でも野鳥から強病原性鳥インフルエンザウイルスの感染が確認されたばかり、感染拡大が心配されます。