目次
膣カンジダ症とは?
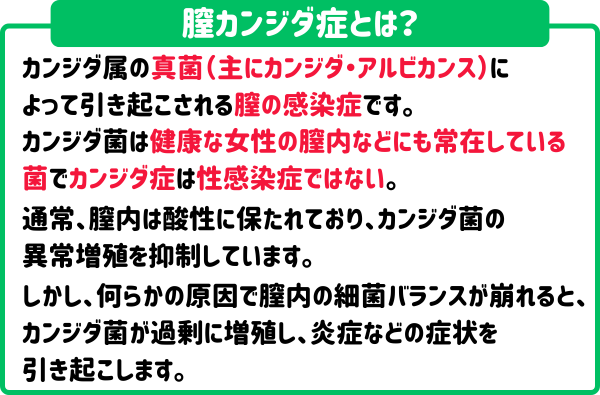
膣カンジダ症は、カンジダ属の真菌(主にカンジダ・アルビカンス)によって引き起こされる膣の感染症です。 まず覚えておきたいことは、厳密にいうとカンジダ症は性感染症ではないということです。カンジダ菌は健康な女性の膣内などにも常在している菌です。 通常、膣内は乳酸菌によって酸性に保たれており、この環境がカンジダ菌の異常増殖を抑制しています。 しかし、何らかの原因で膣内の細菌バランスが崩れると、カンジダ菌が過剰に増殖し、炎症などの症状を引き起こします。 つまり、性行為がなくてもカンジダ症を発症するケースがあるということです。 成人女性が生涯に一度は経験するとされており、決して珍しい疾患ではありません。 かゆみやおりものの変化など、日常生活に影響を与える症状が現れることもあるのと、再発することも珍しくはないため、カンジダ症の予防方法を正しく理解しておくことが重要です。 参考:カンジダ症|国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ
膣カンジダが発症する仕組みと原因を詳しく解説
膣カンジダ症はなぜ発症するのか、再発するのか原因を詳しく知って対策したいと思っている方もいるかと思います。 まず膣カンジダ症の発症には、膣内環境の変化が深く関わっています。正常な膣内は、ラクトバチルス(乳酸菌)が優勢な状態で、常時弱酸性に保たれることで外部からの菌や常在菌の異常増殖を防いでいます。 ところが、次に挙げるような要因で膣内環境のバランスが崩れると、カンジダ菌が急速に増殖し、カンジダ症状を引き起こします。【カンジダ症の主な発症要因】
次で挙げるカンジダ症の発症要因は、一般的に医学界で広く認められているものです。■ホルモンバランスの変化
妊娠中、月経前後、更年期などにエストロゲンレベルが変化すると、膣内環境も変わります。特に妊娠中はエストロゲンの増加により膣内のグリコーゲンが増え、カンジダ菌の栄養源となるため発症リスクが高まります。■抗生物質の使用
抗生物質は病原菌を殺菌する一方で、膣内の有益な乳酸菌も減少させてしまいます。その結果、カンジダ菌が増殖しやすい環境が作られてしまいます。■免疫力の低下
糖尿病、HIV感染、がん治療中、過度のストレス状態などでは免疫機能が低下。カンジダ菌の制御ができなくなり発症リスクが高まります。■生活習慣要因
通気性の悪い下着の着用、過度な洗浄、湿った環境の持続などが膣内環境の悪化を招きます。膣カンジダが疑われる症状やサイン
膣カンジダ症は、初期段階では性器の軽微な不快感から始まることが多く「何となく調子が悪い」と感じる程度の場合もあります。しかし、症状が進行すると日常生活に大きな支障をきたすほどの症状が現れることがあります。 膣カンジダ症には特徴的な症状パターンがあり、それを知っておくことで早期の段階で適切な対処が可能になるので、頭に入れておくと良いでしょう。 膣カンジダ症の特徴的な症状は以下の通りです。
※以下で挙げる症状は個人差があり、すべての症状が必ず現れるわけではありません。軽度の場合は軽いかゆみのみのこともあるでしょう。
ただし、症状の程度は人によって異なるため、症状が出たからといって必ずしもカンジダ症とは限りません。
症状が似ている性感染症のケースも考えられますので、検査をおこない適切な判断のもと治療を進めることが重要です。
外陰部の強いかゆみ
最も特徴的な症状で、我慢できないほどの強いかゆみが生じます。特に夜間や入浴後に悪化することが多く、生活の質を著しく低下させます。白色のおりものの増加
「カッテージチーズ」や「酒粕」と表現される、白くてポロポロとした特徴的なおりものが増加します。通常、においはほとんどありません。外陰部の腫れと発赤
炎症により外陰部が赤く腫れ、時には小さな亀裂ができることもあります。排尿時・性交時の痛み
炎症による痛みで、排尿や性行為が困難になる場合があります。膣カンジダ症に似ている性感染症
膣カンジダ症と似た症状を示す性感染症はいくつか存在し、自己判断では見分けがつきにくい場合があります。そのため、正確な診断のためには医療機関での検査が欠かせません。トリコモナス膣炎
黄緑色の泡状で悪臭のあるおりものと強いかゆみを伴う症状が特徴です。外陰部の赤みなども現れます。性感染症であるためパートナーへの感染も起こります。そのため同時治療が必要です。淋病・クラミジア感染症
膿性のおりもの、下腹部痛、発熱などを伴うことがあります。これらは性感染症であり、放置すると不妊の原因となる可能性があります。膣カンジダ症に似ている性感染症ではない病気
細菌性膣症
魚臭いにおいのあるおりものが特徴で、かゆみは軽度です。膣内のpHが上昇し、ガードネレラ菌などが増殖することで起こります。萎縮性膣炎
更年期以降に見られることが多く、エストロゲン減少による膣粘膜の萎縮が原因です。 症状だけでの自己判断は危険であり、必ず医療機関での適切な診断を受けることが大切です。膣カンジダ症の治療方法
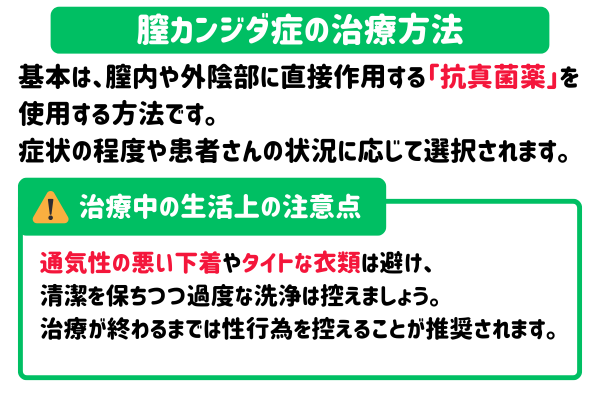
膣カンジダ症の治療では、原因となるカンジダ菌の増殖を抑えることが最も重要です。 基本となるのは、膣内や外陰部に直接作用する「抗真菌薬」を使用する方法です。 市販薬として薬局で購入できるものもありますが、自己判断での使用では症状が改善しなかったり、再発を繰り返してしまうこともあります。 そのため、症状が強い場合や繰り返す場合には、婦人科を受診して適切な治療を受けることがすすめられます。
抗真菌薬による薬物治療
膣カンジダ症の治療は、抗真菌薬を用いた薬物療法が基本となります。治療薬には内服薬と外用薬があり、症状の程度や患者さんの状況に応じて選択されます。膣錠(膣坐薬)
カンジダ症に対する最も一般的な治療法で、膣内に直接薬剤を挿入します。主な薬剤としてクロトリマゾール、ミコナゾール、フルコナゾール(内服薬が主流)などがあります。 通常、1回の使用で効果が期待できますが、症状が重い場合は数日間連続使用することもあります。外用クリーム
外陰部のかゆみや炎症に対して使用します。膣錠と併用することで、より効果的な治療が可能になります。内服薬
重症例や再発を繰り返す場合に使用されます。フルコナゾールが代表的で、通常1回の服用で治療が完了します。 治療効果は通常2〜3日で現れ始め、1週間程度で症状が改善することが多いでしょう。治療中の生活上の注意点
治療期間中は、膣内の環境を整えることが重要です。 通気性の悪い下着やタイトな衣類は避け、清潔を保ちつつ過度な洗浄は控えましょう。 また、治療が終わるまでは性行為を控えることが推奨されます。パートナーに症状がある場合は同時に治療することもあります。繰り返す膣カンジダ症の最も重要な予防方法は?
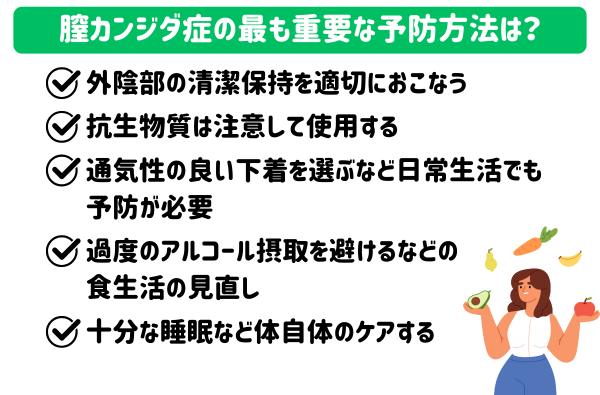
膣カンジダ症の予防において最も重要なのは、冒頭でもお伝えした通り、「膣内の正常な細菌叢を維持すること」です。 膣内の環境が崩れてしまうようなことは避けることが予防につながります。 そのためには以下で挙げることが特に重要となります。
外陰部の清潔保持を適切におこなう
匂いが気になるなどの女性は特に過度な洗浄をしてしまいがちですが、過度な洗浄は逆効果です。(異常な匂いの場合は別の感染症の疑いがあるので、検査を行いましょう) 外陰部は石鹸を使用しても構いませんが、膣内は自浄作用があるため過度に洗浄する必要はありません。 また、ビデや膣洗浄は正常な細菌叢を破壊する可能性があるため、日常的な使用は避けるべきでしょう。抗生物質は注意して使用する
抗生物質は膣カンジダ症の予防において特に注意が必要な薬剤です。 不必要な抗生物質の使用は控え、処方された場合は医師の指示通りに服用することが最も重要です。 自己判断での中断や、症状が改善したからといって途中でやめることは避けましょう。日常生活でできる予防まとめ
通気性の良い下着を選ぶ
綿100%の通気性の良い下着を選び、きつすぎないものを着用しましょう。 ナイロンやポリエステルなどの化学繊維は湿気をこもらせやすいため、避けることをおすすめします。 ムレは細菌や真菌(カンジダ菌)の繁殖を助長し、再発のリスクを高めてしまいます。衣服の管理
濡れた水着や運動着は速やかに着替え、湿った状態を長時間維持しないことが重要です。また、洗濯後は十分に乾燥させてから着用しましょう。月経時のケア
月経中は経血によって膣まわりが湿った状態になりやすく、カンジダ菌が好む環境が整ってしまいます。 そのため、ナプキンやタンポンはこまめに交換し、長時間同じものを使用しないようにしましょう。蒸れや経血の停滞は、かゆみや炎症を悪化させる原因となります。 月経カップを使用する場合も注意が必要です。使用前後には必ず手を清潔にし、カップは適切に洗浄・消毒したうえで再使用してください。 不十分なケアは膣内環境を乱し、感染症リスクを高める可能性があります。 また、月経中は膣や外陰部が敏感になりやすいため、香料入りナプキンやおりものシートの使用は避けるのが望ましいとされています。無香料・低刺激タイプを選ぶことで、肌トラブルやかゆみを軽減できます。食生活の見直しでできる予防まとめ
糖分の摂取制限
高血糖状態はカンジダ菌の増殖を促進します。糖尿病患者では血糖コントロールが特に重要ですが、健康な方でも過度な糖分摂取は控えめにすることが望ましいでしょう。乳酸菌やビフィズス菌(プロバイオティクス)などの摂取
ヨーグルトや納豆、キムチなどの発酵食品に含まれる乳酸菌は、腸内環境を整えるだけでなく、膣内の正常細菌叢(デーデルライン桿菌)を保つサポートになると考えられています。正常な細菌叢は膣内を弱酸性に保ち、カンジダ菌の過剰な増殖を防ぐ働きがあります。 ビフィズス菌や乳酸菌を含むサプリメント(プロバイオティクス)の摂取も、再発予防の補助的な方法として注目されています。ただし、現時点では「確実にカンジダ症を予防・改善できる」と断言できる科学的根拠は十分ではなく、研究が進められている段階です。 そのため、日常の食生活で発酵食品をバランスよく取り入れたり、整腸を意識することが、間接的に膣内環境の改善や再発予防につながると考えるとよいでしょう。バランスの取れた食事
免疫機能を健やかに保つためには、ビタミン・ミネラルをはじめとした栄養素をバランスよく摂取することが欠かせません。 特に、ビタミンB群やビタミンC、亜鉛、鉄分などは免疫調整に深く関わります。 偏った食事や過度な糖質摂取は腸内環境を乱し、カンジダ菌の増殖を助長する可能性があるため注意が必要です。 日々の食事では、野菜・果物・魚・大豆製品などを組み合わせ、栄養のバランスを意識しましょう。過度のアルコール摂取を避ける
過度のアルコール摂取は肝臓の機能を低下させ、免疫バランスに悪影響を及ぼす可能性があります。 また、アルコールによって腸内環境が乱れることもあり、膣内フローラのバランス維持に間接的な悪影響を与えると考えられます。 特に砂糖を多く含むカクテル類は血糖値を急上昇させ、カンジダ菌の増殖を助長する可能性も指摘されています。体自体のケアでできる予防まとめ
ストレス管理
慢性的なストレスは免疫力を低下させ、カンジダ症の再発リスクを高めます。 ウォーキングやストレッチなどの軽い運動、趣味の時間を持つこと、深呼吸や瞑想などのリラクセーション法を取り入れることが効果的です。十分な睡眠
睡眠不足は免疫機能の低下に直結します。できるだけ規則正しい時間に就寝し、質の良い睡眠を7〜8時間確保しましょう。 眠る前にスマホやパソコンのブルーライトを避けることも、安眠につながります。規則正しい生活リズム
不規則な生活はホルモンバランスを乱し、膣内環境の悪化やカンジダ症の再発に影響する可能性があります。 なるべく食事・睡眠・活動のリズムを一定にし、体に過度な負担をかけないよう心がけることが大切です。喫煙を控える
喫煙は血流を悪化させ、組織の修復力や免疫応答を低下させることが知られています。 喫煙女性は膣内の善玉菌(乳酸菌)の割合が低下する傾向があると報告されており、その結果、膣内環境が乱れやすくなるとされています。これはカンジダ症だけでなく、細菌性膣症などのリスクにもつながります。 参考:PubMed Central(PMC)膣カンジダ症になってしまった時はどうする?
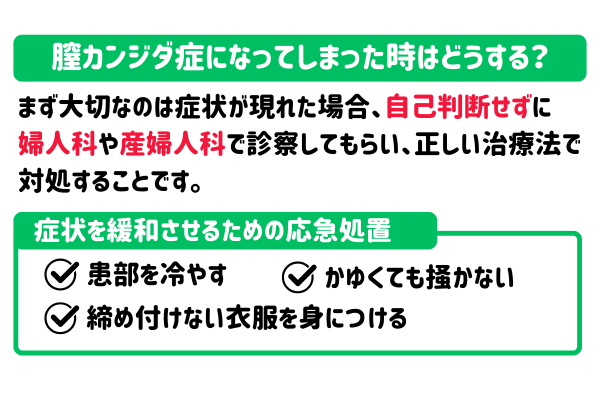
膣カンジダ症の症状が現れた場合、まず大切なのは自己判断せずに婦人科や産婦人科で診察してもらい、正しい治療法で対処することです。 ここでは、受診の流れから応急処置、再発を防ぐためのポイントまで、実際にかかってしまった時の対処法を解説します。
産婦人科・婦人科を受診する
膣カンジダ症を疑う症状が現れた場合、まずは産婦人科または婦人科を受診することが最も重要です。 自己判断による市販薬の使用は、症状を一時的に緩和させても根本的な解決にはならない場合があります。医療機関で正しい診断をしてもらうことが重要
医療機関では、顕微鏡検査や培養検査などによって正確に診断されます。これにより、膣カンジダ症なのか、あるいは他の疾患なのかを明確に区別できます。 症状が似ているからといって自己判断で治療を始めてしまうと、正しい治療を受ける機会を逃す恐れがあります。検査の流れ
受診時には、問診・視診・内診が行われます。膣分泌物を採取して顕微鏡でカンジダ菌の有無を確認し、必要に応じて培養検査で菌の種類や薬剤の効きやすさを調べることもあります。膣カンジダの検査を行うタイミングは?
カンジダと疑われる気になる症状があれば早めに検査(受診)をしましょう。 かゆみ・おりものの変化・外陰部の炎症などの症状が出たら、まずは婦人科(産婦人科)で受診し、診察してもらいます。 また、必要に応じて培養やPCR検査を受けるのが基本です。 臨床所見で判断できることも多いですが、他の膣炎(細菌性膣症・トリコモナスなど)や性感染症との鑑別が必要なため、検査で確定することが望ましいです。症状を緩和させるための応急処置
医療機関を受診するまでの間、症状を少しでも軽減するための方法があります。患部を冷やす
かゆみがあまりに強い場合、清潔な濡れタオルで外陰部を冷やすことで一時的にかゆみの症状が和らぐことがあります。ただし、長時間の冷却は血流低下や凍傷的な刺激が出る恐れがあるため避けてください。締め付けない衣服を身につける
ゆったりとした衣服や下着を着用し、患部への刺激を最小限に抑えましょう。かゆくても掻かない
かゆみがあっても掻くことは避けてください。掻くことで炎症が悪化し、二次感染のリスクも高まります。膣カンジダ症に関するよくある質問
膣カンジダ症に罹っている時に性行為はしても大丈夫?うつる?
膣カンジダ症罹患中の性行為については、複数の観点から慎重な判断が必要です。 まず、膣カンジダ症は性感染症ではありませんが、性行為により男性パートナーに感染する可能性はあります。男性の場合、通常は症状が現れないことが多いのですが、包皮炎や亀頭炎を起こすことがあるでしょう。 また、炎症を起こしている膣や外陰部に摩擦刺激が加わることで、症状が悪化する可能性があります。治療効果も低下することが考えられるため、完全に治癒するまでは性行為を控えることを強く推奨します。 どうしても性行為を行う場合は、コンドームの使用により感染リスクを軽減できますが、完全な予防にはならないことを理解しておいてください。膣カンジダ症に効く市販薬はありますか?
現在、日本では膣カンジダ症に対する市販薬(OTC医薬品)が販売されています。主な成分はクロトリマゾールやミコナゾールなどの抗真菌薬です。 ただし、市販薬の使用には重要な注意点があります。 まず、過去に医療機関で膣カンジダ症の診断を受けたことがあり、同様の症状が再発した場合にのみ使用が推奨されます。 初回発症時や症状が不明確な場合は、必ず医療機関を受診してください。 市販薬を使用しても症状が改善しない場合、または悪化する場合は、速やかに医療機関を受診することが必要です。自己判断による長期使用は、かえって症状を複雑化させます。カンジダ予防にサプリは効果がある?
カンジダ症の再発予防を目的として、乳酸菌やビフィズス菌、オリゴ糖、ビタミン類を配合したサプリメントが市販されています。 これらは腸内環境や膣内の細菌バランスを整えることをサポートするとされますが、医学的に「サプリでカンジダ症を確実に防げる」と証明されているわけではありません。 サプリが役立つ可能性があるのは主に以下2つの点です。- 腸内環境を整えることで、間接的に免疫機能をサポートする
- 膣内細菌叢のバランスを整え、善玉菌の優位性を保つことを助ける
膣カンジダ症は完治する病気ですか?
膣カンジダ症は適切な治療により完治する疾患です。抗真菌薬による治療により、通常1〜2週間程度で完全に治癒します。 ただし、治療によりカンジダ菌の異常増殖は抑制されますが、カンジダ菌自体は膣内の常在菌であるため、完全に除去されるわけではありません。 正常な範囲内で存在し続けることになります。 問題となるのは再発です。約半数の女性が生涯に2回以上の発症を経験するとされており、年に4回以上再発する場合は「再発性膣カンジダ症」として特別な治療が必要になることがあります。膣カンジダは自然治癒する?
軽度の膣カンジダ症の場合、免疫力が正常であれば自然治癒する可能性はあります。膣内の自浄作用により、時間をかけて正常な細菌叢バランスが回復することがあります。 しかし、自然治癒を期待して症状を放置することは推奨できません。 理由としては、症状がさらに悪化する可能性があること、炎症が長期化することで膣や外陰部の皮膚に損傷を与える可能性があること、そして他の疾患を見落とすリスクがあることが挙げられます。 また、妊娠中の膣カンジダ症は分娩時に新生児に感染する可能性があるため、必ず治療が必要です。症状がある場合は、自然治癒を待つのではなく、適切な治療を受けましょう。男性の性器カンジダと女性の膣カンジダはどう違う?
男性と女性のカンジダ症には、発症頻度、症状、治療法において違いがあります。発症頻度は男性の方が低め
女性の膣カンジダ症は非常に一般的ですが、男性の性器カンジダ症の発症頻度は比較的低いとされています。これは男性器の構造上、菌が定着しにくいためです。症状の違い
女性では膣内のかゆみ、おりものの変化、外陰部の炎症が主症状ですが、男性では亀頭の発赤、かゆみ、白いカス状の分泌物、包皮の炎症などが見られます。男性の場合、排尿時の痛みを伴うこともあるでしょう。カンジダ症を発症しやすくなる要因の違い
女性では妊娠、月経、抗生物質使用などがリスク要因となりますが、男性では糖尿病、免疫力低下、包茎、不適切な陰茎衛生などが主なリスク要因です。治療法の違い
基本的には同様の抗真菌薬が使用されますが、男性では主に外用薬(クリームや軟膏)が使用され、女性のような膣錠は使用しません。 治療期間も女性よりも短期間で済むことが多いとされています。
あわせて読みたい

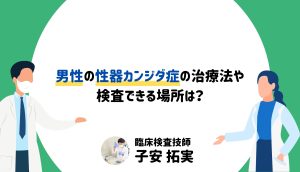
男性の性器カンジダ症の検査できる場所は?
男性の性器カンジダ症は、女性に比べて発症率は低いものの、免疫力の低下などで男性も発症します。 症状としては、性器のかゆみや痛み、亀頭周辺などに白い苔のような分...
膣カンジダ症かどうか、自宅で検査できる?
かゆみやおりものの異常があると「膣カンジダ症かもしれない」と考える方も多いですが、実際には細菌性膣症やクラミジア感染症など、似た症状を持つ病気が少なくありません。 そのため、自己判断だけで区別するのは非常に難しいのが現実です。 しかし、「忙しくてすぐに病院へ行けない」「周囲に知られるのが恥ずかしい」と感じる方も少なくないでしょう。 そんなときに役立つのが、郵送型のカンジダ症検査キットです。 自宅で簡単に検体を採取でき、匿名性が高いため、誰にも知られずに検査を受けられます。 結果は数日で確認できるため、早い段階で安心につながる行動が取れるのが大きなメリットです。 もちろん、陽性だった場合や症状が強い場合には、必ず産婦人科・婦人科での受診と適切な治療が必要です。 検査キットは「病院へ行くべきかどうか判断するための第一歩」として活用するとよいでしょう。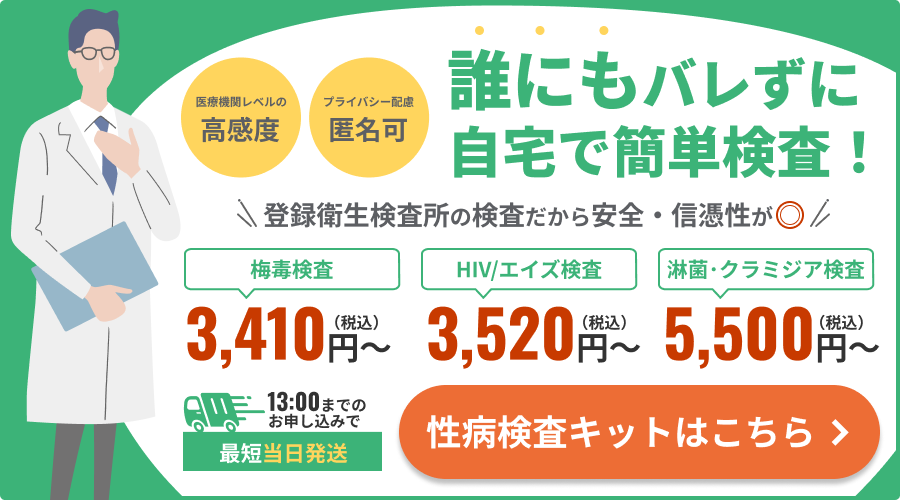
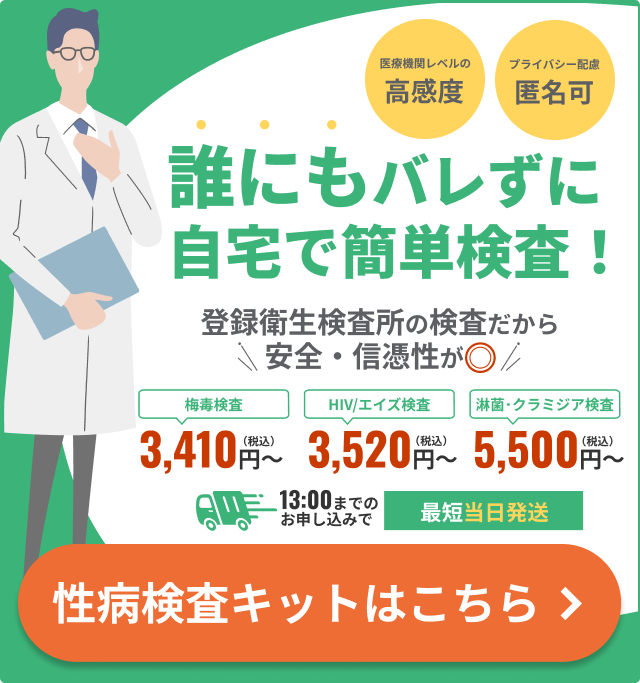

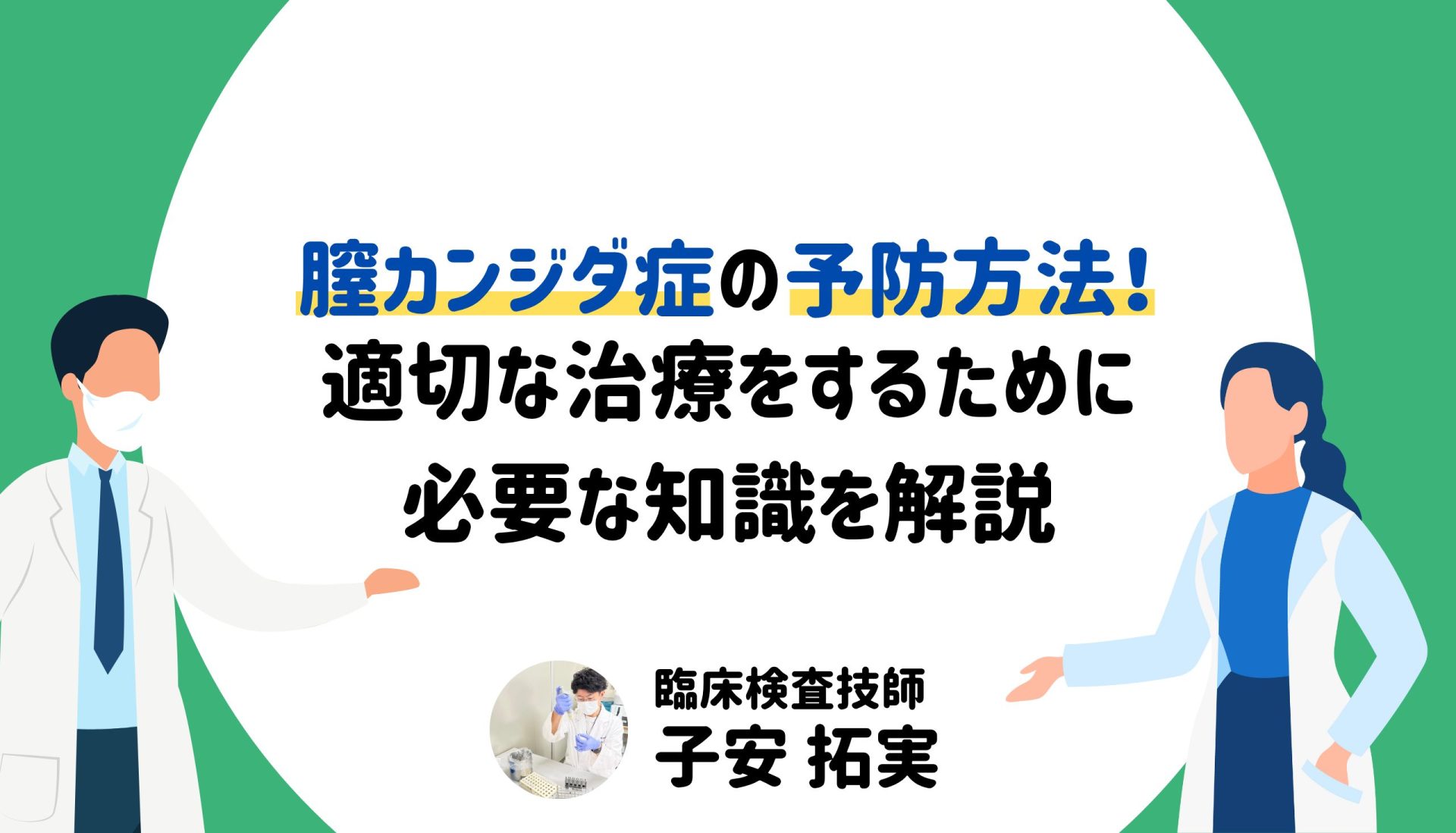

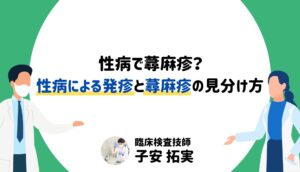

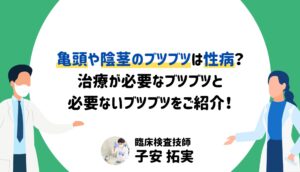
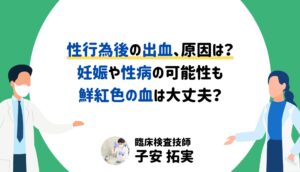
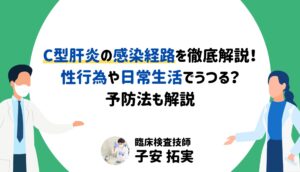
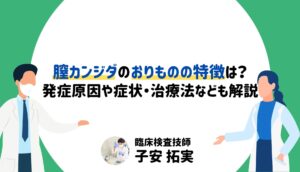
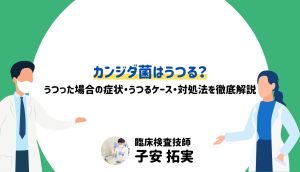
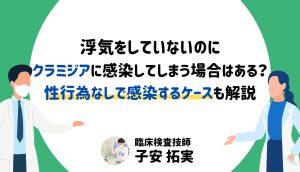
コメント