3月10日から31日まで、東京都調布市の空き地に首輪をつけたヤギ3頭が出没したようです。雑草の駆除を目的とした実験のためで、除草剤、草刈り機などを使わず、富山県からレンタルされたヤギもお腹いっぱいになる予定で、夏にも同様の実験をするようです。ヤギは紙を食べると言われています。昔の紙は多くが植物のみでできていたため食べられたようですが、今の紙は消化されず腸閉塞になる可能性があります。むやみに餌や紙を与えないようにしましょう。
バイオセキュリティ強化資材
バイオセキュリティ強化資材として、バイオセラミックス(BCX)という紹介されていた記事があった。ここで紹介されていたBCXは、材料として鶏糞を用い、それを還元焼結処理することで炭素と窒素原子が除去された無機物にした鶏糞由来BCXというものだった。この鶏糞由来BCXの効果は、非常に魅力的でトリインフルエンザウイルス、トリアデノウイルスを不活化するし、しかも長期間持続(記事では5ヶ月野外に撒いて風雨にさらしても効果あり)というデータが得られているそうだ。さらに、エサとして鶏への給餌も大丈夫とのこと。
微生物の感染源の主役級である鶏糞が、BCXに加工するとこんなにいいことづくめの材料になるなんて、これこそエコカー越えのエコ利用ではないかなと思う。今後は、抗微生物効果の詳細なメカニズムが解明されるのに注目したい。
生肉のお取り寄せ
鶏糞
飼料米
Dairy Japanどくしょかんそう
平成元年に9万4400戸あった採卵養鶏場が、現在では3110戸にまで減少しているそうです。
では、ブロイラー飼養戸数はどうなのか?
気になり、調べてみました。
平成18年2月現在で2593戸。
平成2年の調査時と比較すると3000戸近くも減っています。
採卵もブライラーも戸数は減少を続けています。
この背景には、
景気の悪化、
バイオエタノールや不作による飼料穀物の価格高騰(一時期より落ち着いてますが…)、
養鶏場周辺に住宅が出来、臭い等の苦情が出て継続が困難になる、
後継者不足、
などなど、いくつか要因があります。
そんな中、生き残ることができる養鶏家は、どのような養鶏家か?
それは、良いと言われることは貪欲に何でも実行し、本当に良かったものを取捨択一している養鶏家です。
私は前職でブロイラー業界に携わっていて、多くの養鶏家さんにお会いましたが、
このような養鶏家さんは成績も良く、実際に良い鶏を出荷してくれます。
企業として、個人としても、このような姿勢を見習っていきたいなと思います。
と、まぁ、硬い話は、ここまでにします。
自分としては、
ブログは基本、面白くて、楽しいものだと思っているので、
最後に、前の会社で作った絵をアニメにしたので載せてみました。
↓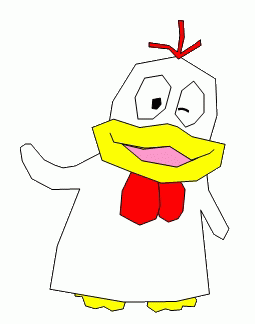
ただの鶏の絵です。お〇けとかじゃないですよ。
決して、おば〇じゃないですよ。
** 小此木 **
食品検査|食品分析|残留農薬|残留抗生物質
レジオネラ菌検査|ノロウイルス検査|食品アレルギー・アレルゲン検査
動物用体温計
農業経営統計調査
牛の妊娠診断
動物愛護管理法
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱い、その他動物の愛護に関する事項を定めて、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛および平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体および財産に対する侵害を防止することを目的とした法律です。平成18年6月1日から規制が強化され、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示を行う業者は、動物取扱業の登録を受けなければならなくなり、事務所ごとに専属の動物取扱責任者を1名以上配置することが義務付けられ、動物取扱責任者は自治体が開催する研修を年1回以上受講するよう決められています。日本は規制がやさしいという意見もあり、ココロない業者や飼い主を取り締まることがなかなかできていないのではないでしょうか。責任を持って取り組まれている方々も多くいらっしゃいますから、将来さらなる対策が望まれています。

