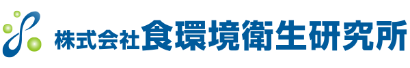レンサ球菌病
S. dysgalactiae subsp. dysgalactiae は血液加寒天培地上で直径0.2~0.7mmの微小集落を形成し、強いβ溶血性を示す。感染材料中の菌は双球菌~短連鎖状を示すが、液体培地中では長い連鎖を形成する。通常1~3週齢の子豚に関節の腫脹がみられる。一般的な臨床症状としては、発熱、元気消失、被毛の逆立ち、食欲減退などが観察される。心内膜炎の症例では著明な臨床症状は示さず、剖検時にのみ判明する。関節炎の症例では関節液の混濁、関節周囲の腫脹などが観察される。病理組織学的には好中球、マクロファージの浸潤とフィブリンの析出をともなう化膿性線維素性関節炎が観察される。豚から分離されるβ溶血性のC群レンサ球菌は当初“S.equisimilis”と命名され、その後長年にわたり本菌種名が用いられてきたが、1984年にDNA相同性試験によりLancefield血清群のC、G、L群菌は同一菌種でありS.dysgalactiaeと命名された。その後、Vandammeら(1996)により、家畜から分離されるC群およびL群菌はS.dysgalactiae subsp. Dysgalactiae、ヒトから分離されるC群およびG群菌はS.dysgalactiae subsp. equisimilis とすることが提案された。診断は主として菌分離以外に特異的なものはない。菌は関節液あるいはほかの主要臓器から血液加寒天培地を用いて容易に分離することが可能である。分離菌の同定はβ溶血性、そのほかの生化学的性状検査により行う。予防はペニシリン系の抗生物質あるいはテトラサイクリンなどの広域抗生物質を予防的に投与することで、その発病を抑制することができる。また、これらの抗生物質は治療薬としても有効である。また、一般的な予防対策として、衛生管理の徹底に努めることで発生を極力抑えることができる。<豚病学より抜粋>O-N100816