偏光顕微鏡の歴史と原理とは?
今回は偏光顕微鏡の歴史と原理について解説したいと思います。
偏光顕微鏡の歴史と原理
偏光は、フランスのマリュス(E.Malus,1775~1812)が1808年に発見したとされ、宮殿の窓の反射光を複屈折物質である方解石で観察している際に発見したといわれています。複屈折物質に光が入射すると複屈折という現象が発生し、スネルの法則(屈折の法則)に従う常光線と法則に従わない異常光線に分かれます。
イギリスのニコル(W.Nicol,1768~1856)は、1828年に二つの方解石プリズムを貼り合わせたニコルプリズムを発明しました。また、このニコルプリズムを用いた偏光装置を考案し、自然光から一定の振動方向をもつ直線偏光を得ることを可能にして岩石や鉱物の研究に活用しました。また、イギリスのタルボット(H.F.Talbot,1800~1877)は、偏光装置を活用し、1834年に偏光顕微鏡を発明したとされています。
第1の偏光装置により得られた直線偏光に対して振動方向が直角になるように第2の偏光装置を配置すると、直線偏光はカットされます。この状態をクロスニコルやクロスポーラ、または直交ニコルと呼びます。このときの第1の偏光装置をポラライザ(polarizer:偏光子)、第2の偏光装置をアナライザ(analyzer:検光子)と呼びます。二つの偏光装置の間に複屈折物質があると、ポラライザによって発生した直線偏光は複屈折物質を透過することで変化し、アナライザを通過して観察ができるようになります。
複屈折物質のない場所の光はカットされて暗黒となり、複屈折物質のある場所の光は観察ができるという性質は、偏光顕微鏡による偏光観察法の最も基礎的な原理であるといえます。
その後、アメリカのランド(E.H.Land,1909~1991)が、1929年に薄板状の偏光板を発明し、「ポラロイドpolaroid」と名付けました。彼は後の「米ポラロイド社Polaroid Corporation」の創業者です。偏光顕微鏡に使用するニコルプリズムは材料である大きくて良質な方解石が入手困難であったことから大変高価なものでしたが、ポラロイドは安価、なおかつ薄くて使いやすいという利点があり、ほとんどの偏光顕微鏡に採用されるようになりました。
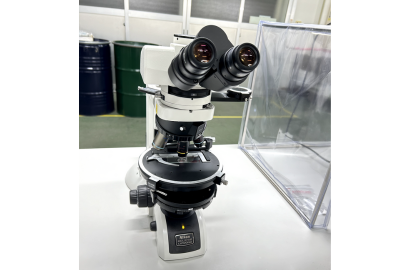
参考文献:It’s Not Just Rock-the Principle and Mechanism of Polarizing Microscope, and Its Various Use Takaki ISHIGUCHI 2020
