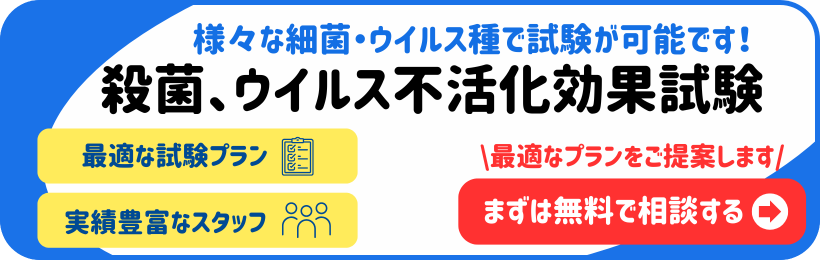【高い致死率!】犬パルボウイルスについて解説
犬の感染症にはさまざまな種類がありますが、その中でも高い感染力と致死率を持つ病気が、犬パルボウイルス感染症です。特に子犬が感染し発症した場合、1~2日で命を落としてしまうこともあるほど、恐ろしい病気です。ここでは犬パルボウイルスの疫学について、感染した場合の症状や感染経路、予防法や治療について解説します。
犬パルボウイルスとそれによる感染症について
Parvoviridae科のParvovirus属に分類されるウイルスの一種で、犬パルボウイルスと呼ばれるウイルスの感染により起こります。このウイルスは、細胞分裂が盛んな腸、胸腺、リンパ組織でよく増殖し、これらを障害します。
犬パルボウイルス感染症は世界各国で流行しており、血清学的、遺伝学的な差により、CPV1とCPV2があります。CPV1は病因としては重要ではありませんが、軽度の下痢を起こすことがあります。CPV2は1978年に、嘔吐や下痢を主徴とした高い致死率を伴う犬の疾病の病因として現れ、短期間のうちに世界的に流行を起こしました。潜伏期間は5~12日で、8~12週齢の子犬の死亡率が高いとされています。
症状
通常は感染後2日で、元気消失、衰弱、嘔吐、下痢、食欲不振がみられるようになり、場合によっては発熱もみられます。感染後約5-7日で免疫ができます。軽度発症の犬は発症後1~2日で自然回復し、中等度発症の犬は病院で補助療法を行って3~5日で回復します。しかし、下痢や嘔吐が持続する場合や脱水が著しい場合、特に子犬は1~2日でショック状態に陥り死亡します。心筋炎型では、3~9週齢の子犬が心不全を起こして死亡します。場合によっては外観上健康であった犬が突然虚脱、呼吸困難になり、30分以内に死亡することもあります。
特徴
このウイルスは強力で、60℃の加熱でも1時間は死滅しません。また、アルコール、逆性石鹸なども無効で、次亜塩素酸ナトリウム(ブリーチ)、ホルマリンなどでようやく死滅します。このため、環境中では数カ月以上生存できるとされており、人間の靴に付着し運ばれる可能性があります。
感染経路
犬の糞便の中に排泄されるウイルスが、口や鼻から別の犬に入り感染します。ただし全世界にこのウイルスが広がったため、多くの犬が免疫を持つようになり、現在では犬が次から次へと感染する激しい発症はあまりみられません。ほとんどの場合は無症状の感染に終わり、まれに子犬が感染して発病します。
予防
不活化ワクチン、生毒、弱毒ワクチンの予防接種があります。パルボウイルスワクチンは犬の7種混合ワクチンの中に組み込まれており、すべての犬に接種することが推奨されています。
生後すぐは母乳からの免疫で守られています。母乳由来の抗体は徐々に消失するため、ワクチン接種は子犬のころに行います。しかし母乳由来の抗体によってワクチンの効果が妨害されることがあるので、ワクチンは2~4週間おきに複数回接種する必要があります。
治療
ウイルス自体を直接殺す治療法は存在しないため、主に対症療法や補助療法が行われます。嘔吐や下痢によって失われた水分および電解質を輸液療法によって補填したり、腸内細菌の異常な増殖を防ぐ目的で、抗生物質を使用したりすることもあります。さらに、ショックに対する処置や、嘔吐・下痢などの症状を抑える対症療法も実施されることがあります。加えて、他の犬から採取した血清を注射する血清療法が用いられる場合もあり、これは栄養分の補給に有効であるだけでなく、免疫力を高める効果も期待されています。
食環研では
食環研では犬パルボウイルスを使用したウイルス不活化試験を実施しております。多種多様な検体に対して対応が可能です。
求める効果やご予算に応じて最適な試験内容をご提案いたします。