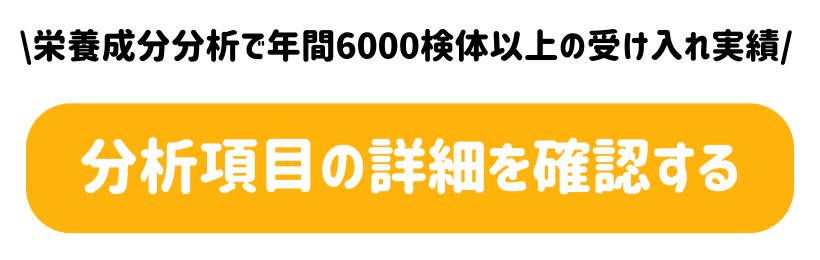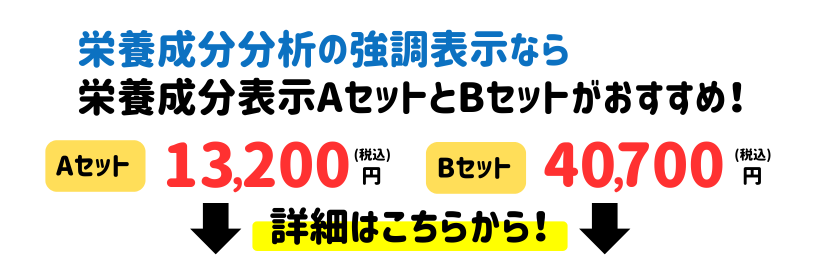栄養強調表示とは?表示の具体例から対象になる栄養素まで検査会社が徹底解説
「高たんぱく」「糖質オフ」「カルシウムたっぷり」などの栄養に関する表示は、すべて栄養強調表示に該当します。
栄養強調表示とは、食品に含まれる栄養成分のうち、その多さや少なさを強調した表示のことです。栄養強調表示は、おおまかに「補給ができる旨の表示」「適切な摂取ができる旨の表示」「添加していない旨の表示」の3つに分類され、それぞれで具体例は下記のように変わります。
| 表示の分類 | 表現の例 |
|---|---|
| 補給ができる旨 | 【絶対表示(基準値以上が条件の表示)】 ・高カルシウム ・カルシウムたっぷり ・ビタミンC豊富 ・たんぱく質多め ・食物繊維入り ・鉄分供給食品 など 【相対表示(他食品と比較した表示)】 |
| 適切な摂取(低減・控えめ)旨 | 【絶対表示(基準値以上が条件の表示)】 ・脂質ゼロ・無脂肪 ・糖類ゼロ ・低脂肪 ・低糖質 ・ナトリウム控えめ ・低カロリー など 【相対表示(他食品と比較した表示)】 |
| 添加していない旨 | 【絶対表示(基準値以上が条件の表示)】 ・糖類無添加・砂糖不使用 ・食塩無添加・食塩不使用・ナトリウム塩不使用 など (「無添加」は一切使用していないことを示す絶対表示であり、比較表現では誤認を招くおそれがあるため認められていません。) |
栄養強調表示をするには、「成分ごとに定められた基準値を越えているか」「相対的に一定以上の差があるか」などの条件を満たしている必要があります。ルールを正しく理解しないまま表示を行うと、消費者を誤認させるだけでなく、食品表示法や景品表示法の違反につながるおそれもあります。
そのため、栄養強調表示をするには、「どの栄養成分が対象になるのか」「どのようなルールがあるのか」などを把握しておくことが大切です。
当記事では、栄養強調表示の概要から表示ルールや具体例、対象になる栄養素などを徹底解説していきます。
目次
栄養強調表示とは?
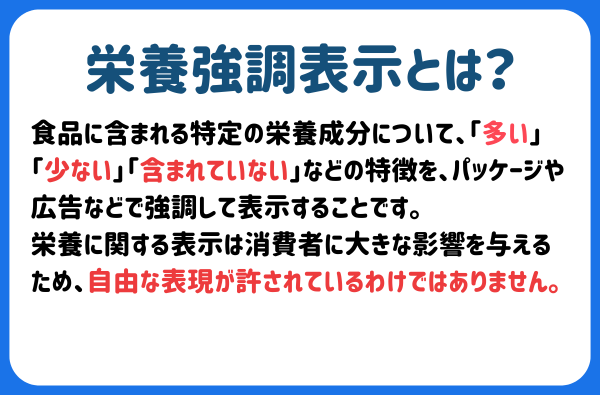
栄養強調表示とは、食品に含まれる特定の栄養成分について、「多い」「少ない」「含まれていない」などの特徴を、パッケージや広告などで強調して表示することです。
たとえば、「カルシウムが豊富」「脂肪ゼロ」「糖質オフ」「ビタミンE配合」のような表現は日常的に店頭やテレビCMなどで目にされますが、これらの表現は栄養強調表示に該当します。
栄養強調表示が重視される背景には、現代の健康志向があります。高血圧や糖尿病などの生活習慣病が社会課題となる中、消費者は栄養成分を意識して食品を選ぶようになりました。
事業者にとっても、栄養強調表示は商品の差別化や訴求力の向上に直結する重要な要素といえます。
しかし、栄養に関する表示は消費者に大きな影響を与えるため、自由な表現が許されているわけではありません。事実と異なる表示や、科学的根拠に乏しい表現は、誤認を招きかねず、消費者の信頼を損ねる原因にもなります。
そのため、栄養強調表示に関して、法律に基づいた明確な基準が設けられています。
日本では、2015年に施行された食品表示法に基づく「食品表示基準」で栄養強調表示に関するルールが定められています。これは、従来の「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の表示関連部分を統合した制度で、消費者にわかりやすく、かつ正確な食品情報を提供するためのものです。
栄養強調表示は、消費者にとっては健康的な食品を選ぶための手がかりであり、事業者にとっては消費者から信頼を得るための手段です。しかし、栄養強調表示には法的な根拠と責任が伴うことを理解し、制度に則って適切に表示することが求められます。
栄養強調表示と栄養成分表示の違い
栄養強調表示と似た言葉に、「栄養成分表示」があります。どちらも食品に含まれる栄養に関する情報を示すものですが、その目的や表示方法、法的な位置づけは大きく異なります。
栄養強調表示と栄養成分表示の違いをまとめましたので参考にしてみてください。
| 項目 | 栄養成分表示 | 栄養強調表示 |
|---|---|---|
| 表示の目的 | 栄養成分の「含有量」を数値で示す | 栄養成分の「特徴(多い・少ない・ゼロ)」を強調する |
| 法的根拠 | 食品表示法・食品表示基準(義務表示) | 食品表示法・食品表示基準(任意表示) |
| 表示の義務 | 加工食品は原則義務 | 任意(行う場合は基準を満たす必要あり) |
| 対象成分 | エネルギー+5成分(+任意項目) | 指定された13成分のみ |
| 表示条件 | すべての加工食品で原則必要 | 表示基準に適合する場合のみ表示可 |
栄養成分表示は、食品にどの栄養素がどれくらい含まれているかを「定量的に示す」ことを目的とした表示です。食品表示法に基づき、原則としてすべての加工食品に表示が義務付けられており、消費者が食品の栄養バランスを把握し、比較検討しやすくするために設けられています。
一方、栄養強調表示は、「脂質ゼロ」「カルシウムが豊富」「糖質30%オフ」といった表現に代表されるように、栄養成分の特徴を強調して伝える任意の表示です。栄養成分表示と違って義務ではありませんが、表示を行う場合は、食品表示基準で定められた成分・基準値・表現方法を厳密に守る必要があります。
また、栄養強調表示を行う場合、その根拠となる栄養成分の量については、必ず栄養成分表示として数値での併記が義務づけられています。つまり、強調表示だけでなく、成分量を正確に表示してはじめて成立するのです。
つまり、簡単に言えば、「栄養成分表示」は成分がどれだけ入っているかを数字で示すもので、一方「栄養強調表示」は多い・少ない・ゼロといった特徴を言葉でアピールするものです。
栄養強調表示の対象となる栄養素
栄養強調表示は、どの栄養素についても自由に行えるわけではありません。食品表示基準により、表示が許可されている栄養素はあらかじめ限定されています。
具体的には、以下の13種類の栄養成分が、栄養強調表示の対象として指定されています。
- エネルギー(熱量)
- たんぱく質
- 脂質
- 飽和脂肪酸
- コレステロール
- 炭水化物
- 糖類
- 食物繊維
- ナトリウム(食塩相当量)
- ビタミン(A、B1、B2、C、D、E)
- カルシウム
- 鉄
- カリウム
※ビタミン・ミネラルは複数あるため、正確には「13類型」とも表現されます。
これらの栄養素について、「○○が多い」「○○を含まない」「○○を強化」などの表示を行うことは可能ですが、それぞれに定められた表示基準値を満たすことが前提です。
たとえば、「カルシウムが多い」と表示するには、100gあたり120mg以上含まれていなければなりません。また、「脂質ゼロ」などの否定的な表示を行う場合にも、完全にゼロである必要はなく、「脂質0.5g未満」のように国が定める微量の上限を下回っていれば表示が可能です。
このように、対象となる栄養素が限定されている理由は、表示内容の客観性と科学的根拠を担保するためです。自由な表現が可能になれば、事業者間で表示の信頼性にばらつきが生じてしまい、消費者が誤解してしまうリスクが高まるためです。
なお、栄養強調表示を行う際は、対象栄養素が含まれているだけでは足りず、その量が国の定める基準を明確に満たしていることを証明する必要があります。そして、表示の根拠として、パッケージ上に栄養成分表示も併記する義務があります。
このような仕組みによって、栄養強調表示は単なる広告表現ではなく、科学的根拠と法的ルールに裏付けられた信頼性の高い情報提供として、消費者の食品選びに役立つ表示制度として位置づけられています。
栄養強調表示の具体例
栄養強調表示は、主に「補給ができる旨の表示」「適切な摂取ができる旨の表示」「添加していない旨の表示」の3つに分類されます。これらは、どういった栄養特性を伝えたいのかが異なるうえ、表示するための条件も違います。
ここからは、代表的な3つの表示形式について、どのような表現が可能で、どのような基準や注意点があるのかを具体例とともに紹介します。
補給ができる旨の表示
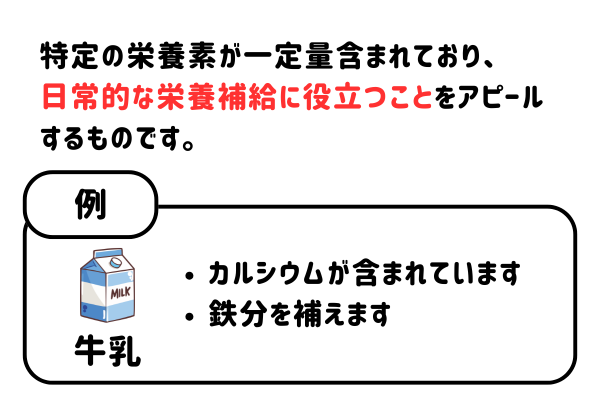
補給ができる旨の表示は、特定の栄養素が一定量含まれており、日常的な栄養補給に役立つことをアピールするものです。「含んでいる」「補える」「配合されている」といった表現が該当します。
補給ができる旨の表示の具体例としては、下記が挙げられます。
- カルシウムが含まれています
- 鉄分を補えます
- ビタミンB1を配合
- たんぱく質を含む食品です
このように表示するには、対象成分が国の基準値を満たしていることが必要です。微量での表示は不可であり、科学的に意味のあるレベルで含まれていることを示す必要があります。
あくまで「量に基づく表示」であり、健康効果を保証する表現はできないのです。
適切な摂取ができる旨の表示
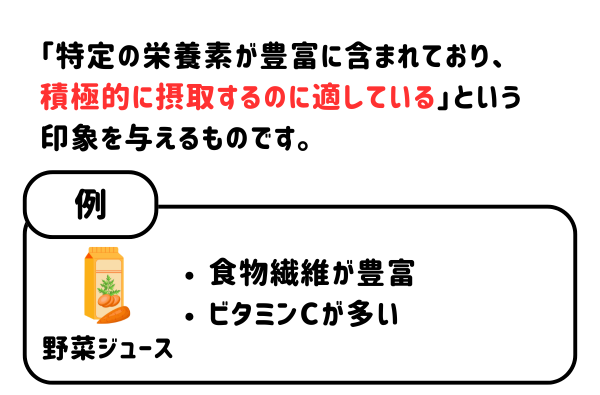
適切な摂取ができる旨の表示は、「特定の栄養素が豊富に含まれており、積極的に摂取するのに適している」という印象を与えるものです。より強調的な言い回しになるため、より高い基準値の充足が求められます。
適切な摂取ができる旨の表示の具体例としては、下記が挙げられます。
- カルシウムたっぷり
- 食物繊維が豊富
- 高たんぱく
- ビタミンCが多い
このように表示するには、「含む」よりもさらに高い含有量を有する必要があります。たとえば「カルシウムが多い」と表示するには、通常100gあたり120mg以上のカルシウムを含む必要があります。
このような強調表示は特に、消費者が健康効果を期待しやすいため、誤認を招かない明確な基準が求められます。加えて、表示内容と実際の含有量が乖離しないよう、商品の設計や分析も適切に行う必要があります。
添加していない旨の表示
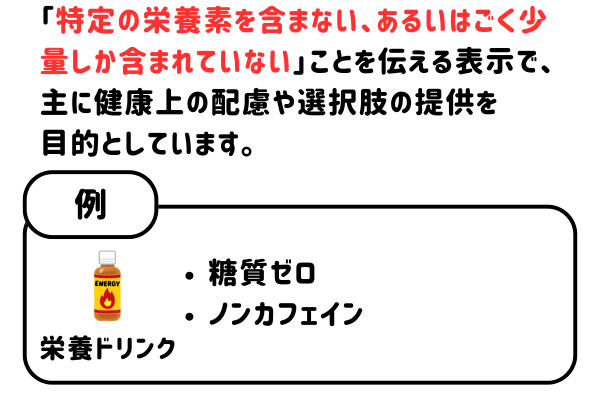
添加していない旨の表示は、「特定の栄養素を含まない、あるいはごく少量しか含まれていない」ことを伝える表示で、主に健康上の配慮や選択肢の提供を目的としています。
添加していない旨の表示の具体例としては、下記が挙げられます。
- 糖質ゼロ
- ノンカフェイン
- 脂肪分を含まない
- ナトリウム無添加
「ゼロ」や「無添加」という言葉が消費者に強い印象を与えることから、このような表示は特に厳密な基準があります。「ゼロ」と言っても本当に完全に含まれていない必要はなく、例えば「脂質ゼロ」の場合は食品100gあたり0.5g未満であれば表示が可能です。
しかし、その上限を超える場合は、「低脂質」などに言い換える必要があります。また、「無添加」表示についても、その成分がもともと食品に含まれていないことや、「添加していない」と断言できるだけの製造工程管理が求められます。
栄養強調表示をする際のルール
栄養強調表示を行う際には、食品表示基準に基づいて、いくつかの重要なルールを遵守する必要があります。表示が消費者の誤解を招かないようにするため、表示できる成分やその量、表示の方法、表示の根拠に至るまで、細かく定められています。
以下では、実際に表示を行う際に必要な4つの重要な観点から、ルールを解説します。
表示を行うために必要な条件と基準値
栄養強調表示は、対象の栄養成分が単に含まれていれば表示できるわけではありません。表示内容に応じて、食品表示基準に基づいた「基準値」を満たすことが求められます。
たとえば、「脂質ゼロ」と表示するには、食品100gあたり脂質が0.5g未満でなければなりません。また「カルシウムが多い」といった強調表現には、100gあたり120mg以上含有することが必要です。
前述したように表示可能な栄養素は13種類に限定されており、それぞれに「多い」「含む」「少ない」「ゼロ」などの表現ごとに基準値が定められています。
「固形か液状か」「100g、100ml、1食分などの表示単位」によって基準が異なるため、商品設計や栄養成分分析の結果と照らし合わせながら表示を設計する必要があります。
栄養成分表示との併記義務
栄養強調表示を行う場合は、その栄養素についての栄養成分表示(数値)をパッケージ上に併記する義務があります。これは、消費者が表示内容の信頼性を確認できるようにすることが目的です。
たとえば、「ビタミンCが豊富」と表示する場合には、「ビタミンC 80mg(100gあたり)」などの情報が記載されていなければなりません。
基本の5成分(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)に加えて、強調表示している成分も、必ず数値で明記する必要があります。表示形式は食品表示基準に準拠し、1食あたり、または100g・100mlあたりで統一されている必要があります。
消費者を誤認させない表現の工夫
栄養強調表示は、消費者にとって健康価値を印象づけるため、表示の文言や見せ方が誤認を与えないようにすることが非常に重要です。
たとえば、下記のような表現は避ける必要があります。
| 効果効能を誤認させる表現 | 「この食品でダイエットに」「骨が強くなる」などは薬機法違反のおそれがある |
|---|---|
| 含有量と乖離した誇張表現 | 「豊富」と表示していても、基準ぎりぎりの数値では過大表現とみなされる場合もある |
| 比較が不明確な表示 | 「30%カット」などは比較対象の明示が必要 |
科学的根拠と実際の含有量に基づいて正確に伝えることで、消費者の信頼を維持することができます。
なお、栄養強調表示のNG例について、詳しくは「栄養強調表示のNG例」の見出しで解説していきます。
表示に関する根拠の保管と責任の所在
表示内容が適正であることを証明するために、その根拠資料を適切に保管する義務があります。具体的には以下のような書類が該当します。
- 成分分析結果(社内/外部機関)
- 栄養成分の推定根拠(文献・成分表)
- 原材料配合比などの設計情報
これらは、販売中および販売終了後も一定期間(目安として2〜3年)保管しておく必要があります。行政からの問い合わせや調査に対応できるよう、整理された形で準備しておくことが望まれます。
栄養強調表示のNG例
栄養強調表示は、商品の魅力を伝えるための有効な手段ですが、消費者の誤認を招いたり、法令違反となったりするリスクも含んでいます。実際、表示内容に関しては消費者庁などによる指導や是正勧告が行われることもあり、事業者にとっては慎重な対応が求められます。
ここでは、栄養強調表示のNG例を挙げながら、それぞれなぜ問題になるのか、どのように回避すべきかを解説します。
科学的根拠のない「効果・効能」を示唆する表現
栄養強調表示はあくまで「栄養素の含有量」に関する表示です。にもかかわらず、健康効果や体調改善を暗示するような表現を用いると、薬機法違反とみなされる可能性があります。
NG例としては下記が挙げられます。
- この食品を食べると疲れが取れる
- 骨が丈夫になる
- 血圧が下がる
これらの表現は医薬品的な効能を暗示しており、表示として認められていません。たとえ栄養素に一定の生理機能があるとしても、明確な科学的根拠と制度的な裏付けがなければ使用できません。
基準値を満たさないのに強調する表現
「多い」「豊富」「たっぷり」などの強調表現を用いるには、対象となる栄養素が定められた基準値以上含まれている必要があります。基準値を満たしていないのに強調表現を使えば、景品表示法の優良誤認に該当するおそれがあります。
NG例としては下記が挙げられます。
- 「カルシウムたっぷり」だが、実際の含有量は100g中50mg程度
- 「ビタミンE豊富」と表示しているが、表示可能な最低量を下回っている
表示の前には必ず、含有量が基準に適合しているかを数値で確認し、根拠資料を保管することが求められます。
相対的な比較表示で根拠が不明確
「○○より△%オフ」「当社従来品比」などの比較を伴う表現は、消費者の誤解を招きやすく、慎重な運用が必要です。比較の対象が曖昧であったり、比較の根拠が明示されていない場合、表示として不適切と判断される可能性があります。
NG例としては下記が挙げられます。
- 「従来品より糖質30%オフ」とあるが、従来品が何か明示されていない
- 「当社比で脂質をカット」とあるが比較対象や算出方法が不明確
比較表示を行う際は、対象品の名称・成分値・比較方法を明記し、第三者から見ても納得できる情報設計にする必要があります。
栄養素として認められていない成分の強調
栄養強調表示として認められているのは、食品表示基準で定められた13の栄養成分に限られています。それ以外の機能性成分については、栄養強調表示の対象外であり、制度上の表示はできません。
NG例としては下記が挙げられます。
- ポリフェノールたっぷり
- カテキン配合で健康維持
これらの表現は、健康食品でよく見られますが、栄養強調表示として用いると制度外表示になります。これらを訴求したい場合は、機能性表示食品など別の制度を検討する必要があります。
消費者が誤解しやすい曖昧な表現
「バランスのよい栄養」「ヘルシー設計」「体にやさしい」などの表現は、一見すると健康的に感じられますが、明確な基準や根拠が存在しないため、表示として適正とは言えません。
NG例としては下記が挙げられます。
- 体にいい食品
- 健康サポート食
- 栄養バランス重視
このような表現は、消費者に好印象を与える反面、具体的な裏付けがない場合、優良誤認とされるリスクがあります。表示には、常に定量的・客観的な情報が求められることを意識しましょう。
栄養強調表示に関するよくある質問
栄養成分の分析をしていない場合でも、栄養強調表示は可能ですか
可能ですが、表示する以上は必ず科学的根拠となる資料を保有する必要があります。自社で成分分析を実施していない場合でも、以下のような方法で根拠を整えることが求められます。
- 民間の検査機関に依頼して分析を行う
- 食品成分表や学術論文などの既存データを使用して推定値を算出する
- 原材料情報や配合設計をもとに含有量を計算し、合理的な説明ができる形で記録を残す
いずれの場合も、表示した内容について後から行政や消費者に説明ができるよう、根拠資料を保存しておくことが不可欠です。根拠が不明確なまま表示すると、法令違反となるリスクがあります。
栄養強調表示が原因で行政から指摘されることはありますか?
はい。消費者庁や都道府県の担当部局による監視・指導の対象となります。
表示内容に問題があると判断された場合は、是正指導や措置命令の対象となる可能性もあるため、事前の確認と根拠資料の保管が重要です。
まとめ
栄養強調表示は、消費者に対して食品の栄養価や健康的な印象を伝える有効な手段です。しかしその一方で、表示内容には厳密なルールが定められており、科学的根拠と法律への理解が欠かせません。
栄養強調表示できる栄養素は限られており、それぞれに基準値が設定されているため、単に「身体によさそう」という印象だけで表示を行うことはできません。
また、栄養強調表示を行うには、その成分の含有量を示す栄養成分表示の併記が義務付けられており、誤解を招く表現や過剰な強調は違反のリスクがあります。特に、健康効果や効能を示唆する表現、基準値に達していない成分の強調、比較の曖昧な表示は要注意です。