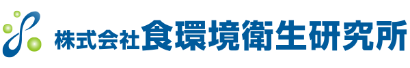食中毒の症状が出るまでの時間や食中毒予防のポイント
食中毒を発症すると、さまざまな症状がみられます。食中毒の症状は発症した原因の細菌やウイルスなどによって異なりますが、主には吐き気・おう吐・腹痛・下痢・発熱がみられます。
そして、食中毒の症状が出るまでの期間は、細菌やウイルスの潜伏期間によって変わります。そのため、「食中毒を発症すると、〇〇という症状が△時間後にみられる」のように断言することはできません。
食中毒の症状について詳しく知りたい場合、細菌やウイルスごとの潜伏期間や症状を調べておくのがよいでしょう。また、細菌やウイルスごとで予防策も変わるため、食中毒を予防するためにもこれらを把握しておくことが重要です。
当記事では、「食中毒の症状とは?」をテーマに、食中毒を引き起こす細菌やウイルスごとの症状や潜伏期間、予防方法などを解説していきます。
※食中毒の症状がみられた際には適切な処置が必要になることもあります。食中毒が疑われる場合にはすぐさま医師に相談するようにしてください。
目次
食中毒の主な症状は吐き気・おう吐・腹痛・下痢・発熱
食中毒は、食中毒を引き起こす細菌やウイルス、有害な物質がついている食べ物を食べることで症状が出る病気です。食中毒による症状はさまざまなものがありますが、食中毒の主な症状としては「吐き気」「おう吐」「腹痛」「下痢」「発熱」が挙げられます。
食中毒の症状は数日〜2週間程度続くとされており、場合によっては命にかかわることもあります。そのため、食中毒の症状が疑われる場合には消化器内科や総合内科といった医療機関を受診することが大切です。
なお、詳しくは後述しますが、食中毒の症状は食中毒を引き起こす原因である細菌やウイルスなどによって異なります。食中毒の症状について詳しく知りたい場合には参考にしてみてください。
食中毒の症状が出るまでの時間は食品に潜む細菌などによって異なる
「食中毒の症状は食べてから何時間後に出るのか」と考えている人もいることでしょう。
結論から述べると、食中毒の症状が出るまでの時間は細菌やウイルスなどによって変わるため、「食べてから○時間後に症状が出る」のように断言することはできません。
前提として、食中毒を引き起こす細菌やウイルスなどがついた食べ物を食べたしたとしても、直後に症状が出るケースは多くありません。基本的には感染してから発症するまでの時間である「潜伏期間」が経過してから、食中毒の症状がみられ始めます。
そして、細菌やウイルスなどによって潜伏期間は異なります。そのため、どのような細菌やウイルスが体に入り込んでしまったかによって、食中毒の症状が出るまでの時間は変わるのです。
なお、インターネットなどでは、「食後3時間程度で食中毒の症状がみられる」といった情報もみられます。確かに潜伏期間が3時間程度の細菌やウイルスもありますが、潜伏期間が1日以上のものもあるため、食後3時間で必ず食中毒の症状が出るとは限りません。
食中毒が疑われる場合、「食べてから3時間経ったけど食中毒の症状が出ないから安心」とは考えず、医師の診察を受けるようにしてみてください。
食中毒が起こる主な原因は細菌・ウイルス・有毒な物質にある
食中毒を引き起こす主な原因は、食べ物についている「細菌」「ウイルス」「有害な物資」にあります。それぞれで食中毒の原因や食中毒が起こりやすい季節などが異なります。
ここからは、食中毒を引き起こす原因について、それぞれ解説していきます。
細菌性食中毒:6月〜8月ごろの夏場に起こりやすい
細菌性食中毒は細菌によって引き起こされる食中毒で、食中毒の原因の大部分を占めます。最近の多くは気温や湿度が高いと活発に増殖をする傾向があるため、6月〜8月ごろの夏場は細菌性食中毒が起こりやすいです。
なお、細菌性食中毒を大きく分けると「感染型」「毒素型」の2種類があります。
| 感染型 | 飲食によって体内に入ってしまった細菌自体が食中毒の原因になるタイプ |
|---|---|
| 毒素型 | 細菌によって産生された毒素が食中毒の原因になるタイプ |
感染型の細菌性食中毒は、体内に入った細菌が腸管内で増殖、または細菌が増殖した食べ物を食べたことで発症します。主な例としては、サルモネラ属菌やカンピロバクターなどが挙げられます。
一方、毒素型の細菌性食中毒は、体内に入った細菌が腸管内で増殖し、それらが産生した毒素が原因となって発症する食中毒です。主な例としては、O15やO111といった腸管出血性大腸菌、セレウス菌などが挙げられます。
ウイルス性食中毒:11月〜3月ごろの冬場に起こりやすい
ウイルス性食中毒はウイルスによって引き起こされる食中毒です。主な例としてはノロウイルスが挙げられ、「令和5年食中毒発生状況」をみると令和5年の食中毒のうち42.3%がノロウイルスであるほど感染力が非常に強いウイルスです。
ウイルス性食中毒の場合、そのウイルスが蓄積した食べ物を食べたり、調理をした人からウイルスが付着した食べ物を食べたりすることで発症します。ウイルスの多くは気温や湿度が低いと感染力を保つため、11月〜3月ごろの冬場にウイルス性食中毒が起こりやすいです。
有害な物質による食中毒:フグや毒キノコ、アニサキスなどが原因で起こる
食中毒の原因は細菌やウイルスだけではありません。有害な物質が原因で食中毒が発症することもあります。
たとえば、フグや毒キノコに含まれる自然毒が挙げられます。また、魚類に寄生するアニサキスによる食中毒も近年増加しており、「令和5年食中毒発生状況」によると平成28年ごろからアニサキスが原因の食中毒が急増していることがわかります。
さらに、大分県の公式サイト「化学物質による食中毒について」では、金属容器を使用して粉末のドリンクを溶かしたことで銅の食中毒が起きた事例が取り上げられています。
自然毒だけでなく、寄生虫や化学物質が原因で食中毒が起こることもあり、有害な物質による食中毒は1年中発生するリスクがあります。
食中毒を起こす細菌やウイルス一覧!食中毒の原因ごとに症状や潜伏期間を紹介
食中毒を引き起こす細菌やウイルスなどには、さまざまな種類があります。食中毒を起こす主な例としては、下記が挙げられます。
| 細菌やウイルス | 原因 |
|---|---|
| サルモネラ属菌 | 主に食肉や卵が原因 |
| 黄色ブドウ球菌 | 切り傷のある指などで触った食品が主な原因 |
| 腸炎ビブリオ | 主に魚や貝などの魚介類が原因 |
| カンピロバクター | 主にとり肉や生野菜が原因 |
| 腸管出血性大腸菌 | 十分に加熱していない肉や生野菜が主な原因 |
| ノロウイルス | カキのような二枚貝が主な原因 |
| セレウス菌 | チャーハンやパスタなどが主な原因 |
| ボツリヌス菌 | 缶詰や瓶詰め、真空パック食品などが主な原因 |
| アニサキス | 魚類が主な原因 |
細菌やウイルスなどによって、食中毒の症状や潜伏期間は異なります。ここからは、食中毒を起こす細菌やウイルスとともに、それぞれの症状や潜伏期間などもあわせて解説していきます。
サルモネラ属菌:主に食肉や卵が原因
サルモネラ属菌は自然界に広く分布しており、主に牛や豚といった動物の腸管にいる細菌です。「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年の食中毒のうち2.4%はサルモネラ属菌が原因であるように、食中毒を引き起こす原因として注意するべき細菌です。
サルモネラ属菌の詳細については、下記のとおりです。
| 特徴 | 乾燥に強く、35度~40度程度の温度帯で活発に増殖する |
|---|---|
| 潜伏期間 | 6時間〜48時間程度 ※72時間程度で発症するケースもある |
| 主な症状 | 激しい腹痛、吐き気、おう吐、下痢など |
| 主な原因 | ・鶏卵、またはその加工品 ・牛・豚・鶏などの食肉 ・うなぎ、すっぽん など |
| 食中毒を予防する対策 | ・加熱に弱い細菌であるため、食材を十分に加熱してから食べる |
サルモネラ属菌の潜伏期間は6時間〜48時間とされており、激しい腹痛、吐き気、おう吐、下痢といった症状がみられます。主には食肉や鶏卵などが原因食品になります。
サルモネラ属菌の特徴として、乾燥には強いですが加熱には弱いとされています。そのため、食材を十分に加熱することがサルモネラ属菌による食中毒を予防する主な対策となります。
黄色ブドウ球菌:切り傷のある指などで触った食品が主な原因
黄色ブドウ球菌(おうしょくぶどうきゅうきん)は、自然界に広く分布しており、牛や豚といった動物だけでなく人間の体にも生息している細菌です。「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年の食中毒のうち2.0%はブドウ球菌が原因であるように、食中毒を引き起こす原因として注意するべき細菌です。
黄色ブドウ球菌の詳細については、下記のとおりです。
| 特徴 | 熱に強く、通常の加熱では毒素が分解されない |
|---|---|
| 潜伏期間 | 30分〜6時間程度 |
| 主な症状 | おう吐、吐き気、下痢など |
| 主な原因 | 切り傷のある指や傷口が化膿した部分からの汚染 |
| 食中毒を予防する対策 | ・手荒れや傷があるときには調理をしない ・手洗いや消毒をしたうえで手袋を着用して調理する |
黄色ブドウ球菌の潜伏期間は比較的短く、30分〜6時間程度とされています。黄色ブドウ球菌が原因の食中毒を発症した場合には、おう吐、吐き気、下痢といった症状が急激にみられます。
黄色ブドウ球菌の特徴として熱や乾燥に強い点が挙げられ、産生された毒素は通常の加熱では分解されません。
そのため、「手洗いや消毒をしたうえで手袋を着用して調理する」などの食材に菌をつけないようにすることが黄色ブドウ球菌による食中毒を予防する主な対策となります。
腸炎ビブリオ:主に魚や貝などの魚介類が原因
腸炎ビブリオは、主に海水中に生息する細菌です。「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年の食中毒のうち腸炎ビブリオは0.2%と比較的少ない数値ではありますが、食中毒を引き起こす原因として無視はできない細菌です。
腸炎ビブリオの詳細については、下記のとおりです。
| 特徴 | 食塩濃度が高い環境下で増殖する。熱や真水に弱い |
|---|---|
| 潜伏期間 | 8時間〜24時間程度 ※48時間で発症するケースもある |
| 主な症状 | 腹痛、下痢、発熱、おう吐など |
| 主な原因 | 寿司や刺身といった加熱をしていない魚介類 |
| 食中毒を予防する対策 | ・生で食べる場合はなるべく低温で保存し、調理前に魚介類を真水で洗う ・火を入れる場合は中心部分まで十分に加熱する ・魚介類の調理で使用した調理器具や手指を十分に洗浄・消毒して、二次汚染を防ぐ |
腸炎ビブリオの潜伏期間は比較的短く、8時間〜24時間程度とされており、食中毒を発症した場合には、腹痛、下痢、発熱、おう吐といった症状がみられます。
腸炎ビブリオの特徴として熱や真水に弱い点が挙げられます。そのため、魚介類を調理する際には「十分に加熱する」「生食の場合はなるべく低温で保存し、調理前に魚介類を真水で洗う」などが腸炎ビブリオによる食中毒を予防する主な対策となります。
カンピロバクター:主にとり肉や生野菜が原因
カンピロバクターは、とくに鶏といった動物の腸内や飲料水、生野菜などにいる細菌です。「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年の食中毒のうち20.7%はカンピロバクターが原因であるように、食中毒を引き起こす原因として特に注意するべき細菌の1つです。
カンピロバクターの詳細については、下記のとおりです。
| 特徴 | 酸素のないところでは増殖できない。乾燥に弱く、通常の加熱調理で死滅する。 |
|---|---|
| 潜伏期間 | 2日〜7日程度 |
| 主な症状 | 発熱、下痢、吐き気、腹痛、頭痛、悪寒、倦怠感など |
| 主な原因 | ・十分に火が通っていない焼鳥 ・十分に洗われていない野菜 ・井戸水や湧き水 |
| 食中毒を予防する対策 | ・十分に加熱する ・食肉を触った際には手を洗う ・食肉を扱った調理器具はほかと分ける ・食肉の調理で使用した調理器具や手指を十分に洗浄・消毒して、二次汚染を防ぐ |
カンピロバクターの潜伏期間は比較的長く、2日〜7日程度とされており、食中毒を発症した場合には、発熱、下痢、吐き気、腹痛、頭痛、悪寒、倦怠感といったさまざまな症状がみられます。
カンピロバクターの特徴として「乾燥に弱く、通常の加熱調理で死滅する」という点が挙げられます。そのため、とくに鶏肉を調理する際には十分に加熱をし、ほかの食材と調理器具をわけるといった対策が食中毒予防となります。
腸管出血性大腸菌:十分に加熱していない肉や生野菜が主な原因
腸管出血性大腸菌は、人や動物の腸管に存在する細菌です。腸管出血性大腸菌として、「O157」「O111」が一般的にも知られています。
「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年の食中毒のうち1.9%は腸管出血性大腸菌が原因であるように、食中毒を引き起こす原因として注意するべき細菌といえます。
腸管出血性大腸菌の詳細については、下記のとおりです。
| 特徴 | 熱や消毒剤に弱い |
|---|---|
| 潜伏期間 | 菌種によって異なるが、1日〜3日程度 |
| 主な症状 | 激しい腹痛、下痢、発熱、血便など |
| 主な原因 | ・肉を生で食べる ・加熱が足りない肉を食べる |
| 食中毒を予防する対策 | ・十分な加熱や消毒をして調理する ・食肉の調理で使用した調理器具や手指を十分に洗浄・消毒して、二次汚染を防ぐ |
腸管出血性大腸菌の菌種にもよりますが、潜伏期間は1日〜3日程度とされています。食中毒が発症した場合には、激しい腹痛、下痢、発熱、血便などの症状がみられます。
腸管出血性大腸菌の特徴として「熱や消毒剤に弱い」という点が挙げられます。そのため、食肉を調理する際には十分な加熱や消毒をすることが腸管出血性大腸菌による食中毒を予防する主な対策となります。
ノロウイルス:カキのような二枚貝が主な原因
ノロウイルスは、食中毒のなかでも毎年患者数が多く、感染力が強いウイルスです。「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年の食中毒のうち16.0%はノロウイルスが原因であるように、食中毒を引き起こす原因として特に注意するべきウイルスです。
ノロウイルスの詳細については、下記のとおりです。
| 特徴 | 少量でも感染するほど感染力が強い。85度〜90度で90秒間以上の加熱で感染力を失うとされている |
|---|---|
| 潜伏期間 | 24時間〜48時間程度 |
| 主な症状 | 吐き気、おう吐、下痢、腹痛、発熱など |
| 主な原因 | ・カキやハマグリといった二枚貝 ・井戸水 ・ノロウイルスに感染した人の糞便や嘔吐物 |
| 食中毒を予防する対策 | ・二枚貝は十分に加熱してから食べる ・排せつ物や吐しゃ物はマスク・手袋をして処理し、十分に消毒をする |
ノロウイルスの潜伏期間は24時間〜48時間程度とされており、食中毒が発症した場合には、吐き気、おう吐、下痢、腹痛、発熱などの症状がみられます。通常であれば3日以内で自然に回復するとされていますが、乳幼児や高齢者といった場合は重症化するおそれもあります。
ノロウイルスの特徴として「熱に弱い」という点が挙げられます。そのため、二枚貝を調理する際には十分な加熱をすることがノロウイルスによる食中毒を予防する主な対策の1つです。
また、ノロウイルスは感染力が非常に強いウイルスであるため、感染者からの二次汚染に対する防止策も必要です。感染者の排せつ物や吐しゃ物を処理する際は、マスク・手袋を必ず着用し、十分に消毒をすることも大切です。
なお、当サイトを運営する株式会社食環境衛生研究所では、「ノロウイルス検査【検便検査】」を行っています。
最短即日で検査結果を報告できるため、「症状が出ていないがノロウイルスに感染しているかを検査したい」「ノロウイルスに感染したが回復している」といった場合は二次汚染を防ぐためにもノロウイルス検査をしておくことも検討してみてください。
セレウス菌:チャーハンやパスタなどが主な原因
セレウス菌は自然界に広く分布している細菌です。チャーハンやピラフ、パスタといった料理が原因食品になりやすく、調理施設だけでなく家庭でもセレウス菌による食中毒は発生するリスクがあります。
「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年の食中毒のうち0.2%と比較的少ない数値ではありますが、家庭でも発症する可能性があることから、セレウス菌は注意するべき細菌の1つです。
セレウス菌の詳細については、下記のとおりです。
| 特徴 | ・28度~35度の温度帯で増殖しやすい ・産生された毒素は通常の加熱でも分解されない |
|---|---|
| 潜伏期間 | おう吐型と下痢型で異なる おう吐型:30分~6時間程度 下痢型:6時間~15時間程度 |
| 主な症状 | おう吐型:おう吐、吐き気など 下痢型:腹痛、下痢など |
| 主な原因 | 土がつきやすい穀類や豆類、香辛料などが主な感染源となる。チャーハンやピラフ、パスタ、焼きそばなど |
| 食中毒を予防する対策 | ・調理した食べ物は常温放置せずに速やかに食べる ・米飯や麺類は作り置きをしない ・保存する場合には、8度以下または55度以上を保つ |
セレウス菌の食中毒にはおう吐型と下痢型があり、それぞれで潜伏期間や症状が変わります。
おう吐型の場合は潜伏期間が30分〜6時間程度で、おう吐、吐き気などが主な症状です。下痢型の場合は6時間〜15時間程度が潜伏期間で、腹痛や下痢といった症状がみられます。
セレウス菌の特徴として「28度〜35度の温度帯で増殖しやすい」「毒素は通常の加熱でも分解されない」といった点が挙げられます。この特徴が家庭でも食中毒を起こしやすい点につながっており、セレウス菌に対する予防策をとることは大切です。
具体的な予防策には、「調理した食べ物は常温放置せずに速やかに食べる」「米飯や麺類は作り置きをしない」「保存する場合には8度以下または55度以上を保つ」などが挙げられます。
ボツリヌス菌:缶詰や瓶詰め、真空パック食品などが主な原因
ボツリヌス菌は、空気のない環境で生育・増殖する「偏性嫌気性菌」という細菌です。そのため、缶詰や瓶詰め、真空パック食品などが原因食品になりやすいです。
ボツリヌス菌の詳細については、下記のとおりです。
| 特徴 | ・空気のないところで生育・増殖し、熱にきわめて強い芽胞を作る ・毒素を無害化するには、80度で30分間の加熱処理が必要 |
|---|---|
| 潜伏期間 | 5時間~3日間程度(通常12時間~24時間) |
| 主な症状 | 吐き気、おう吐、便秘、神経症状など |
| 主な原因 | 缶詰、瓶詰、真空パック食品、レトルト類似食品など |
| 食中毒を予防する対策 | ・材料を十分に洗ってから調理をする ・80度で30分間の加熱処理をしておく |
ボツリヌス菌の潜伏期間は5時間〜3日間程度と幅が広く、通常12時間〜24時間とされています。食中毒を発症した場合には、初期症状として吐き気、おう吐、便秘がみられ、その後は眼瞼下垂、複視、嚥下障害といった神経症状が現れます。
ボツリヌス菌の特徴として「熱にきわめて強い芽胞を作る」という点が挙げられ、毒素を無害化するには、80度で30分間の加熱処理が必要とされています。そのため、調理する際には材料を十分に洗い、80度で30分間の加熱処理をしておくことが大切です。
アニサキス:魚類が主な原因
アニサキスは、サバやアジ、サンマ、カツオ、イカといった魚類に寄生する寄生虫です。2cm〜3cmほどの長さ、0.5mm〜1mmほどの幅で、白色の糸のような見た目をしています。
「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年の食中毒のうち42.3%はアニサキスが原因であるように、食中毒を引き起こす原因として特に注意するべき細菌の1つといえます。
アニサキスの詳細については、下記のとおりです。
| 特徴 | ・目視で確認できる ・魚類の内臓に寄生する ・冷凍と加熱に弱い |
|---|---|
| 潜伏期間 | 1時間~10時間程度(通常は8時間以内) |
| 主な症状 | 激しい腹痛や吐き気、おう吐、じんましんなど |
| 主な原因 | サバ、サンマ、サケ、ニシン、イワシ、ホッケ、タラ、イカなどの魚介類 |
| 食中毒を予防する対策 | ・魚類は十分に加熱する(60度〜70度で1分程度) ・目視で確認できるものはすべて取り除く ・魚類の内臓は生で食べない |
アニサキスの潜伏期間は1時間〜10時間程度とされており、通常は8時間以内で症状がみられます。アニサキスによる食中毒を発症した場合には、激しい腹痛が主な症状で、おう吐、じんましんといった症状も合わせてみられます。
アニサキスの特徴として「冷凍と加熱に弱い」という点が挙げられます。そのため、魚類を調理する際には60度〜70度で1分程度加熱をする、また生で内臓を食べるのは避けるといった対策が食中毒予防となります。
なお、アニサキスの有効な予防策は、加熱や冷凍による死滅、または目視での目視での除去です。ワサビや醤油、酢といった調味料でアニサキスは死滅しないため、加熱や冷凍といった対策を講じるようにしましょう。
食中毒予防のために細菌などを「持ち込まない」「増やさない」「死滅させる」を心がける
前述したように、食中毒はさまざまな食品が原因で起こります。そのため、特定の食材や料理を避けることだけでは十分な食中毒対策にはなりません。
食中毒を予防するためには、細菌やウイルスなどを「持ち込まない」「増やさない」「死滅させる」という3つを心がけることが大切です。
食中毒を引き起こす細菌などを持ち込まなければ食中毒は発症しません。仮に持ち込んでしまったとしても、細菌などを増やさずに死滅させることで食中毒を予防できます。
ここからは、食中毒予防になる「持ち込まない」「増やさない」「死滅させる」の3つの対策について、具体例を紹介しながらそれぞれを解説していきます。
細菌などを持ち込まないためにできること
食中毒予防として、細菌やウイルスなどを持ち込まないことが大切です。実際に、内閣府大臣官房政府広報室が運営する「政府広報オンライン」でも食中毒予防の1つとして細菌などを持ち込まないことを挙げています。
細菌などを持ち込まないためにできることとしては、具体的に下記が挙げられます。
- 食べる時に消費期限や賞味期限が過ぎないものだけを買う
- 他の食材に細菌などがつかないように、肉や魚などは最後に買う
- 他の食材に細菌などがつかないように、肉や魚はビニール袋に入れる
- 帰宅後は必ず手を洗う
家庭において、細菌などを持ち込まないためには食品の買い物時に注意が必要です。とくに肉や魚は食中毒を起こしやすい食品であるため、ビニール袋に入れて買い物の最後に買うようにしましょう。
細菌などを増やさないためにできること
食中毒予防として、細菌などを増やさないことも大切です。細菌などを増やさないためにできることとしては、下記の対策が挙げられます。
- 持ち帰った食品はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れる
- 冷蔵庫は10度以下、冷凍庫は-15度以下に保つ
- 他の食材に細菌などがつかないように、肉や魚はビニール袋や容器に入れて保管する
- 冷蔵庫で保管する食べ物も早めに食べる
食中毒を引き起こす細菌の多くは、温度と湿度が高い環境で活発的に増殖します。そのため、細菌を増やさないために、持ち帰った食べ物はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れるようにしましょう。
冷蔵庫と冷凍庫の温度にも気をつけておくべきであり、目安としては冷蔵庫の場合は10度以下、冷凍庫の場合は-15度以下にしておくと細菌の増殖を抑えられます。
なお、冷蔵庫で保管したとしても、細菌の増殖を完全に止めることはできません。ゆっくりと増殖してしまうため、冷蔵庫で保管する食べ物は早く食べることが食中毒予防となります。
細菌などを死滅させるためにできること
食中毒予防として、細菌などを死滅させることも大切です。細菌などを死滅させるためにできることとしては、下記の対策が挙げられます。
- 調理や食事の前は必ず手洗いをする
- 生野菜は十分に洗う
- 肉や魚は中心部を75度で1分間以上を目安に十分に加熱する
- 包丁やまな板は食材を変えるたびに洗剤で洗う
- 使用した調理器具は洗った後に熱湯をかけて殺菌する
食中毒予防としては、手洗いは有効です。そのため、帰宅した際や調理前、食事前には必ず手を洗うようにしましょう。
また、食中毒の原因食品になりやすい肉や魚を調理する際には、十分な加熱処理が大切です。中心部を75度で1分間以上を目安として、調理するようにしてみてください。
まとめ
食中毒を引き起こす細菌やウイルスなどにはさまざまな種類があり、その原因によって症状は変わります。食中毒の主な症状としては吐き気・おう吐・腹痛・下痢・発熱が挙げられますが、症状が出るまでの期間もその原因によって変わります。
そして、食中毒が疑われる場合、自己判断で薬を服用することは避けてください。薬の服用によって体内の細菌やウイルスが留まってしまい、症状が長期化してしまうリスクもあります。
食中毒の症状が出た際には下痢止めや吐き気止めといった薬を自己判断で服用するのは避けて、必ず医療機関を受診するようにしましょう。
なお、株式会社食環境衛生研究所では、細菌検査やノロウイルス検査を行っています。「症状は出ていないが検査をしたい」「発症から回復に向かっているため検査をしたい」という場合には、当社の食中毒検査を行うことも検討してみてください。