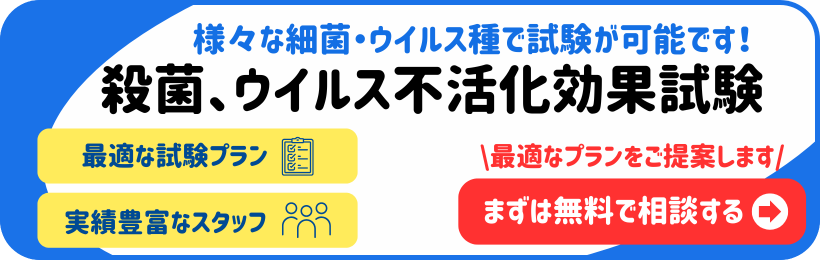ノロウイルスに感染したらどうする?|症状・潜伏期間・家庭でできる対処法まとめ
冬になると毎年のように話題になる「ノロウイルス」。
特に11月から3月にかけて流行し、家庭や学校、職場などでノロウイルスによる食中毒が起こることも珍しくありません。
突然の嘔吐や下痢などの症状に悩まされることが多いノロウイルスですが、正しい知識と対策を知っておくことで感染リスクを減らすことができます。
この記事では、ノロウイルスの症状、潜伏期間、感染経路、家庭でできる対処法、予防法について詳しく解説します。
目次
ノロウイルスとは?
ノロウイルスは、非常に感染力の強いウイルスで、わずか10~100個程度のウイルス粒子で感染するとされています。発症すると急な吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などを引き起こすことがあります。
また、ノロウイルスはアルコール消毒が効きにくく、塩素系消毒剤を使用しなければウイルスを不活化できません。そのため、感染対策をしっかり行わないと家庭内で広がってしまうことがあります。
ノロウイルスの主な症状
ノロウイルスに感染した場合、症状は突然現れることが多いです。特に以下のような症状が代表的です。
突然の吐き気や嘔吐はノロウイルス感染の特徴的な症状です。小さなお子さんでは嘔吐が強く出ることが多く、脱水症状に注意が必要です。
水のような下痢が1日数回から10回以上続くこともあります。腸内環境が乱れるため、体力が低下しやすくなります。
下痢とともに腹痛を伴うことが多いです。特に腸の動きが活発になることで、差し込むような痛みを感じることがあります。
高熱は少ないものの、37℃〜38℃程度の微熱が出ることがあります。特に小児や高齢者では注意が必要です。
強い吐き気や下痢が続くと体力を奪われ、全身がだるく感じることがあります。
ノロウイルスの潜伏期間
ノロウイルスの潜伏期間は約24時間〜48時間とされています。
つまり、感染してから1〜2日後に症状が出ることが多いです。ただし、個人差があるため、感染当日に発症する方もいれば、3日後に症状が出る方もいます。
潜伏期間中でもウイルスを排出している場合があるため、症状が出ていないからといって安心はできません。家族や職場で感染が疑われる場合は、早めに予防策を講じることが大切です。
ノロウイルスの主な感染経路は、「経口感染」「接触感染」「飛沫感染」があります。
ノロウイルスは非常に感染力が強く、以下のような経路で感染します。
経口感染
ウイルスに汚染された食べ物や水を摂取した場合
接触感染
嘔吐物や便の処理時にウイルスが手につき、口や鼻を介して体内に入る場合
飛沫感染
嘔吐物を片付ける際に、ウイルスを含む微粒子を吸い込んで感染する場合
特に家庭内では、嘔吐物やトイレの掃除の際にウイルスが広がりやすいため、正しい消毒方法を知っておくことが重要です。
家庭でできるノロウイルス対策
ノロウイルスに感染した場合や、感染者が家族にいる場合は、家庭内での感染拡大を防ぐことが重要です。
1. 嘔吐物・便の正しい処理方法
嘔吐物や便を処理する際は、使い捨て手袋とマスクを必ず着用します。
処理後は塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)を使って、床や周辺をしっかり消毒しましょう。
2. 手洗いの徹底
石けんと流水による手洗いが最も有効です。特に調理前後、トイレ使用後、嘔吐物処理後は30秒以上かけて丁寧に洗いましょう。
3. 食器や調理器具の消毒
熱湯消毒が効果的です。85℃以上の熱湯で1分以上加熱することでウイルスを死滅させることができます。
4. 洗濯物の対処
嘔吐物や便で汚れた衣類は、塩素系漂白剤で消毒するか、85℃以上の熱湯で洗濯するのが望ましいです。
ノロウイルスの予防法
ノロウイルスの感染を防ぐためには、日常生活で以下の予防策を徹底することが大切です。
調理前後の手洗いを徹底する
受診が必要な場合
軽症であれば自宅で安静にしているだけで回復することが多いですが、以下の場合は医療機関への受診をおすすめします。
早めに受診することで重症化を防げる可能性があります。
まとめ
ノロウイルスは感染力が非常に強く、家庭や学校、職場で集団感染が発生することもあります。
潜伏期間は1〜2日程度で、急な嘔吐や下痢が主な症状です。感染を防ぐためには、手洗い・正しい消毒・食品の加熱が大切です。
家族に感染者が出た場合は、嘔吐物や便の処理を適切に行い、二次感染を防ぎましょう。
また、症状が重い場合は早めに医療機関を受診することをおすすめします。
ノロウイルス キャンペーンを9月22日(月)から開始!
ノロウイルス(遺伝子型GⅤ)を使った試験はこちら