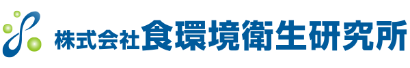放射能分析とは?
「放射能分析」というと、今までは研究機関や医療機関など、特殊な環境でのみ必要な分析分野でした。
しかし、東日本大震災の発生により急速に「放射能分析」の必要性が増し、ハンディタイプの放射能分析装置が売れるなど、今では広く民間に普及した分析分野でもあります。
弊社でも震災後いち早く放射能分析装置を導入し、多くの食品・土壌・水等の放射性物質に対する安全性を分析してきた経歴と実績があります。
今回のコラムでは、実際にどのような方法で放射能分析を行っているのか、その原理と具体的な分析装置の説明をさせていただこうと思います。
放射能って?
最初に大前提として、放射能とはどのようなものなのか、わかりやすく簡潔に説明します。
まず、全ての物質は、細かく、細かく・・・ずっと細かく分割していくと、「原子」という最小単のものになります。この原子の中心には核(原子核)があり、高速で動く粒子(α、β、陽子、中性子、電子)等によって原子が構成されています。
この高速で動く粒子、実は結構なエネルギーを持っていて、特殊な方法(原理?)を用い、高速で動く粒子(エネルギー)だけを取り出すことができるのです。(これを一般には「核反応」と言います)
そのエネルギーを発電に利用したものが、「原子力発電」です。
数々の原子の中でも「放射性物質」といわれるエネルギーを取り出しやすい物質があります。(具体的にはウランやプルトリウムです)
話を戻すと、放射能というのは簡潔に言えば、エネルギーを持つ高速で動く粒子を「放射」する「能」力を指すもので、放射能分析の主な原理は、この高速で動く粒子がどれくらい放射されているのかを分析し、数値化して、相対的な放射性物質の量を測っています。
放射能分析装置の実例
弊社では主に3種類の放射能分析装置で放射能を測っております。
1. 簡易放射能分析装置

原理としては、簡易放射能分析器(いわゆるガイガーカウンター)についてはGM(ガイガー・ミュラー)計数管が使用され、高電圧をかけた不活性ガスが入った筒状の中を放射線が通過すると不活性ガスが電離され、陰極と陽極の間にパルス電流が流れるのでこの通電回数を数えて放射能を分析するというものです。
検体が届いた際に、高濃度放射能汚染物質を分析室に持ち込まないため事前分析として使用しています。
使い方は、スイッチを入れ検体に近づけ、一定時間置くだけです。
2. NaIシンチレーション放射能分析装置

分析装置については放射能の話であった高速で動く粒子のうち、ガンマ線を受けると発光(蛍光)する「シンチレーター」という装置から光電子増幅管等により信号の強さを読み取って、放射能を分析しています。
使い方については、一定量の容器に検体を詰めて一定時間、分析装置にかけます。
その分析用容器に入れた試料の量と分析装置にかけていた時間から、放射能検出器にどれくらいガンマ線が飛んできたかを計算し、放射性物質の量を特定しています。
3. ゲルマニウム半導体検知器付き放射能分析装置

原理的には上記のNaIシンチレーション放射能分析装置と同じですが、こちらの装置の方がより大型で高性能な検出器を装備した放射能分析装置になります。
使い方もNaIシンチレーション放射能分析装置と似ていますが、こちらの方は分析時に低温状態にする必要があるため、機器の下に液体窒素のボトルが装着されています。
精度(より少量の放射能まで正確に分析できるかどうか?)については
簡易放射能分析器 < NaIシンチレーション < ゲルマニウム半導体検知器
といった感じです。
食品にもよりますが、基準値と同程度やそれ以下の残留放射性物質を検出するには、
ゲルマニウム半導体検知器レベルの放射能分析装置による検査が必要であると考えています。
まとめ
放射能分析という狭い分野について、簡易的ではありましたが、説明させていただきました。少しでも理解を深めることができましたでしょうか?
現在食品や土壌には放射性物質の残留基準が制定され、基準値を超える放射性物質が残留する製品については流通が禁じられています。
実際に放射能分析を依頼しようとお考えの方は、弊社までお気軽にご相談下さい。
放射能分析の詳細はこちら