溶連菌の検査方法|検査のタイミング・費用・治療や予防の方法まで解説
目次
溶連菌の検査方法|迅速抗原検査・培養検査・PCRの違いとは?
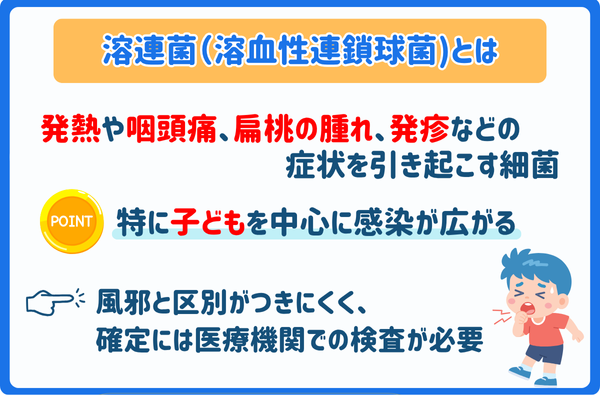
「溶連菌(溶血性連鎖球菌)」は、とくに子どもを中心に感染が広がることが多く、発熱や咽頭痛、扁桃の腫れ、発疹などの症状を引き起こす細菌です。見た目の症状だけではウイルス性の風邪と区別がつきにくいため、確定させるためには医療機関での検査が必要です。
現在、医療現場で行われる溶連菌の検査方法としては主に下記が挙げられます。
- 迅速抗原検査
- 咽頭培養検査
- PCR検査
これらの検査方法では、特徴や検査精度、判定にかかる時間などが異なります。ここからは、これら3つの検査方法について詳しく解説していきます。
迅速抗原検査
迅速抗原検査は、短時間で結果が出ることから、一般的に行われている溶連菌の検査方法です。綿棒を使って咽頭から粘液を採取し、抗原を検出することで、溶連菌の感染の有無を判断します。
迅速抗原検査について概要をまとめましたので参考にしてみてください。
| 概要 | 咽頭の奥を綿棒でこすって粘液を採取し、溶連菌の抗原検出する簡易検査です。全国の小児科や内科で広く実施されています。 |
|---|---|
| メリット | ・5分~15分程度で結果がわかる ・その場で診断・治療の判断が可能 ・外来で手軽に実施できる |
| デメリット | ・偽陰性の可能性がある ・陰性でも医師の判断で追加検査が行われることがある |
通常、検査結果は5分〜15分程度で判明し、その場で医師の診断と治療方針が決まるため、迅速な対応が可能です。とくに小児科では、症状の早期改善や家庭内感染の防止の観点からも、この迅速検査が利用されています。
ただし、迅速抗原検査の精度は100%ではなく約70%~90%とされており、検査のタイミングや採取部位によっては偽陰性が出てしまう可能性もあります。迅速抗原検査はあくまで簡便かつ速やかな診断ツールであるため、必要に応じて他の検査方法との併用も推奨されています。
培養検査
「培養検査(咽頭培養)」は、採取した咽頭粘液を培地に塗布して、細菌を増殖させてから同定する検査方法です。迅速検査に比べて精度が高く、偽陰性が疑われるケースや、感染拡大のリスクが高い施設内感染の調査などで用いられます。
培養検査について概要をまとめましたので参考にしてみてください。
| 概要 | 咽頭粘液を採取し、専用の培地で溶連菌を培養・増殖させて同定する検査です。溶連菌そのものを目視確認するため、感度・特異度ともに高く、確定診断に使われます。 |
|---|---|
| メリット | ・診断精度が非常に高い ・偽陰性・偽陽性のリスクが少ない ・感染拡大の追跡調査にも有効 |
| デメリット | ・結果が出るまでに2〜3日かかる |
この検査のメリットとして、感度・特異度の高さが挙げられます。培養によって菌そのものを確認するため、誤診のリスクがほとんどなく、医師にとっても確定診断の根拠になります。
ただし、結果が出るまでには通常48〜72時間程度かかるため、初期診断には不向きとされています。そのため、まず迅速抗原検査を行い、陰性でも溶連菌感染が強く疑われる場合に補完的に培養検査を行うという使い方が一般的です。
PCR検査
PCR検査は、遺伝子の一部を増幅して病原体の存在を検出する、高感度かつ高精度な検査方法です。新型コロナウイルスの検査でも一躍注目されましたが、溶連菌に対してもPCRによる検出は可能です。
培養検査について概要をまとめましたので参考にしてみてください。
| 概要 | PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査は、菌の遺伝子を増幅して検出する方法で、微量な溶連菌でも高精度に見つけられるのが特徴です。新型コロナウイルスで知られるようになった技術でもあります。 |
|---|---|
| メリット | ・非常に高い精度・感度 ・少量の菌でも検出可能 ・他の疾患との鑑別にも活用できる |
| デメリット | ・専門設備が必要で、実施できる医療機関が限られる ・保険適用外となるケースが多く、費用が高額 ・結果判定まで数時間〜1日ほど時間がかかる |
溶連菌感染は一般的に迅速検査や培養検査で十分な精度が得られることから、PCR検査が行われるケースは限られています。たとえば、他の疾患との鑑別が難しい場合や、免疫不全患者における慎重な診断が必要な場合など、医療的な高度判断が求められるケースで使用される傾向があります。
また、PCR検査は保険適用の対象外となることも多く、自費診療扱いになる可能性が高い点にも注意が必要です。検査費用は医療機関によって異なりますが、数千円〜1万円程度になることがあります。
溶連菌の検査を受けるべきタイミング
溶連菌感染症は、とくに「A群β溶血性連鎖球菌(Group A Streptococcus:GAS)」によって引き起こされる咽頭炎が代表的で、子どもを中心に幅広い年代で見られます。
感染初期には発熱やのどの痛みといった症状が現れますが、ウイルス性の風邪と似た症状が多く、外見だけで区別することが難しいです。そのため、以下のような症状が見られた場合には、医療機関での検査を検討することが大切です。
- 突然の高熱(38度以上)
- 飲み込み時に強い咽頭痛や嚥下痛がある
- 扁桃に白い膿が付着している
- 赤くざらざらとした発疹がみられる
- 舌に赤みとブツブツがある(いちご舌)
- 頸部リンパ節の腫れや圧痛
とくに小児では、熱が出ていても咳や鼻水が少ない場合は、ウイルス性よりも溶連菌が原因である可能性が高くなります。
なお、溶連菌感染症は風邪と誤解されることもありますが、自然治癒に任せることにはリスクがあります。溶連菌に感染した場合、「急性腎炎」「リウマチ熱」「中耳炎」といった合併症を引き起こすおそれもあります。
そのため、溶連菌感染の症状が該当する場合は早めの検査をおすすめします。
溶連菌の検査を受けられる場所
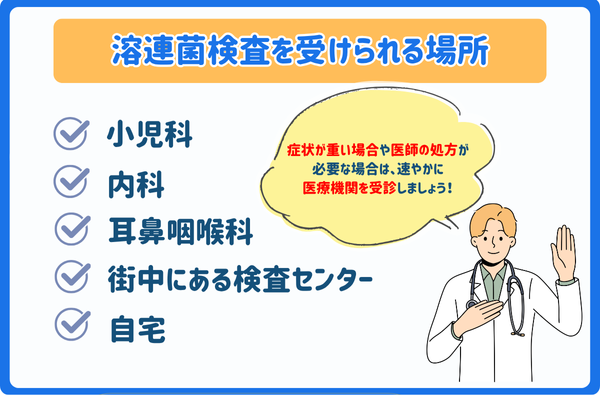
溶連菌の検査は、日常的に医療現場で実施されている一般的な検査の1つです。とはいえ、どの医療機関でも必ず検査ができるわけではないため、症状が出たときに「どこを受診すればよいのか」を知っておくことはとても大切です。
そこで、ここからは溶連菌検査を受けられる主な医療機関の種類と、それぞれの特徴について解説していきます。
小児科
小児で最も多くみられるのが、A群溶血性連鎖球菌による咽頭炎です。そのため、子どもに発熱やのどの痛みなどの症状が見られた場合には、まず小児科を受診するのが一般的です。
小児科では、迅速抗原検査が常備されていることが多く、医師が診察の中で必要と判断すればその場で検査を受けることができます。
とくに以下のようなケースは、受診を急ぐべきといえます。
- 38度以上の高熱が続いている
- 飲み物を飲むのを嫌がる、食欲がない
- 学校や保育園で溶連菌が流行している
内科
溶連菌は子どもに多い病気と思われがちですが、成人にも感染します。とくに家庭内や職場内で感染が広がっている場合、免疫が落ちているタイミングで感染する可能性があります。
そのため、大人であっても喉の痛みや発熱がある場合には、内科や総合診療科での受診が適しています。小児に比べて発疹などの症状は出にくい傾向にありますが、倦怠感や咽頭痛が続く場合には検査が推奨されます。
耳鼻咽喉科
のどの腫れや違和感、扁桃の腫大・白苔が強い場合は、耳鼻咽喉科を受診するのも有効な選択肢です。耳鼻科では咽頭の視診がより専門的に行えるほか、扁桃腺周囲膿瘍など他の合併症を伴っていないかどうかの評価も受けられます。
また、慢性扁桃炎や咽頭痛を繰り返す人にとっては、定期的に耳鼻科を受診することが適しているケースもあります。
一般の検査機関・検査サービス提供事業者
近年では、医療機関に限らず、民間の検査サービス提供事業者によって、検査キットの配送や店舗での検査提供を行っているケースも増えてきました。このような事業者では、以下のようなサービスが提供されています。
- 自宅に届く郵送検査キット
- 街中にある検査センターなどでの対面検査
- 結果のWeb通知や、医師とのオンライン相談の付帯サービス
ただし、溶連菌の迅速抗原検査や培養検査では、咽頭からの適切なぬぐい液の採取が非常に重要となるため、自己採取の精度や安全性、診療との連携体制の有無を確認することが重要です。
また、症状が重い場合や医師の処方が必要な場合には、速やかに医療機関の受診が推奨されます。
溶連菌の検査にかかる費用の目安
溶連菌の検査を受けるにあたって、「どれくらい費用がかかるのか」「保険は使えるのか」といった疑問を抱くこともあるでしょう。
溶連菌の検査費用は、基本的に「診察料」「処方箋料・薬剤費」がかかります。これらの費用には医療保険が適用されることが一般的であり、保険証を提示すれば自己負担は1割〜3割となります。
あくまで目安にすぎませんが、医療保険が適用された場合の溶連菌の検査費用をまとめましたので参考にしてみてください。
| 検査項目 | 自己負担の目安 |
|---|---|
| 初診料 | 約900円〜1,200円 |
| 迅速抗原検査 | 約300円〜600円 |
| 培養検査(咽頭培養) | 約500円〜900円 |
| 処方箋・薬代 | 約500円〜1,000円程度 |
なお、通常の外来診療で医師の判断によって検査を受ける場合は、健康保険が適用されますが、以下のような場合には保険適用外となる可能性があります。
- 医療機関を介さずに検査キットのみの購入
- 学校・会社提出用の陰性証明書発行を目的とした検査
- オンライン診療等で医師の診察を経ずに検査を依頼する場合
これらのケースでは、検査料が数千円〜1万円前後になることもあります。検査サービス提供事業者を利用する場合は、事前に費用や内容をしっかり確認しておくことが重要です。
溶連菌の治療方法
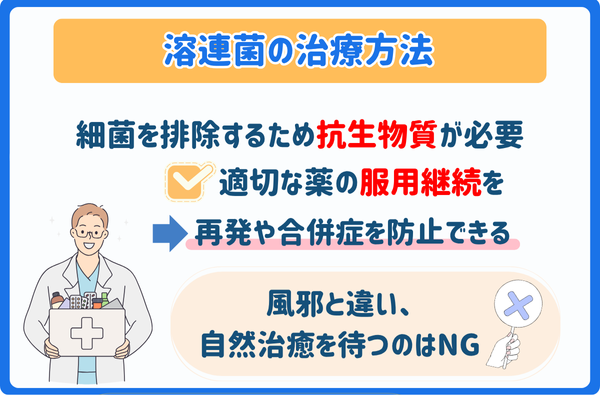
溶連菌感染症の治療には、細菌を排除するための抗菌薬であるいわゆる抗生物質が必要です。風邪と違って自然治癒を待つだけでは不十分で、適切な薬を処方してもらい、医師の指示どおりに服用を続けることが重要です。
薬を飲み始めて1日~2日で熱が下がったりのどの痛みが軽くなったりすることが多いですが、症状が治まったからといって自己判断で服用を中断するのは避けるべきです。
抗菌薬は最後まで飲み切ることで、再発や合併症を防ぐことができます。とくに、溶連菌感染後に起こりうる急性腎炎やリウマチ熱といった合併症を予防するうえでも、きちんとした治療が欠かせません。
また、治療開始から24時間程度が経過し、症状が落ち着いていれば、登園・登校などの再開が可能とされています。ただし、判断は医師の指示に従うのが原則です。家族内で感染を広げないためにも、指示された治療をきちんと受け、無理のない回復を目指しましょう。
溶連菌の予防方法
溶連菌感染症は、主にせきやくしゃみなどの飛まつを通じて人から人へとうつる病気です。とくに子ども同士の集団生活や家庭内での感染が多く、完全に防ぐことは難しいものの、日ごろのちょっとした工夫で感染のリスクを下げることができます。
まず重要なのは、こまめな手洗いとうがいです。外出先から戻ったときや食事前、トイレのあとなど、手を清潔に保つ習慣は感染症全般の予防につながります。
また、家族に感染者がいる場合はタオルやコップ、食器を共有しないことも大切です。症状が出ていない人でも、潜伏期間中に菌を広げてしまうおそれがあります。
室内では定期的な換気を心がけ、必要に応じてマスクを着用しましょう。とくにのどの痛みや発熱がある人が近くにいる場合には、飛まつ感染を防ぐための対策が効果的です。
さらに、日ごろから十分な睡眠と栄養をとることで、体の免疫力を高めておくことも忘れてはいけません。疲れがたまっていたり、体調を崩しやすい時期には、普段以上に感染しやすくなるため注意が必要です。
もし家族の中に溶連菌にかかった人がいる場合は、ほかの家族も早めに症状が出ていないかをチェックし、必要があれば医療機関で相談・検査を受けるようにしましょう。早期に対応することで、重症化や広がりを防ぐことができます。
まとめ

溶連菌感染症は、発熱やのどの痛みなど風邪に似た症状で始まることが多いため、見逃されがちな病気です。
しかし、正しく検査を受け、早期に治療を始めることで重症化や合併症を防ぐことができます。とくに子どもがかかりやすく、家庭内や学校などで広がることも少なくありません。
検査には迅速抗原検査、培養検査、PCR検査など複数の方法があり、それぞれに特徴があります。症状や状況に応じて、医師や検査機関が適切な方法を選んでくれます。また、検査を受けるべきタイミングや場所を正しく理解しておくことも重要です。
治療には抗菌薬が用いられ、医師の指示どおりに飲みきることが、再発や合併症を防ぐポイントになります。さらに、手洗い・うがいの徹底、十分な休養、家族内での感染対策など、日ごろの予防行動も欠かせません。
のどの痛みや高熱など、少しでも気になる症状があれば、無理をせずに早めに医療機関や信頼できる検査機関を受診しましょう。
畜産の溶連菌(レンサ球菌)検査はこちら
食環境衛生研究所では、畜産における溶連菌(レンサ球菌)検査をおこなっております。
検査をご検討のお客様はお気軽にご相談ください。
溶連菌(レンサ球菌)検査
