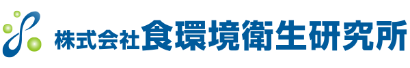芽胞形成菌と食中毒の関係について
食中毒は夏の時期に発生が多いというイメージを持っている方もいるかもしれませんが、涼しくなってきた秋の時期でも注意する必要があります。
今回は、食中毒を引き起こす原因菌の1つである「芽胞形成菌」についてお話ししたいと思います。
芽胞とは
一部の細菌が形成する細胞構造のことで、芽胞殻、皮層、芯部で構成されています。芽胞は熱、低温、乾燥、紫外線、化学薬品等に対して極めて高い抵抗性を示すため、多くの食中毒菌に有効である煮沸やアルコール消毒などでは不活化することができません。
厳しい環境条件下では芽胞を形成することにより休眠状態を維持します。そして、環境が細菌の生存に適した条件になると発芽し、再び増殖を始めます。
芽胞形成菌の分類
芽胞を形成できる細菌は限られており、バチルス属とクロストリジウム属の2つに大別されます。どちらも土壌や水などの環境中に広く分布し、芽胞を形成するという点では似ていますが、発育に必要な条件が異なります。
バチルス属
好気性あるいは通性嫌気性のグラム陽性桿菌です。好気性の場合は酸素がある環境で発育し、酸素がない環境では発育ができません。通性嫌気性の場合は、酸素の有無に関わらず発育することができます。主な食中毒菌として、セレウス菌が挙げられます。
クロストリジウム属
嫌気性のグラム陽性桿菌です。酸素がない環境で発育し、酸素がある環境では発育ができません。主な食中毒菌として、ウェルシュ菌、ボツリヌス菌が挙げられます。
原因食品
芽胞形成菌による食中毒は、以下の食品が原因となることが多いです。
| 原因菌 | 原因食品 |
|---|---|
| セレウス菌 | 焼飯、パスタ、乳製品、肉類、野菜、スープ |
| ウェルシュ菌 | カレーやシチューなどの食肉調理食品 |
| ボツリヌス菌 | 発酵食品、びん詰、缶詰、真空包装食品 |
芽胞形成菌による食中毒を防ぐには
食中毒の予防には「つけない・増やさない・やっつける」の3原則が重要です。びん詰や缶詰などの加工食品については、加工時に芽胞を完全に死滅できる温度・時間で過熱するか、加工から流通段階においてできる限り低温を維持する必要があります。家庭では通常の調理温度で芽胞を死滅させることが難しいため、芽胞の発芽とその後の菌の増殖を防ぐことが重要です。調理後は室温で長時間放置せず、すぐに喫食するか、速やかに冷蔵・冷凍保存するようにしましょう。