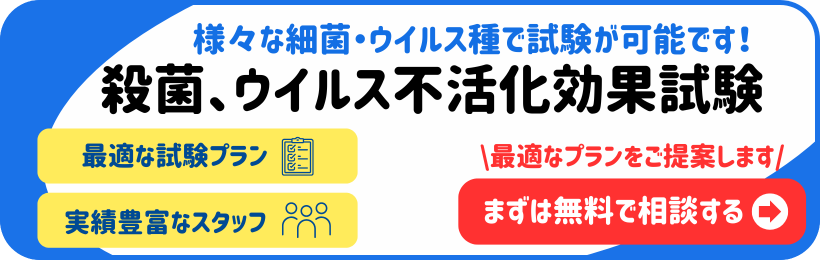ノロウイルスは二枚貝で感染する?牡蠣・ホタテのリスクと安全対策
目次
ノロウイルスは二枚貝で感染する?感染経路と安全対策
冬場を中心に流行するノロウイルス感染症は、食中毒の原因としても非常に多いウイルスです。特に、鍋料理でよく使われる牡蠣・ホタテ・アサリなどの二枚貝は、ノロウイルスによる食中毒のリスクが高い食品として知られています。
過去の食中毒統計を調べてみると、生牡蠣だけでなく、焼き牡蠣、ボイルアサリなどが原因として特定されている事例もあります。
この記事では、ノロウイルスと二枚貝の関係、感染経路、予防対策について詳しく解説します。
ノロウイルス感染の主な原因は二枚貝
ロウイルスによる食中毒は、主に牡蠣などの二枚貝を食べることが原因で発生します。
牡蠣・ホタテ・ムール貝・アサリ・シジミ・バカガイなどの二枚貝は、海水を大量に取り込む性質があり、その過程で海水中のノロウイルスを体内に蓄積します。
特に、以下のような食品で感染事例が報告されています。
二枚貝に含まれるウイルスは調理法によっては死滅しないことがあり、十分な加熱が行われないと感染リスクが高まります。
「生食用牡蠣」と「加熱用牡蠣」は牡蠣が採れた海域で決まる
ノロウイルス感染に繋がる最も有名な二枚貝「牡蠣」には生食用と加熱用がありますが、どちらになるかは牡蠣が採れた海域によって決まります。
加熱用の牡蠣は、河口付近で育てられるため、山や川から流れてくる豊富な栄養素やプランクトンを含んだ水により、濃い味の牡蠣になると言われています。
しかし、河口付近で育てられた牡蠣は、プランクトンなどと一緒に生活用排水に含まれる病原性細菌やウイルスなどで汚染される可能性が高くなります。
一方、生食用の牡蠣は、定期的な水質検査において国が定める大腸菌や腸炎ビブリオなど細菌数の基準をクリアした海域で採られるため、生食として食べることができます。
ノロウイルスの感染経路~ヒトとノロウイルス~

1. ヒトから環境へのウイルス排出
ノロウイルスに感染した人は、症状が出ていなくてもウイルスを排出することがあります。
便1gあたり10億個以上のウイルスを含む場合もあり、感染者の嘔吐物や便を通じて大量のウイルスが環境中へ放出されます。
このウイルスはトイレを経由して下水へと流れ込みます。
2. 下水処理場での除去と限界
下水処理場では、沈殿・ろ過・消毒といった工程でウイルスの除去を行いますが、
ノロウイルスは耐性が高いため完全除去は困難です。
一般的に下水処理で除去できる割合は約80〜90%とされており、残ったウイルスは処理水とともに河川や海へ放出されます。
3. 河川・海へのウイルス流出
下水処理をすり抜けたノロウイルスは河川を経由して海へ流れ込みます。
特に河口付近は生活排水や下水が集まりやすく、ウイルス濃度が高くなる傾向があります。
さらにノロウイルスは低温環境で長期間生存できるため、冬場は特に海水中のウイルス量が増加します。
4. 二枚貝へのウイルス蓄積
牡蠣・ホタテ・アサリなどの二枚貝は、濾過摂食(ろかせっしょく)という方法で海水中のプランクトンを取り込みます。このとき、海水中に含まれるノロウイルスも一緒に取り込まれ、二枚貝の中腸腺(消化器官)に蓄積されます。
二枚貝自体はノロウイルスに感染しませんが、濃縮された状態で保持するため、人が加熱不十分な状態で食べると感染リスクが高まります。
5. 二枚貝を介した再感染
ウイルスを蓄積した二枚貝を十分に加熱せずに食べた場合、ノロウイルスに感染する可能性があります。
また、生の二枚貝を扱う調理工程で、まな板・包丁・食器・調理者の手指が汚染され、他の食品を介して感染が広がるケースもあります。
このように、二枚貝はノロウイルス感染の重要な媒介となっています。
6. 冬場に感染が多い理由
ノロウイルスは低温環境で長期間生存する特徴を持つため、冬場は特に感染リスクが高まります。
夏場は高温や紫外線の影響でウイルスが減少する傾向がありますが、冬場は海水中のウイルスが長く残存し、二枚貝に蓄積されやすくなるのです。
そのため、牡蠣をはじめとした二枚貝を食べる際は、冬場ほど注意が必要です。
ノロウイルス感染を防ぐための加熱と消毒方法
ノロウイルスは非常に熱に強いウイルスであり、通常の調理では死滅しないことがあります。
安全に食べるためには、以下のポイントを徹底しましょう。
食品の加熱目安
調理器具・手指の消毒
ノロウイルス検査の重要性
ノロウイルスは感染力が非常に強く、症状がなくてもウイルスを排出している可能性があります。 感染源を早期に特定するために、食品関連従事者や飲食店ではノロウイルス検査の実施が推奨されています。
ノロウイルス検査はこちら
検便検査で感染拡大を防ぐ
特に飲食店や食品工場などでは、従業員の定期的な検便検査が有効です。
感染者を早期に発見し、二次感染や食中毒の拡大を防ぐことができます。
食中毒事例一覧(厚生労働省)
過去の食中毒統計を見ても、二枚貝が原因となるノロウイルス感染事例は多数報告されています。
詳しくは厚生労働省の「食中毒統計資料」で確認できます。
まとめ
冬場は特にノロウイルス食中毒が増加しますので、正しい知識と対策で安全に二枚貝を楽しみましょう。
ノロウイルス検査のご依頼はこちらから!

ノロウイルス(遺伝子型GⅤ)を使った試験はこちら