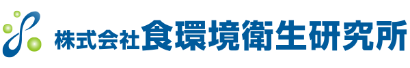飲食店の検便検査は義務?検便の頻度や必要な検査を解説
「飲食店の開業を検討している」「すでに飲食店を経営している」といった場合、店舗にて検便検査を実施するべきかを考えている人もいることでしょう。
飲食店の信頼性や安全性を高めるためにも、衛生管理は徹底することが大切です。安全や安心を確保するためにもさまざまな施策を講じる必要がありますが、その一つとして検便検査の実施が挙げられます。
飲食店において原則的には検便検査の実施が義務付けられているわけではありません。あくまで店舗での判断によって検便検査が行われていますが、多くの飲食店で検査が実施されています。
検便検査を定期的に実施しておくことで、食中毒事故が発生するリスクを抑えられるうえに、万が一事故が起きた場合にも従業員や店舗を守るための証拠にもなるためです。そのため、飲食店においては検便検査を行なっておくのが望ましいです。
とはいえ、はじめて飲食店で検便検査を実施する場合、「どんな検査をするべきか」「誰を対象に検査するのか」「どこに依頼するべきか」といった疑問があることでしょう。
そこで、当記事では、飲食店の検便検査についての対象や頻度、依頼先も解説していきます。飲食店での検便検査の実施を検討している場合にはぜひ参考にしてみてください。
目次
低価格で高品質な検査を短納期でお届け

※1検体 検便3項目セット(赤痢・サルモネラ・O157)770円(税込)~
※至急対応可能 最短で2営業日で実施
※団体割引可能 お見積りが必要なお客様はお気軽にお問い合わせください
また、どのような検査項目にすればいいのか分からないなどがございましたらお気軽にまずはご相談ください!
ご丁寧にご説明をさせていただきます!
飲食店において検便は義務化されていないが食中毒の拡大リスクを抑えるためにも実施するべき
飲食店において、検便検査の実施は法律で明確に義務付けられていません。
しかし、多くの飲食店では定期的に従業員に対して検便検査を行っています。これは、食中毒やウイルスによる感染症の拡大を防ぐ目的として行われています。
そもそも検便検査は、細菌やウイルスなどに感染していないかを調べるために行われます。
飲食店の従業員は調理や提供を行うため、飲食物に触れる機会が多いです。細菌やウイルスに感染している従業員が飲食物の調理や提供をすると、その飲食物を通して食中毒やウイルス感染症を拡大させてしまうリスクがあります。
感染症の予防や万が一が起きた場合の証拠のためにも検便検査の実施は有効であるため、義務はなくとも多くの飲食店では自主的に検便検査を定期的に行っているのです。
なお、食品衛生法施行規則では、下記のように定められています。
食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理
イ食品又は添加物を取り扱う者(以下「食品等取扱者」という。)の健康診断は、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な健康状態の把握を目的として行うこと。ロ都道府県知事等から食品等取扱者について検便を受けるべき旨の指示があつたときには、食品等取扱者に検便を受けるよう指示すること。
引用元 e-Gov「食品衛生法施行規則」
食品衛生法施行規則で定められているように、自治体から指示があった場合には検便を実施しなければなりません。その場合は例外として検便検査の義務が生じるため、自治体からの指示にしたがって検査を実施するようにしてください。
飲食店における検便検査の必要性
前述したように、飲食店において検便検査は、感染症の予防や万が一が起きた場合の証拠を目的として実施されます。そして、検便検査を実施することで、具体的には下記を明確にすることができます。
- 食中毒菌に感染していても症状がない「健康保菌者」がいないかを確認できる
- 万が一食中毒が発生してしまったときに原因を追跡できる
これらを明確にできるため、定期的な検便検査の実施は飲食店において非常に非常に重要です。ここからは、飲食店における検便検査の必要性について、それぞれ解説していきます。
食中毒菌に感染していても症状がない「健康保菌者」がいないかを確認できる
健康保菌者とは、食中毒菌やウイルスなどに感染していても、まったく症状が出ていない人のことを指します。症状がないことから、健康保菌者本人には食中毒菌などに感染している自覚がないことが多いです。
しかし、自覚や症状がないとはいえ食中毒菌やウイルスに感染していることは変わりありません。そのため、健康保菌者が調理や提供などを行なってしまうと、食材や料理に菌を付着させてしまい、食中毒が発生するリスクがあるのです。
検便検査では便から食中毒菌などを調べられるため、健康保菌者がいないかどうかも確認できます。つまり、定期的に検便検査を実施することで、無自覚・無症状によって気づきようがなかった感染者による食中毒感染を予防することができるのです。
この点からも飲食店においては、義務がなくても検便検査を定期的に実施するべきといえるでしょう。
万が一食中毒が発生してしまったときに原因を追跡できる
飲食店にて万が一食中毒事故が起きてしまった場合、その原因を特定するために保健所による調査が行われます。
保健所による調査が行われた場合、食材や調理器具、調理工程、厨房などの環境といったものだけでなく、飲食店の従業員も調査されます。そのため、飲食店の従業員に対して保健所から出勤停止が命じられることもあり、働きたくても働けない状況をつくってしまう可能性もあるのです。
検便検査を実施しておくことで、万が一食中毒事故が起きてしまった場合でも従業員が原因ではないことを検査結果で示すことができます。そのため、飲食店においての定期的な検便検査の実施は、店舗や従業員を守るための手段ともいえるのです。
また、検便検査の結果は食中毒事故が起きたときの証拠になりますが、その証拠を提示できなかった場合、店舗だけでなくその企業や団体も責任が問われることになります。
店舗だけでなくその企業や団体の責任になるリスクを抑えるためにも、飲食店では義務がなくても検便検査を定期的に実施しておくべきです。
飲食店ではアルバイトも含めて食材や料理にかかわる全員を検便検査の対象にするのが一般的
飲食店における検便検査の実施の必要性について解説しましたが、「検便検査を実施するとしても誰を対象にすればいいのか」と考える人もいるかもしれません。
結論から述べれば、飲食店では食材や料理にかかわる従業員全員を検便検査の対象にするのが一般的です。飲食店における食中毒事故は、感染者が食材や料理に触れることで細菌やウイルスを付着させてしまうことが原因で発生するリスクがあります。
そのため、調理担当者は当然のこと、配膳担当者も食中毒事故の原因になる可能性があります。また、勤務の時間や日数が少ない従業員であっても健康保菌者である可能性は考えられます。
飲食店で検便検査を実施する場合、正社員だけでなくアルバイトを含めて、食材や料理に接する従業員全員を対象にするのがよいでしょう。
飲食店での検便検査の頻度は自治体の指示をもとに定期的に実施するべき
前述したように、飲食店においては原則検便検査の実施が義務付けられていないため、検査を行なう頻度についても明確に定められていません。そのため、検便検査を実施するとしてもどの程度の頻度で行なうべきかがわからない人もいることでしょう。
あくまで一般的には、1年に1回以上の検便検査の実施が求められますが、飲食店で検便検査を実施する場合、その頻度は自社の判断で決定する必要があります。
検便検査の必要性の1つとして健康保菌者がいないかを確かめることが挙げられます。日々の食事だけでも細菌やウイルスに感染するリスクはあり、言ってしまえばいつ従業員が健康保菌者になるかどうかはわかりません。
そのため、頻度高く検便検査を実施しておくことで、飲食店の従業員に健康保菌者がいないかを確かめられ、食中毒事故を引き起こすリスクを抑えられるといえます。
とはいえ、検便検査を実施するにもコストがかかります。理論上は毎日のように実施することで食中毒事故を引き起こすリスクをさらに抑えられますが、現実的に考えればそれは難しいでしょう。
そのため、飲食店で検便検査を実施する場合、その地域の自治体に相談をして検査の頻度を決定するのもよいでしょう。自治体によっては検便検査の頻度を独自で推奨していることもあるため、その場合にはその頻度で検便検査を実施するようにしてみてください。
飲食店で検便を実施した場合に検査される項目
食中毒を引き起こす原因として、さまざまな細菌やウイルスがあります。検便検査ではこれらの細菌やウイルスに感染していないかを調べますが、検査項目にはおおきくわけて下記の2つがあります。
- 腸内細菌検査:必要に応じて行うべき
- ノロウイルス:毎年10月から3月に実施が推奨される
これらは同時に行なってもらえることもありますが、基本的に依頼者がどの検便検査を実施するかを判断する必要があります。
これから飲食店で検便検査を実施するためにも、ここからは検便検査の検査項目を解説していきます。
腸内細菌検査:必要に応じて行うべき
腸内細菌検査では、感染症法で三類感染症として位置付けられている「赤痢菌」「腸管出血性大腸菌」「腸チフス」「パラチフス」を主な対象として検査が行われます。腸チフスとパラチフスはサルモネラ属菌に含まれることから、「赤痢菌・腸管出血性大腸菌・サルモネラ属菌」として腸管細菌検査が行なわれるのが一般的です。
また、食中毒を引き起こす細菌であるO157やO26など、腸管出血性大腸菌にはさまざまな細菌があるため、これらの細菌の感染がないかを確かめる際には、すべての腸管出血性大腸菌を検査する必要もあります。
検査する腸内細菌が多ければ多いほど健康保菌者がいないかをより正確に確かめられますが、その分コストがかかります。
当然すべての腸内細菌を検査するのが望ましいですが、それが難しい場合には、飲食店の従業員の行動や世間の傾向をみながら腸内検査を行うのもよいでしょう。
たとえば、感染症が流行している地域に渡航した従業員がいる場合、その原因となる細菌に対する腸内細菌検査を実施することも検討してみてください。
ノロウイルス:毎年10月から3月に実施が推奨される
ノロウイルスは食中毒のなかでも毎年患者数が多く、感染力が強いウイルスです。「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年の食中毒のうち16.0%はノロウイルスが原因であるように、食中毒を引き起こす原因として特に注意するべきウイルスです。
そのため、飲食店において、腸内細菌検査だけでなくノロウイルスに対しても検便検査を実施するのが望ましいです。
厚生労働省が定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、大量調理施設に対して10月から3月までの間は必要に応じて8ノロウイルスの検便検査に努めるように記載されています。
大量調理施設には社員食堂のような集団給食施設や学校給食施設が該当し、一般的な飲食店は該当しません。
とはいえ、10月から3月の間はノロウイルスによる食中毒が発生するリスクが高いため、飲食店で検便検査を実施する場合にはこの期間にノロウイルスの検査も実施するのが望ましいといえます。
飲食店で検便検査を実施する場合の依頼先
飲食店で検便検査を実施するにしても、どこに依頼をすればいいかがわからない人もいることでしょう。
飲食店における検便検査の依頼先は、大まかにわけると下記の2つになります。
- 民間の検査会社
- 飲食店がある地域の保健所
ここからは、飲食店における検便検査の依頼先について、それぞれ解説していきます。それぞれの特徴を踏まえて、検便検査の依頼先を決めるようにしてみてください。
民間の検査会社
民間の検査会社のなかには、当社のように検便検査を行っている会社もあります。民間の検査会社であれば、さまざまな細菌やウイルスに対する検便検査を行ってもらえるうえに、検便を依頼するにあたってのサービスを受けられるのが一般的です。
たとえば、民間の検査会社であれば、基本的に検便キットの受け取りや提出は郵送で行えます。また、検便検査を依頼してから数日程度で結果を確認できるのも民間の検査会社に依頼するメリットと言えるでしょう。
さらに、実績がある検査会社であれば、飲食店での検便検査の実施についてさまざまな相談をすることも可能です。
「どのような検査項目を選ぶべきか」「どの程度の頻度で検便を行うべきか」など、はじめて飲食店で検便検査を実施する場合には民間の検査会社に依頼するのもよいでしょう。
食環境衛生研究所が行う検便検査について
当社「株式会社 食環境衛生研究所」では、検便検査を行なっているため、飲食店での検便検査を実施する場合にはぜひ検討してみてください。
なお、当社が行なっている検便検査については、下記のとおりです。検査名をタップ・クリックすることで当社の検査ページを確認できます。
「どのような検査項目にすればいいのかわからない」といった場合でもお気軽にまずはご相談ください。
飲食店がある地域の保健所
保健所には飲食店の衛生管理を監督する役割があるため、依頼をすることで検便検査を行ってもらえます。
飲食店がある地域の保健所からは、食品衛生責任者の資格の取得や衛生指導などの案内を受けられます。そのため、検便検査を含めた飲食店に関する相談をしやすいのがメリットです。
一方で、検便検査を受けるのに予約が必要になるのが一般的であり、検便キットの提出などが直接の受け渡しのみであるケースも少なくありません。そのため、民間の検査会社よりも時間や手間がかかるのがデメリットといえるでしょう。
保健所に検便検査を依頼する場合、自治体の公式サイトから予約できるのが一般的です。まずは飲食店がある地域の自治体の公式サイトを確認するのがよいでしょう。
まとめ
飲食店において、検便検査は法律で明確に義務付けられているわけではありません。とはいえ、食中毒事故を引き起こすリスクを抑えるため、また従業員や店舗を守るためにも、飲食店では検便検査を実施しておくことが望ましいです。
飲食店で検便検査を実施する場合、食材や料理にかかわるすべての従業員が対象となります。そのため、出勤頻度が少ない人やアルバイトであっても、検便検査を実施するようにしてみてください。
なお、株式会社 食環境衛生研究所では、腸内細菌検査やノロウイルス検査を行なっています。はじめて飲食店で検便検査を行なう場合の相談にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
検便検査のお申し込みはこちら
13時までのお申込みで当日中に発送いたします。(土日、祝日を除く)
お申し込み後、ご自宅に検査キットをお届けいたします。糞便の採取後、弊社まで冷凍便でご返送下さい。
臨床検査のプロを中心に精度の高い検査結果をお安く、素早くご報告致しますのでぜひご依頼下さい。