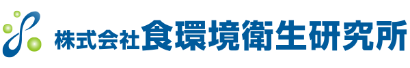豚の細菌性下痢感染症制御|細菌感染症への抗生剤を効果的に選択するために…|Vol.3
はじめに:豚の細菌性下痢について
豚の下痢は、細菌やウイルス、寄生虫の感染によって引き起こされます。細菌が原因となる下痢症では、1.大腸菌、2.クロストリジウム、3.サルモネラ、4.ローソニア、5.豚赤痢菌が原因となります。本章では、細菌症下痢に対する抗生剤の選択を軸に、それらの病気に関してお話いたします。
豚の細菌性下痢に対する抗生剤の基本的な考え方
細菌が関与する下痢症では、原因となる細菌は、腸管で多く増殖しています。そこで、抗生剤を投与する場合、「“標的となる菌に効果のある薬“を”消化管の原因菌まで届ける“」のが重要となります。例えば、アミノグリコシド系の抗菌薬は、経口投与の場合、消化管から吸収されないという特性があります。この吸収されないという特性は、逆に言い換えると口から入って腸管まで届くということを示します。この特性ゆえ、大腸菌やサルモネラ症の治療では、アミノグリコシド系の抗菌薬も使用されます。また、マクロライド系の抗菌薬は、脂溶性があり、生体の細胞内に取り込まれる性質があります。本章で後述の増殖性腸炎を引き起こすローソニア菌は、細胞内に寄生して増え下痢を引き起こす細菌であり、細胞内に取り込まれるマクロライド系抗菌薬で効果的に細菌の増殖を抑えることができます。このように抗生剤の特性を考慮して、抗生剤を決定し、治療することが重要です
もちろん、薬剤感受性試験を実施し、効果のある抗生剤を選定することも重要です。
1.大腸菌症
豚の大腸菌症は、その発症時期から1.早発性大腸菌症、2.遅発性大腸菌症、3.離乳後大腸菌症に大別されます。それぞれ、発症するステージが異なり、1.早発性大腸菌症では、生後3日齢以内、2.遅発性大腸菌症では、生後7~14日齢、3.離乳後大腸菌症では、離乳後3~5日に下痢便を呈する病気です。原因菌は、どれも共通しており、大腸菌の中でもエンテロトキシンという毒素を産生する“エンテロトキシン産生性大腸菌(以下、ETEC)“になります。このETECは、抗生剤に対して耐性化が進んでいることが知られており、抗生剤の使用状況や地域によって耐性化している抗生剤が異なります。そのため、ETECを実際に分離したのち、薬剤感受性試験を実施してから効果のある抗生剤を選択することが重要になります。ニューキノロン系抗生剤やアミノグリコシド系の抗生剤等、抗生剤が効きそうなものを選択して投与することを検討ください。また、エンドトキシンショックの可能性があるため、ペニシリン系抗生剤は避けるべきであります。
2.クロストリジウム症
新生豚において、暗赤色から暗褐色の下痢が認められた場合、甚急性~急性のクロストリジウム症が強く疑われます。クロストリジウム症は、別名「壊死性腸炎」ともよばれ、小腸が広範囲に壊死しているため、死亡率が高いのが特徴です。死亡せず、耐過した場合でも、著しく発育が低下することが知られています。大腸菌と混合感染する場合が多く、どちらも一緒に治療することが大事です。母豚用のワクチンも市販されており、症状を抑制することができます。大腸菌との混合感染が疑われる場合の治療には、エンドトキシンショックの恐れがあるため、ペニシリン系は避け、テトラサイクリン系抗生剤、ニューキノロン系抗生剤等を使用します。
3.サルモネラ症
Salmonella Typhimurium およびS. Derby等が原因で、初感染の多くは肥育豚です。これは、カラスやネズミによる伝播が原因であるからと言われています。生臭い特徴的な下痢便を排泄し、急激に削痩するのが特徴です。呼吸器症状を伴う場合があり、肺炎と誤診する場合があるため注意が必要です。初期対応を誤ると豚舎全体に集団感染を引き起こす場合があります。また、放置すると繁殖豚が保菌豚となり、母子感染につながり、常在化する危険性が高いため、正常化させる必要があります。さらに、多剤耐性株も報告されています。それゆえ、セフチオフルやニューキノロン系抗生剤、アミノグリコシド系の抗生剤から効果のあるものを投与するのが推奨されます。
4.増殖性腸炎(PPE)
増殖性腸炎(PPE)は、Lawsonia intracellularis の回腸粘膜細胞内寄生が原因となります。急性経過では、タール便を排泄し、死亡します。慢性経過では、黄褐色から褐色の泥状~軟便を排泄し、発育が低下します。特徴的な病変として、回腸後部がホース状に肥厚し、粘膜面に偽膜の形成が認められます。発育は、著しく低下します。病理組織診断が診断の主軸ではありますが、抗体価の測定および糞を試料としたPCRで検出する方法があります。感染初期には、糞中に菌体が多く排出されるので、タイミング次第でPCRにて特定できます。マクロライド系の抗菌薬等に感受性があります。急性期の発症の多くが死亡して発見され、治療効果は軽症なものしかないの為、予防することが重要です。
タイロシンをはじめとするマクロライド系薬剤は、抗菌薬中ですぐれた細胞内移行性を有し、さらに腸肝循環により回腸への到達が比較的良好で、PPEに効果的な抗菌薬の一つです。
5.豚赤痢
Brachyspira hyodysenteriaeが経口感染することで発症する病気です。特に肥育後期に発症が多く、急性症状は、赤褐色の悪臭のある粘液便を排泄し、元気食欲廃絶、被毛粗造となり、発育が著しく低下します。慢性期では、黄褐色~緑黄褐色の軟便を排泄し、便に血液の混入は認められません。食欲と発育は次第に回復しますが、出荷日数は大幅に延長することがあります。マクロライド系抗菌薬(タイロシン、リンコマイシン)やチアムリン、バルネムリンが有効です。粘血便を排泄しているものや、全身症状のあるものは注射にて投薬を行います。また、発症豚は水をよく飲むため、飲水投与も有効です。
食環境衛生研究所では抗生剤を選択する際のお手伝いを行っております。具体的には、細菌感染が疑われる検体から細菌を分離・同定し、まずはターゲットを特定します。同じ菌でも、使われている抗生剤によって抗生剤に耐性のものも出てきますので、実際に分離された細菌に対して薬剤感受性試験を行います。薬剤感受性試験では、ターゲットの細菌にどの抗生剤が効いているかを培地上で確認する試験で、多種類の抗生剤を試すことができます。抗生剤選択でお悩みの際はぜひご検討ください!
>>畜産検査ページはこちら
>>畜産コンサルをご希望の方はこちら