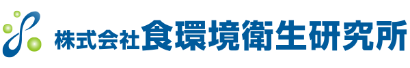用語検索
頭文字を入れるだけで簡単に検索が可能です。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |||||
| あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ |
| た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ |
| ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ | ら | り | る | れ | ろ | わ | を |
| ん |
UPDATE : 2025/02/04 09:02:14 | データ件数 : 2967件
「せ」 の検索結果は 187 件です
生物学的同等性試験(動物用医薬品):
後発動物用医薬品の承認申請の際に必要な試験。予定用法用量で投与したときの標準製剤と試験製剤のバイオアベイラビリティを確認する。
STI(性感染症)
sexually transmitted infectionsの略。以前はSTDとも呼ばれていました。
梅毒、淋菌感染症、性器クラミジア感染症や、梅毒、HIVなどが含まれます。
赤色尿
【せきしょくにょう】
赤色を呈する尿を指し、尿の潜血陽性反応は糸球体からヘモグロビンが漏出している血色素尿症(レプトスピラ症、ピロプラズマ症、産褥性血色素尿症)、ミオグロビンが漏出している筋色素尿症(麻痺性筋色素尿症)、赤血球が泌尿生殖器中へ直接溢血する血尿症(腎盂腎炎、膀胱炎、結石症、外傷、腫瘍など)とに分類される。このほか、ポルフィリン尿、薬物・食餌性にも赤色尿を呈することがある。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
ゼアラレノン
【ぜあられのん】
エストロゲン作用をもつカビ毒の一種で、中毒例として、この毒素に汚染されたトウモロコシやオオムギを給与された家畜の集団中毒がある。中毒症状は外陰部の腫脹、膣脱、乳房および子宮の肥大などで、豚においてもっとも著しい。<獣医学大辞典より抜粋>N090602
ゼアラレノン
【ゼアラレノンの検出について】
平成14年3月18日に、米国から輸入した飼料用マイロからゼアラレノンが検出されたとの報告があったところです。ゼアラレノンはカビが産生する代謝産物であり、高濃度に飼料に含まれた場合は、給与された豚において繁殖障害等の有害作用を生じる可能性があることが知られております。今般、米国から輸入されたマイロは配合飼料の原料として使用されることから、当面の対策として、念のため、飼料中のゼアラレノンの暫定許容値を下記のとおり設定したのでお知らせします。またその周知徹底状況について、別記様式のとおり生産局長まで報告下さるようお願いします。なお、ゼアラレノンの分析については飼料分析基準( 平成7 年11 月15日付け7 畜B 第1660 号畜産局長通知) により行うこととします。【参考】家畜に給与される飼料に含まれることが許容されるゼアラレノンの最大値:1.0 ppm(T090307)
精液希釈液
【せいえききしゃくえき】
精子の保護、生存延長、増量などの目的のため精液の希釈に用いられる溶液をいい、浸透圧およびpHが希釈される精液とほぼ等しいことが基本とされている。<獣医学大辞典より抜粋>N090529
精液検査法
【せいえきけんさほう】
精液の性状を検査する方法で、精液の量、pH、色などの肉眼的検査法と精子数、活力、生存率および奇形率などの顕微鏡的検査法がある。<獣医学大辞典より抜粋>N090529
精液減少症
【せいえきげんしょうしょう】
射精によって放出された精液量がその動物の正常範囲よりも著しく少ないものをいい、まったく精液を欠如するものを無精液症という。先天的な原因による場合もあるが、後天的には精嚢腺炎、前立腺炎、前立腺肥大など、副生殖腺の障害によって起こる場合がある。<獣医学大辞典より抜粋>N090529
精液注入器
【せいえきちゅうにゅうき】
人工授精の際に、精液を雌生殖器道に注入する器具で、動物種や注入精液量などの違いによって、ストロー式注入器、カテーテル式注入器、ピペット式注入器などがある。<獣医学大辞典より抜粋>N090529
精液保存
【せいえきほぞん】
授精その他試験研究などの目的で、精液を生体外に保存することで、家畜の人工授精に用いる精液の保存には-196℃の液体窒素中で凍結保存する場合と、4~20℃で液状保存する場合とがある。牛、馬、山羊などの精液は液体窒素中の凍結保存で半永久的な長期保存が可能であるが、豚では凍結保存にも一部成功しているが通常15℃の液状で保存され、その場合、授精のための有効保存日数は短い。<獣医学大辞典より抜粋>N090529
精液横取法
【せいえきよこどりほう】
人工膣法はもっとも実用的な精液採取方法で、人工膣の大きさ、形状、構造は動物種によって異なるが、いずれもゴム筒と硬質外筒の間に温湯を入れる基本構造は類似している。<獣医学大辞典より抜粋>N090529
精液量
【せいえきりょう】
1回の射精によって射出される精液の量で、家畜の種類、品種、年齢、季節、栄養状態、精液の採取方法と採取頻度などによって左右される。平均的な射出精液量(mL)は、牛3~10、豚150~500、鶏0.2~1.5である。<獣医学大辞典より抜粋>N090529
成形乾草
【せいけいかんそう】
乾草の流通、貯蔵および給与の効率化を図る目的で開発され普及し、ヘイキューブ、ヘイウエハ-などがある。特に牧草を乾燥し、圧縮して作った圧縮成形乾草は元の乾草の1/9以下の容量となり、取扱も容易である。<獣医学大辞典より抜粋>N090602
制限給飼
【せいげんきゅうじ】
飼養目的に対応して飼料の給与量を制限することで、質的制限法、時間制限法、スキップ・デイ法、給水制限の方法を単独あるいは組み合わせて実施する。<獣医学大辞典より抜粋>N090602
生産飼料
【せいさんしりょう】
肉や乳や卵や羊毛などを生産させるために必要な飼料をいう。<獣医学大辞典より抜粋>N090602
青酸中毒
【せいさんちゅうどく】
ヒトでは青酸カリ中毒が多いが、家畜では青酸配糖体などを含む植物の摂取によって中毒を起こす。青酸中毒には亜硝酸ナトリウム、次いでチオ硫酸ナトリウムを投与してチオシアン酸に変えるのが良い。<獣医学大辞典より抜粋>N090602
精子奇形率
【せいしきけいりつ】
精子の形態は動物種によって相違がみられ、奇形精子の出現状況は受胎成績と関係が深く、さらに精巣と生殖道の機拍ヤの判定が可能である。<獣医学大辞典より抜粋>N090529
精子減少症
【せいしげんしょうしょう】
射出精液量は通常範囲にあってもなかの精子数が著しく少ない場合をいう。普通は精子活力の減退、精子奇形率の増加などを伴い、精巣機能が減退している。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
精子死滅症
【せいししめつしょう】
採精直後の精液で、射出精液量や精子数が正常範囲内にあるにもかかわらず、精子の活力がまったくなく、精子が死滅しているものをいうが、全精子が死滅していなくても通常50%以上の精子が死滅している場合には本症と判断され、実際には精子減少症を伴うものが多い。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
精子生存率
【せいしせいぞんりつ】
総精子に対する生存精子の百分率をいい、精子の運動性や生存率は受精能と関係が深い。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
精子耐凍性
【せいしたいとうせい】
精子の凍結保存に耐え得る性質の良否をいい、動物種によって大きな差異があり、牛はもっとも優れ、豚はもっとも劣るが、同種類の家畜でも個体差がある。どの家畜でも射出されたままの精子には耐凍性がないので、凍結保存するには精液にグリセリン、ジメチルスルホキシドなどの凍害防御物質を添加する必要がある。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
精子無力症
【せいしむりょくしょう】
精子活力減退症。正常な交尾欲を有し交尾して射精するにもかかわらず、射出精液の精子活力が著しく低下している雄の状態をいい、精子数の減少と奇形率の増加を伴っている場合が多く、生殖不能である。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
正常細菌叢
【せいじょうさいきんそう】
常在細菌叢。ヒトや動物の体のさまざまな部位(皮膚、目、耳、鼻、消化器、生殖器、泌尿器などの粘膜面)に長期にわたって生体側の正常な防御機高ノよって排除されることなく生息する細菌の集団をいう。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
生殖不能症
【せいしょくふのうしょう】
雄性生殖不能症。雄畜が正常な交尾欲を示し交尾能力をもっているにもかかわらず、交配した雌畜を受胎させる能力のないもので、無精液症、無精子症、精子減少症、精子無力症、精子死滅症、血精液症などによる。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
精巣下降
【せいそうかこう】
精巣の原基は腰椎の腹側位で発生するが、胎子の成長に伴って下降し、鼠径管を通って陰嚢内に入る。この下降は造精機狽ロ持するために精巣温度を体温より低く保つのに重要な意義がある。下降が完了する時期は反芻家畜がもっともはやく、牛で胎生5か月目、豚では出生前後に、馬と犬では出生後に終了する。出生後も精巣が腹腔内、鼠径部、下腹部皮下などにとどまるものを陰睾という。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
製造者固有記号
【製造者固有記号の登録にはどれくらいの期間がかかるか】
2週間程度です。
製造者固有記号
【製造者固有記号の登録はどこで行うか】
厚生労働省のホームページより専用書式をダウンロードし、申し込む。
生物学的同等性試験
【生物学的同等性試験とは】
製剤の形態などを変えるときには、新しいものの生物学的利用性すなわち、生体での吸収の速度と量が、今までのものと同じであることを確かめるために行う試験。(毒性・薬効データの統計解析より抜粋)
生物学的同等性試験
【せいぶつがくてきどうとうせいしけん】
生物学的同等性試験薬剤を投与して体内動態を比較し、対数変換した値を統計解析により同等性を判定する。通常は2剤2期のクロスオーバー法となる。M140129M
成分規格
【生あんの成分規格】
生あんは、シアン化合物の検出されるものであってはならない。【食品衛生法小六法】(T090307)
成分規格
【油で処理した即席めん類の成分規格】
即席めん類は、めんに含まれる油脂の酸価が3を超え、又は過酸化物価が30を超えるものであってはならない。【食品衛生法小六法】(T090307)
成分分析
【 重金属は食品中にどのくらい含まれていますか?(カドミウム)】
田畑等の土壌より米に蓄積されることが問題となっています。最近の研究ではバークなどが土壌中のカドミウムを吸着することなどがわかっているようです。(T090721)
成分分析
【「クエン酸」「酒石酸」は検査できます?】
検査可能ですが、標準品準備の為、検査依頼前に連絡が必要となります。(T090518)
成分分析
【「窒素-たんぱく質換算係数」とは①】
たんぱく質の窒素含量は16%であるため、窒素量×6.25でたんぱく質を算出することができます。ただし、食品の種類によっては、たんぱく質を構成するアミノ酸の種類が異なるため、換算に使用する係数は食品それぞれに応じたものを用います。(T090318)
成分分析
【「窒素-たんぱく質換算係数」とは②】
食品により個々の係数があります。簡単に抜粋します。分析では、その都度確認しながら所定の係数をかけてたんぱく質を算出しています。(T090318)
成分分析
【「窒素ーたんぱく質換算係数」とは?】
たんぱく質の窒素含量は16%であるため、窒素量×6.25でたんぱく質を算出することができます。ただし、食品の種類によっては、たんぱく質を構成するアミノ酸の種類が異なるため、換算に使用する係数は食品それぞれに応じたものを用いる。
成分分析
【ICP発光分析で一度に測定できる元素はどのくらいありますか?】
2009年3月現在までに71の元素分析が可能です。(T090316)
成分分析
【QC Sampleとは】
試験を行う際に品質管理(Quality Control)を行うために既知濃度の標準品を被験物質と同様の操作で調整したサンプルの事をいいます。この濃度を測定し、理論値とのズレが無いことを確認することで試験の信頼性を保証します。(T090318)
成分分析
【アイソクラティック分析とは】
溶媒または溶媒混合物の組成を変化させずに溶出する方法の事をいいます。(T090318)
成分分析
【お茶の(煮だした後の抽出液)栄養成分分析はできますか?】
可能です。煮だし条件を記載してください。検体の状態により分析できない場合もありますので詳しくはその都度お問合わせください。
成分分析
【カリウムとは?】
カリウムは主に細胞内に存在し、浸透圧の調整においてナトリウムと拮抗する作用を示しています。特に日本人はナトリウムの摂取量が諸外国に比べて多いため、ナトリウムの低減に加えて、ナトリウムの尿への排泄を促すカリウムの積極的な摂取が大切と判断されています。(T090721)
成分分析
【カリウムの1日の摂取基準】
日本人の食事摂取基準(2005年版)では体内のカリウム平衡を維持するため適正と考えられている値を、目安量で男性2000mg/日(18歳以上)、女性で1600mg/日(15歳以上)に設定されています。カリウムは、野菜、果実をはじめとするほとんどの食品に比較的豊富に含まれています。(T090721)
成分分析
【カルシウムとは?】
人の体重の1~2%を占める必須酵素であります。大部分は骨及び歯の成分として存在しますが、血液や筋肉中にも存在します。(T090721)
成分分析
【カルシウムの1日の摂取基準】
日本人の食事摂取基準(2005年版)では1日の摂取目標量が10歳以上で600~900mgとされています。食品中では、海産加工物や乳製品に比較的多く含まれていますが、カルシウム強化食品やミネラルサプリメントなどのようにカルシウムを多量に含有する加工食品も市販されています。(T090721)
成分分析
【カルニチンとは?】
カルニチンは、昆虫の成長因子として見つかったアミノ酸の一種ですが、動物の筋肉や肝臓にも広く存在することが明らかになりました。脂質代謝に必須であることから、俗に「ダイエットに効果がある」、「脂肪を燃やす」といわれていますが、ヒトでの有効性については信頼できるデータは見当たりません。一方、循環器への効果が期待され、慢性安定狭心症患者の運動耐性向上、うっ血性心不全患者の症状改善、心筋梗塞発作後の合併症や死亡率の低減に有効性が示唆されています。ただし、効果があるのはL-カルニチンであり、D-カルニチンはL-カルニチンの作用を阻害するため、L-カルニチン欠乏を引き起こすことがあります。安全性については、適切に経口摂取する場合はおそらく安全と思われます。妊娠中の安全性については信頼できる充分なデータがないので使用を避けるべきです。血液透析、無尿症、尿毒症、慢性肝疾患の場合には使用を避けるべきです。参照先:独立行政法人国立健康・栄養研究所”(T090814)
成分分析
【グラジエント分析とは】
極性、pH、溶媒特性が異なる2成分または2成分の溶離液を用いて、分析の進行に従って連続的に溶離液の組成を変える方法。主にバンドの広がりを防ぐために使用されます。(T090318)
成分分析
【ジエチエーテルなどの有機溶媒に溶解可能な物質には何がありますか?】
主として、中性脂肪(トリグリセライド)からなりますが、そのほかに、色素類、ろう、アルカロイド、ステロール類、リン脂質などもふくんでいます。そのため、有機溶媒による抽出は「粗脂肪」「エーテル可溶物(ただし有機溶媒にジエチルエーテルを用いた場合)」などとも呼ばれています。T090616
成分分析
【セレンの1日の摂取推奨量は?】
成人男子で30~35μg/日、成人女子で25μg/日であり、他方、上限量は成人男子で450μg/日、成人女子で350μg/日に設定されています。(T090814)
成分分析
【セレンの過剰摂取は?】
セレンを過剰に摂取するとセレン中毒を起こし、毛髪と爪の脆弱化をはじめ、胃腸障害、神経障害、腎不全、心筋症などを発症すると報告されています。そのため、日本人の食事摂取基準(2005版)では摂取推奨量だけでなく上限値も設定されています。(T090814)
成分分析
【たんぱく質の測定法にはどのようなものがありますか?】
改良ケルダール法によって定量した窒素量に「窒素-たんぱく質換算係数」を乗じて算出します。(T090318)
成分分析
【たんぱく質の測定法は?】
改良ケルダール法によって定量した窒素量に「窒素ーたんぱく質換算係数」を乗じて算出します。
成分分析
【ナトリウムとは?】
ナトリウムは体液や汗の成分として生理的に不可欠な元素であり、近年はともするとナトリウムの摂取過剰傾向にあります。(T090814)
成分分析
【ナトリウムの1日の摂取基準は?】
日本人の食事摂取基準(2005版)においては、過剰摂取による生活習慣病のリスクを予防する観点から、摂取目標量を、食塩相当量で、男性は10g/日未満(12歳以上)、女性は8g/日未満(10歳以上)に設定しています。(T090814)
成分分析
【プリカーサーイオンとは】
MS/MSで測定を行う際に、最初のイオン化で生じるイオンの事をいいます。T090616
成分分析
【プロスキー法で使用する酵素には何がありますか?】
熱安定αーアミラーゼ・プロテアーゼ・アミログルコシダーゼ 以上の三種類を使用しております。T090415
成分分析
【プロダクトイオンとは?】
プリカーサーイオンが不活性ガスと衝突し解離して生じるイオンの事をいいます。T090616
成分分析
【ペット用のおやつの成分を調べたいが何を調べたら良いですか?】
食品の栄養成分の扱いでは無く、畜産飼料と同じ扱いで「水分・粗蛋白・粗脂肪・粗灰分・粗繊維・可溶性無窒素物」の項目になります。(T090518)
成分分析
【マグネシウムとは?】
マグネシウムは体内に約0.04%の割合で存在し、その60~65%は骨に含有されています。血液中には19.2~20.4μg/lの濃度で存在し、カルシウムの細胞壁への侵入を抑える役割を果たしています。また、ストレスによりマグネシウムの排泄が促されています。(T090814)
成分分析
【マグネシウムの1日の摂取基準は?】
日本人の食事摂取基準(2005版)では、15歳以上の日本人の1日の摂取推奨量を0.7~0
成分分析
【マトリックス効果とは】
GC分析において、脂質や色素等の分析試料中に含まれる不揮発性の成分等によって、分析対象物質のピーク形状や面積が大きく変動する事をいいます。(T090318)
成分分析
【マンガンとは?】
マンガンは主として糖代謝や脂質代謝に関与する微量元素であります。摂取不足は代謝不全による成長障害を引き起こします。(T090925)
成分分析
【マンガンの1日の摂取基準とは?】
日本人の食事摂取基準(2005版)では目安量で男性4.0mg、女性3.5mgとされています。食品では種実類、穀粒に多く含まれており、食肉にはほとんど含まれていません。(T090925)
成分分析
【メソッドとは】
機器分析を行う際に波形処理パラメーター、キャリブレーション、ピーク情報等のデータ収集に必要なパラメーターの事をいいます。(T090318)
成分分析
【ソックスレー抽出法とは】
粉砕した試料を円筒ろ紙に入れてソックスレー抽出管に装備し、ジエチルエーテルを滴下循環させてエーテル可溶物質(主として脂肪)を温抽出し受器中に集め、ジエチルエーテルを留去後、乾燥して抽出物を量ります。(T090318)
成分分析
【ソックスレー抽出法以外に測定法はありますか?】
酸分解法・・・組織成分と強固に結合されている脂肪を酸加水分解により溶液中に遊離・分散させた後、ジエチルエーテル及び石油エーテルで抽出を行う。穀類及びその加工食品等に用いる。
成分分析
【ソックスレー抽出法以外に測定法はありますか?】
クロロホルムーメタノール混液抽出法・・・組織へのメタノースの浸透性の高さと、クロロホルムへの溶解性の高さから、大豆や大豆加工品(味噌や納豆は除く)のリン脂質含量の高い商品の抽出に用いる。
成分分析
【ソックスレー抽出法以外に測定法はありますか?】
レーゼ・ゴットリーブ法・・・脂肪球を覆っている脂肪球膜(たんぱく質の被膜)をアンモニアにより分散させ、遊離した脂肪をアンモニア性アルコール溶液から、ジエチルエーテル及び石油エーテルにより抽出する。主に、乳及び乳製品に用いる。
成分分析
【ソックスレー抽出法以外に抽出法はありますか?】
①代表的なものに酸・アンモニア分解法があります。チーズ類に用いる方法で、試料にアンモニアを加え、加温しながら混和し組織を柔らかくし、更に塩酸を加え塩酸下でたんぱく質を加熱分解します。遊離した脂肪を賛成溶液からシエチルエーテル及び石油エーテルにより抽出し、抽出溶媒を留去後、乾燥して抽出物の重量を算出します。他には液-液抽出法といって、しょうゆ・食酢(醸造)・つゆ類に用いる方法で、水分の多い液状試料では蒸発乾固させるのは容易ではないので、直接エーテルなどを用いて脂肪を液-液抽出する方法があります。(T090318)
成分分析
【ヨウ素とは?】
ヨウ素は甲状腺ホルモンに必須の元素であります。ヨウ素欠乏の代表的な症状は、甲状腺腫でありますが、世界的には依然欠乏状態にあり、欧米の先進国でさえもヨウ素の摂取強化を呼びかけています。日本人は海産物によりヨウ素を比較的多量に摂取しているため、ヨウ素欠乏はほとんどないと考えられています。ヨウ素は、過剰摂取によっても甲状腺機能低下、甲状腺腫を引き起こしますが、日本人は恒常的な多量摂取により、過剰摂取の症状がおこりにくいといわれています。食品中のヨウ素は海藻類に圧倒的に多く、特にコンブの含有量が顕著であります。(T090925)
成分分析
【ヨウ素の1日の摂取基準とは?】
日本人の食事摂取基準(2005版)では、成人におけるヨウ素の摂取推奨量と上限値をそれぞれ150μg/日と3000μg/日に設定しています。(T090925)
成分分析
【ラパコールとは?】
パウ・ダルコは南米原産の植物で、メキシコ北部からアルゼンチンにかけて見られる。滑らかなグレーの樹皮と黒褐色の木部を持つ大木であり、長さ20cmの葉は小葉に分かれています。春に紫紅色の花が咲き、後に長さ55cmの円筒形の実(さく果)がなる。俗に「関節炎や痛みを和らげる」といわれていますが、ヒトでの有効性については信頼できるデータは見当たりません。安全性については、過剰摂取は吐き気、嘔吐、めまい、下痢を起こし、場合によっては重篤な悪影響を引き起こすことが報告されています。妊娠中・授乳中の経口使用はおそらく危険と思われることから、摂取は避けるべきです。参照先:独立行政法人国立健康・栄養研究所”(T090814)
成分分析
【リンとは?】
ATPなどの核酸関連化合物、脂質、あるいは骨の成分として人体に1%程度含まれています。食品中のリンは脂質や核酸として、あるいはカルシウムやマグネシウムなどの塩を形成して存在しています。(T090925)
成分分析
【リンの1日の摂取基準とは?】
日本人の食事摂取基準(2005版)では18~29歳の日本人の1日のリン摂取目安量は男性1050mg、女性900mgと設定しています。主食である穀物に比較的リンが多く含まれているため、通常の食生活ではリンの摂取不足はまず問題になりません。加工食品では食品添加物としてリン酸塩、縮合リン酸等の使用が認められていますが、縮合リン酸はカルシウムなどのミネラルと結合してそれらの吸収を妨げる場合があり、摂り過ぎに注意する必要があります。(T090925)
成分分析
【亜鉛とは?】
亜鉛は骨格、筋肉、肝臓、腎臓に存在しており、主として代謝酵素の活性中心やタンパク質合成に関与する重要な酵素であります。摂取不足は成長阻害や皮膚障害、味覚障害を引き起こすことが知られています。(T090721)
成分分析
【亜鉛の1日の摂取基準は?】
日本人の食事摂取基準(2005年版)では、成人で1日7~9mgの摂取が推奨されています。食品では、魚介類、牛肉や種実類に多く含まれています。(T090721)
成分分析
【異性体とは】
分子式は同一だが構造が異なる分子、またはそのような分子からなる化合物をいいます。T090616
成分分析
【一般に我々が消化、吸収可能な炭水化物名は何がありますか?】
ブトウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳頭などの少糖類、でんぷん、でんぷんの部分加水分解物であるマルトデキストリンやマルトオリゴ糖などがあります。T090616
成分分析
【一般栄養成分とは】
水分、タンパク質、脂質、炭水化物及び灰分をいいます。(五訂日本食品標準成分浮謔閨j炭水化物を糖質と食物繊維に分けて六大成分ともいわれます。
成分分析
【一般的な脂肪酸の定量方法にはどのようなものがありますか?】
ガスクロマトグラフィー法といい、脂肪酸を加熱気化しやすくするため、メチルエステル化を行う方法があります。一般的な食品の場合には、遊離脂肪酸も含めてメチルエステル化するこのできる酸触媒によるのが適切です。T090616
成分分析
【栄養成分分析と飼料成分分析の単位】
食品栄養成分分析では100g中のg数で赴Lしますが、飼料成分分析では%表示をします。いずれも100を全量とした時の値ですのでそのまま置き換えることができます。(T090721)
成分分析
【栄養表示基準と五訂食品成分表との関連は?】
栄養表示基準と五訂食品成分表のその成立経緯から、法律・法令と政府資料というものの違い、用いられた分析方法の違いなど、つまり別ものといえます。よって、互いに分析値にズレがでる可能性があります。
成分分析
【栄養表示基準に定める糖類とは?】
単糖または二糖類であって、糖アルコール類でないものをいいます。T090616
成分分析
【栄養表示基準はどのように読みとればいいですか?】
国民の栄養摂取状況からみて欠乏が国民の健康維持・増進に影響を与えるものとして、食物繊維、たんぱく質、亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ビタミンA、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンEおよび葉酸があります。(T091120)
成分分析
【過酸化物価】
試料にヨウ化カリウムを加えた場合に遊離されるヨウ素を試料1kgに対するミリ当量数(mgq)で表したもの。【食品衛生検査指針 理化学編 2005】(T090307)
成分分析
【灰分の測定法は?】
550℃で燃焼させたときに残る灰の量として定義されている。
成分分析
【乾燥助剤とは?】
成分分析
【丸棒のステンレス材について】
丸材には主に、押出材(BE)と引き抜き材(BD)があります。押出しは、材料の3軸方向から圧力を加え、コンテナの開口部から高圧で流出させ、断面積や形状を変化させて長さをのばす加工法で鉛管やアルミ合金形材などを製造する手段として活用されます。引抜きは金属材料をダイを通して引っ張り、ダイ穴と同じ断面形状の棒、管、線材をつくる加工法で、ステンレス鋼などは主にこちらになります。ステンレス鋼は、含有するクロム(Cr)が空気中で酸素と結合して表面に5nm程のごく薄い不動態皮膜を形成しており、耐食性が高いです。クロムが作る不動態皮膜は硝酸(HNO3)のような酸化性の酸に対しては大きな耐蝕性を示しますが、硫酸(H2SO4 )や塩酸(HCl)のような非酸化性の酸に対しては耐蝕性が劣るため、ニッケル(Ni)を8%以上加えて非酸化性の酸にも耐蝕性を高めています(SUS304など)。オーステナイト系ステンレス鋼は非磁性であるが、フェライトになると磁性を備え、マルテンサイト系ステンレス鋼は磁性があり、強度と共に耐摩擦性が高いが耐蝕性が少し劣るようです。(T100222)
成分分析
【機能性成分とは?】
食品の三次機能としての生体調節機能に関与する食品成分を機能性成分といいます。ポリフェノールやカロテノイド、イソチオシアネートなどの植物二次代謝成分は、様々な生体調節機狽ヲすことから代表的な機能性成分です。この他、タンパク質やペプチド、アミノ酸等のタンパク質関連化合物、多糖類やオリゴ糖、単糖などの糖質、複合脂質や高度不飽和脂肪酸等の中で生体調節機狽ヲす成分も機能性成分です。参照先:独)農業・食品産業技術総合研究機(T090814)
成分分析
【桑には血糖値を下げる成分があると聞きましたが、何という成分ですか?】
桑の葉には、桑の葉特有の成分で糖類の一種「1-デオキシノジリマイシン」が含まれています。「1-デオキシノジリマイシン」は、小腸で糖の分解酵素の働きを阻害するため、糖の吸収を抑え、食後の血糖値をゆるやかにするという働きがあるそうです。(T090814)
成分分析
【検出限界とは】
試料に含まれる分析対象物質の検出可能な最低量または濃度をいいます。T090616
成分分析
【検体量が少ないのですが、栄養成分分析はできますか?】
検体の状態によっては分析可能です。詳しくはその都度お問合わせください。
成分分析
【鹸化とは?】
エステルにアルカリを加えて酸の塩とアルコールに加水分解する化学反応の事をいいます。(T090318)
成分分析
【減圧乾燥の利点は?】
乾燥庫内を1~10kPaの減圧度にすることによって、水分を蒸発させるための加熱温度を低く設定することが可能になる。同時に、空気を除去することにより、加熱乾燥中の試料の酸化による重量変化を最小限に抑制することができる。
成分分析
【固相抽出 C18カートリッジカラムとは?】
オクタデシル基をシリカゲルに結合した固相をいいます。展開液の溶媒濃度を段階的に変更し、相互作用を制御することにより、細かな分離、分画が可能となります。コンディショニングには主にメタノールを使用します。コンディショニングせずに直接試料を固相へ負荷すると、固相が持っている本来の機能が十分に発揮されないため、目的物質の保持が極端に悪くなります。(T091023)
成分分析
【固相抽出 C18カートリッジカラムの試料負荷条件は?】
試料が血漿、血清等の時は、1:1または1:2の割合で水またはpH緩衝液で希釈する。試料中にメタノール、アセトニトリルなどの親水性溶媒が含まれる時は、その濃度が10%以下になるように調製する。希釈に用いるpH緩衝液の濃度は、0.1M以下とする。保持をより効果的にするため中性物質は水またはpH緩衝液などで希釈しpH6~7とする。保持をより効果的にするため酸性物質は塩酸、酢酸またはpH緩衝液などでpH2~4とする。
成分分析
【固相抽出法のデメリットには何がありますか?】
固相カートリッジの充填量が少ないため大量の試料では過負荷により精製効果および回収率が低下する場合がある、固相カートリッジの充填量が少ないため夾雑物の多い試料では過負荷により精製効果および回収率が低下する場合がある、順相吸着型の充填剤を含水させて吸着力を調製することが困難である、値段が高い、充填剤の種類が多く、使いこなすには知識と経験が必要である、等があります。(T090925)
成分分析
【固相抽出法のメリットには何がありますか?】
溶媒の使用量が少なくてすむ、同じ製造会社のものは製品の品質が一定に保たれており実験者間あるいは分析機関間での再現性が良い、充填剤の種類が多く分析対象物質に応じた分析が可能、1~数個ごとにパッケージに密封されているので汚染、吸湿などによる変質の可能性が少ない、操作の自動化に対応可能である、等があります。(T090925)
成分分析
【高速液体クロマログラフ法(酵素ーHPLC法)とは?】
プロスキー法では回収しにくい(すなわち約80%v/vのエタノール中では沈澱しにくい)低分子水溶性食物繊維を含む食品の食物繊維総量を求めることができる方法であります。T090415
成分分析
【酸化油油脂】
酸化油油脂および油脂性食品は劣化しやすく、劣化油は食中毒の原因となり得るため、油脂および油脂を多量に含有する食品について一定の規格・基準などが設定されている。油脂(脂質)の劣化は、油脂中の不飽和脂肪酸の自動酸化により起こり、脂質ラジカルやヒドロペルオキシド生成およびそれらの分解物としてのエポキシド、カルボニル化合物(アルデヒド類およびケトン類)、低級脂肪酸、また、重合物(二量体、多量体)などの蓄積を特徴とする。劣化の程度は官能的には、におい、食後の不快感などから検知も可能であるが、感覚反応を定量化することは困難である。したがって、酸化油脂の試験として、これら酸化生成物を定量する酸価、過酸化物価、カルボニル価などの測定が行われている。【食品衛生検査指針 理化学編 2005】(T090307)
成分分析
【酸価】
油脂1g中に含まれる遊離脂肪酸を中和するのに要する水酸化カリウムmg数である。酸価は、油脂の加水分解により生成する脂肪酸と一次酸価生成物(カルボニル化合物)から二次的に生成する脂肪酸を測定する方法で、酸化により生成する脂肪酸の場合は、酸化の初期には検出しにくい。【食品衛生検査指針 理化学編 2005】(T090307)
成分分析
【紫外線吸光検出器とは?】
化合物の特定の光を吸収する性質を使用した検出器でUV検出器とも呼ばれ、HPLCの検出器として利用されています。重水素(D2)ランプ)を光源として使用し、フローセル中の化合物に照射することで化合物の吸光度を測定します。(T090318)
成分分析
【脂質の測定法にはどのようなものがありますか?】
脂質は「有機溶媒に溶ける食品中の有機化合物の総称」と定義されているため、ジエチルエーテルを溶媒とするャbクスレー抽出法が一般的方法として知られています。(T090318)
成分分析
【脂質の測定法は?】
脂質は「有機溶媒に溶ける食品中の有機化合物の総称」と定義されているため、ジエチルエーテルを溶媒とするャbクスレー抽出法が一般的方法として知られています。
成分分析
【脂肪とは】
水に不溶で、ジエチルエーテル、石油エーテル、クロロホルムなどの有機溶媒に可能な成分です。したがって、食品に含まれている脂質は、一般に有機溶媒で抽出して定量します。T090616
成分分析
【脂肪酸の分離、抽出方法には何がありますか?】
主にけん化法と呼ばれるアルカリ処理で直接けん化し、脂肪を脂肪酸に分解してから抽出する方法と酸分解法と呼ばれる脂質の抽出の妨げとなる植物系の細胞壁やデンプン粒を分解した後、可溶化した脂肪を溶媒抽出する方法があります。T090616
成分分析
【飼料の成分分析に必要な検体量は?】
飼料の場合、風乾処理をしますので、最低でも500gは必要です。
成分分析
【飼料成分からのエネルギー算出】
食品栄養成分分析では5大栄養素からエネルギーを算出します。飼料分析の場合はこれがないのですが、暫定的に食品の計算式をあてはめて算出しています。(修正アトウォーター法)(T090721)
成分分析
【飼料成分のうち粗脂肪はどのような方法で分析していますか?】
酸分解-ャbクスレー抽出法で行っております。(T090316)
成分分析
【飼料成分を測定したいが、エネルギーはできますか?】
飼料分析の場合はエネルギー計算は通常算出しませんが、食品検査の場合を参考にして算出することはできます。(T091221)
成分分析
【重金属は食品中にどのくらい含まれていますか?(ヒ素)】
海産物に多く含まれる傾向にあります。ヒ素は無機ヒ素と有機ヒ素に区別され、海産物に多く含まれるヒ素は有機ヒ素で毒性は低いものが多いです。(T090721)
成分分析
【重金属は食品中にどのくらい含まれていますか?(鉛)】
やはり魚介類に多く含まれることが多いです。また海藻中にも同様に蓄積されやすいことも知られています。(T090721)
成分分析
【食品のタンパク質の求め方】
タンパク質を構成するアミノ酸中のアミノ基の窒素を定量し、所定の窒素・タンパク質換算係数を乗することにより求めます。(T090518)
成分分析
【食品の成分分析に必要な検体量は?】
検体1項目あたり30g必要だと考えてください。つまり、一般成分分析の場合150gが必要になります。ただ、再検査できるように、2倍の約300gが必要です。検体の条件にもよりますので、詳しくはその都度お問合わせください。
成分分析
【食品残渣の栄養成分分析はできますか?】
可能です。飼料としての使用が目的ならば飼料成分として測定します。検体の状態により分析できない場合もありますので詳しくはその都度お問合わせください。
成分分析
【食物繊維とは?】
「ヒトの消化酵素で消化されない食品中の難消化成分の総体」と定義されています。非消化性成分(難消化成分)が約80%(v/v)のエタノールに不溶であり、かつ消化性成分が逆に可溶であることを利用して、ヒトの消化系に類似した条件で食品中のでん粉やタンパク質を酵素分解処理し、非消化性成分と消化性成分とを分別し、非消化性成分の重量をはかって「食物繊維」量とします。T090415
成分分析
【食物繊維と粗繊維はどう違うのですか?】
食物繊維は食品成分の測定項目、粗繊維は飼料成分の測定項目です。分析方法が異なります。(T091221)
成分分析
【食物繊維の分析に使用する検体量は?】
上記の分析試料についての事項から、検体により乾燥処理、脱脂処理等行うことを想定すると約100gは必要です。T090415
成分分析
【食物繊維の分析試料について①】
原則として500μmのふるいを通過する均質な試料の調整が必須となります。よって、水分の多い食品ではそのままでは均一に粉砕することが難しいので、乾燥試料を調製してから粉砕します。乾燥処理は、成分変化のほとんどない凍結乾燥法によるのが最適である。T090415
成分分析
【食物繊維の分析試料について②】
脂肪の多い食品については、食品組織にまとわりついている脂質によって、酵素が食品組織中のでん粉やタンパク質に近づくのが妨害されるため、あらかじめ脱脂しておく必要があります。T090415
成分分析
【食物繊維の分析試料について③】
糖類(ショ糖、ブドウ糖、果糖など)を多く含有する食品(例えば果実など)では、乾燥後の残さ中に残る糖類の粘性のために完全に乾燥することが極めて難しいため、糖類の多く含有する食品ではそのままホモジナイザーで処理し、処理物の約10gを精密に採取して試験操作に移ります。T090415
成分分析
【食物繊維定量法とは?】
衛新第13号に食物繊維定量法として採用されている方法には2種類あり、プロスキー法(酵素ー重量法)と高速液体クロマログラフ法(酵素ーHPLC法)があります。当検査室では、プロスキー法で実施しております。T090415
成分分析
【真度とは】
分析法で得られる測定値の偏りの程度をいい、真の値と測定値の総平均の差で表されます。T090616
成分分析
【人体を構成する無機質には何がありますか?】
人体を構成している95%ほどは有機物から成り立っているため、残りの約5%は無機物から構成されています。中でも、カルシウム、鉄、リン、マグネシウム、亜鉛、ヨウ素(ヨード)、セレンは重要な無機質であります。(T090925)
成分分析
【人体を構成する無機質は?】
人体を構成している95%ほどは有機物から成り立っているため、残りの約5%は無機物から構成されています。中でも、カルシウム、鉄、リン、マグネシウム、亜鉛、ヨウ素(ヨード)、セレンは重要な無機質であります。(T090721)
成分分析
【人体を構成する無機質は?】
人体を構成している95%ほどは有機物から成り立っているため、残りの約5%は無機物から構成されています。中でも、カルシウム、鉄、リン、マグネシウム、亜鉛、ヨウ素(ヨード)、セレンは重要な無機質であります。(T090814) せ
成分分析
【酢酸分析は可能ですか?】
酢酸、乳酸、酪酸などの有機酸分析は可能です。HPLCによる分析となります。試料は100g以上、納期は約2週間です。(T091120)
成分分析
【水の栄養成分分析はできますか?】
可能です。検体の状態により分析できない場合もありますので詳しくはその都度お問合わせください。
成分分析
【水の元素分析をお願いしたい。できますか?】
半定量試験として実施します。ICP発光分析にて行います。
成分分析
【水分の測定法にはどのようなものがありますか?】
代表的なものに直接法もしくは乾燥助剤添加法の常圧または減圧加熱乾燥法による減量法があります。ただし、アルコール飲料は乾燥減量からアルコール分の重量を、食酢類は乾燥減量から酢酸の重量をそれぞれ差し引きます。他にはアルミニウム法といって、粘質状の穀類加工食品(飯、ゆで麺)に用いる方法があります。アルミニウム箔を用いて所定温度、時間で損失水分を測る方法や、カール・フィーシャー法といって、カール・フィーッシャー水分測定装置を用いて電気的に検出する方法があります。砂糖類、油脂類、味噌類、乾燥卵、香辛料に用いる方法ですが、弊社では、装置がないため現在この方法は実施しておりません。(T090318)
成分分析
【水分活性とは】
食品中に存在する水分は、食品成分と結合・吸着した状態の結合水あるいは遊離の状態で環境や温度・湿度の変化により容易に移動や蒸発が起こる自由水として存在する。水分活性は、食品中の微生物が増殖に際して利用できる水分、すなわち食品中の遊離水(自由水)の割合を示す指数のことである。【食品衛生検査指針 理化学編 2005】(T090307)
成分分析
【水溶性食物繊維と不溶性食物繊維】
約80%(v/v)のエタノールで非消化性成分と消化性成分に分ける前に上澄液と沈澱とに分けておくことにより、上澄液が「水溶性食物繊維」、沈殿物が「不溶性食物繊維」となります。T090415
成分分析
【成分分析において食品と堆肥は同じ検査方法ですか?】
分析方法は異なります。特に堆肥分析は前処理として自然乾燥する必要がありますので食品に比べ多少時間が必要です。
成分分析
【精度とは】
均質な検体から採取した複数の試料を繰り返し分析して得られる一連の測定値が一致する程度をいいます。T090616
成分分析
【堆肥の完熟度を知りたいのですが?】
完熟度の判定は行っておりませんが、目安として灰分残量を測定する方法もあります。(T091120)
成分分析
【堆肥の有害物質にはどのようなものがありますか?】
主に重金属などで、豚糞等が原料であれば銅や亜鉛が多く残ります。鶏糞でも亜鉛は残りやすいです。T090616
成分分析
【堆肥分析項目について】
鶏・豚・牛などの家畜糞尿堆肥については亜鉛や銅が特に多く含まれます。特に豚糞尿堆肥では銅が多く検出されますので確認が必要です。また消毒用に石灰を多用することが多くなっていますので石灰が多すぎてもいけません。(T090721)
成分分析
【炭水化物と食物繊維と糖質の関係は?】
炭水化物は、全量から水分、タンパク質、脂質、灰分の合計を引いた値として求められます。栄養表示基準では、炭水化物の値からさらに食物繊維の値を引いたものを糖質と言います。
成分分析
【炭水化物の測定法は?】
差し引き(水分、たんぱく質、脂肪及び灰分の合計g数を100gから差し引く)法。
成分分析
【窒素・タンパク質換算係数】
タンパク質中の窒素含有量はほぼ一定の割合(約16%)であることから、通常、窒素・タンパク質換算係数として6.25(=16/100)が用いられます。他の代表的なものに 小麦(玄穀)、大麦・ライ麦・えん麦(5.83)、小麦(粉)・うどん・マカロニ・スパゲティ(5.70)、米(5.95)、そば(6.31)、落花生・ブラジルナッツ(6.31)、くり・くるみ・ごま・その他ナッツ(5.30)、アーモンド(5.18)、かぼちゃ・すいか・ひまわりの各果実(5.40)、大豆および大豆製品(植物性たんぱく、調味植物性たんぱく、豆乳類を除く)しょうゆ(5.71)、乳・乳製品・マーガリン(6.38)、ゼラチン(5.55)などがあります。(T090518)
成分分析
【直線性とは】
一定の濃度範囲において分析対象物の量または濃度に対して直線関係を与える分析法の能力をいいます。T090616
成分分析
【定量限界とは】
適切な制度と真度を伴って定量できる、試料中に存在する分析対象成分の最低量または濃度をいいます。T090616
成分分析
【鉄とは?】
鉄は血液中のヘモグロビンやチトクロムなどの構成成分として人体に不可欠な元素であります。食品中の含有量をみると、鉄を豊富に含む食品は比較的少なく、肝臓、海産物の乾物や香辛料など一部の食品に比較的多く含まれています。(T090721)
成分分析
【鉄の1日の摂取基準】
日本人の食事摂取基準(2005年版)では、15歳以上の日本人の1日の鉄の推奨摂取量を、性別、年齢別に多少の差はあるものの、9.0~11.0mgに設定しています。(T090721)
成分分析
【糖質とは】
一般に、単糖を構成する有機化合物(すなわち炭水化物)の内で、われわれが消化、吸収して体内で利用できるものを指します。よって、利用可能な炭水化物と呼ばれることもあります。T090616
成分分析
【糖質の定量方法にはどのようなものがありますか?】
「差し引きの糖質」法と呼ばれる、たんぱく質(含窒素成分)、脂質(脂溶性成分)、灰分(無機成分)、水分及び食物繊維(利用不能な炭水化物)のそれぞれの量を除いた残り(言い換えるならば、炭水化物から食物繊維を除いた残り)を糖質量とする方法があります。T090616
成分分析
【糖分の分析はできますか?】
糖分には単糖類や二糖類、多糖類など様々にありますが通常は実施しておりません。別に栄養成分分析として、炭水化物から食物繊維を差し引いた糖質であれば常時取り扱っております。(T091221)
成分分析
【糖類の分析法は?】
一般にクロマトグラフ法が広く用いられていますが、それぞれの化学的、物理的に非常に似通った成分同士を分離、同定して定量する必要があるため、該当ピークが目的とする物質に由来するものであること、他の共存物質に影響がないことを確認しなければならない、とあります。T090616
成分分析
【同位体とは】
同じ原子番号を持つ元素の原子において、原子核の中性子が異なる核種の関係、あるいは核種をいいます。T090616
成分分析
【銅とは?】
銅は、結締組織の形成やヘモグロビン生成で重要な役割を担う元素であり、摂取不足は骨の異常や貧血の原因になります。銅の吸収は腸管で行われますが、亜鉛との拮抗作用があるため、亜鉛の過剰摂取は銅の過剰摂取不足を引き起こします。(T090814)
成分分析
【銅の1日の摂取基準は?】
日本人の食事摂取基準(2005版)では、15歳以上の日本人の1日の摂取推奨量を0.7~0
成分分析
【特異性とは】
分析対象試料に含まれる不純物、マトリックス等の共存下で分析対象物質を性格に測定できる能力をいいます。T090616
成分分析
【肉の食味成分について】
脂肪中のオレイン酸(GC法)、アミノ酸のグルタミン酸(HPLC法)、還元糖(ャcMー変法(滴定法))などが数値化できる成分の一つとして知られています。(T090518)
成分分析
【日本酒の栄養成分分析ができますか?】
可能です。ただし、水分にアルコール分が付加されますので、エネルギーを算出するためには全8項目になります。(アルコール分は外部委託検査となります。)
成分分析
【飽和脂肪酸とは】
分子中に二重結合をもたない脂肪酸のことをいいます。脂肪酸の大部分はグリセリンにエステル結合をしたトリグリセライドの形で存在し、リン脂質やステロールエステル類の構成成分として、あるいはスフィンゴシンと酸アミド結合したセラミドの構成成分としても存在しています。T090616
成分分析
【無機質とは?】
無機質とはミネラルのことで炭素、水素、酸素、窒素以外のことです。無機質は食べ物や生物体を燃焼すると、二酸化炭素、二酸化窒素、亜硫酸ガス、水となって飛散した灰の部分のことであり、灰分とも呼ばれています。(T090721)
成分分析
【無機質の分析法は?】
試料を乾式灰化し、酸に可溶化させた後、原子吸光光度法もしくは誘導結合プラズマ(ICP)発光分析法で定量するのが一般的であります。(T090721)
成分分析
【油のpHは通常どれくらいですか?】
pHの定義は水に対して定義されるもので、純粋な油には水素イオンも水酸イオンも含まれませんから理論上pHは7です。しかし現実には食用油には僅かに水分も含まれ、理論通りには行かず実測pHは様々な要因で変化します。そのためpHがどのくらいになるかは、測る度に値が変わり、何が本当なのかわからないことが多いようです。(T100222)
成分分析
【誘導体化とは】
検出器に対して目的物質が十分な感度を示さない場合に、化学反応等により検出器に強い感度を示す物質へ変換することをいいます。(T090318)
成分分析
【卵の残留試験としての項目には何がありますか?】
規格基準のテトラサイクリン系抗生剤や、シロマジン等の農薬、フルベンダゾール等の駆虫薬が挙げられます。T090616
成分分析
【夾雑物(きょうざつぶつ)とは】
分析試料の抽出物に含まれている、色素、糖、脂質、イオウ化合物等の分析の障害となる物質の事をいいます。夾雑物を除去するために対象試料や分析目的物質等によって、液液分配、カラムクロマトグラフィー等の精製を行います。(T090318)
生理食塩水
【せいりしょくえんすい】
人間の体液とほぼ等張の塩化ナトリウムの水溶液(食塩水)である。20140228TM
整理整頓
【物品の整理整頓はどのように進めればいいですか?】
まず、いらないものを処分するのが第一歩です。それでもスペースの足りなければ、簡易な物置などの設置を検討して下さい。t090213
石炭酸中毒
【せきたんさんちゅうどく】
石炭酸およびその誘導体を含む製品(コールタール、クレゾールなど)は皮膚・粘膜に強い腐蝕性を有し、吸収されると痙攣および麻痺を示す。特に猫は感受性が強く、豚がこれに次ぐ。舐食すると口腔および消化管粘膜の炎症を起こし、嘔吐、下痢、食欲不振、腹部過敏、呼吸頻数が認められる。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
赤痢菌
【分布】
サルモネラ菌や大腸菌と違って自然界では哺乳動物の腸管のみに生息している。
是正措置
【ぜせいそち】
ISOにおける用語。起こりうる不適合又はその原因の繰り返しを排除する再発防止措置。M140427
接触感染
【せっしょくかんせん】
感染様式のひとつで、感染動物との直接の接触、またはその排泄物に汚染された器物を介しての間接の接触など、接触を契機として感染することをいう。損傷のある皮膚や外部に露出している粘膜などが侵入門戸となる。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
節足動物媒介感染
【せっそくどうぶつばいかいかんせん】
蚊、ヌカカ、サシチョウバエ、ダニ、ハエ、アブなどの節足動物の媒介による微生物感染をいう。日本脳炎、アカバネ病、バベシア病、タイレリア病などがある。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
切迫と殺
【せっぱくとさつ】
食用獣畜は原則的にと畜場でと殺解体されなければならないが、例外的にと畜場外において獣畜のと殺が認められる場合がいくつかある。これらのうちただちにと殺が必要とされる場合がいわゆる切迫と殺と呼ばれる。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
セミウインドレス鶏舎
【せみういんどれすけいしゃ】
開放鶏舎とウインドレス鶏舎の特徴を合わせた鶏舎です。開放部と温度センサーによる換気扇で鶏舎内の環境を調整します。 O140325
セルカリア性皮膚炎
【せるかりあせいひふえん】
鳥類を終宿主とする住血吸虫類のセルカリアが、非固有宿主であるヒトの皮膚に侵入し、その部位に発赤や掻痒感を伴う一過性の皮膚炎を起こすことがある。日本では古くから島根県宍道湖畔の水田地帯で多発し、湖岸病、湖畔病と称されていた。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
セレニウム中毒
【せれにうむちゅうどく】
高セレニウム飼料摂取によるセレニウム過剰症で、急性、亜急性、慢性の3型がある。主症状は呼吸困難、視力低下、蹄の変形、脱毛、発育不良など病型によりいろいろである。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
腺胃
【せんい】
鳥類の前胃で、胃の上部を占め、直接食道から続き、腹腔左側肝臓の背方に位置する。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
線維芽性細胞
【線維芽性細胞の形態】
2極ないし多極に遊出する紡錘形細胞でその長さが幅の2倍以上みられる。090207
線維素性関節炎
【せんいそせいかんせつえん】
関節腔内の増量した関節液が線維素を主体とする関節炎をいい、原因は細菌感染が多い。豚丹毒、牛、豚、めん羊、山羊、鶏のマイコプラズマ、子牛のクラミジア感染などにより起こり、関節包は肥厚し、関節腔は関節液増量を伴って腫脹する。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
線維素性口内炎
【せんいそせいこうないえん】
偽膜性口内炎。口粘膜の線維素性炎で、析出した線維素が壊死に陥った粘膜とともに偽膜を形成し、混濁した灰白色ないし灰黄色を呈する。病巣は一般に限局性である。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
線維素性肺炎
【せんいそせいはいえん】
細気管支・肺胞内に多量の線維素が滲出する肺炎で、細菌の感染によることが多い。牛肺疫、豚疫などが典型で、初期には肺は充血し、水腫が著明である(充血期)が、気管支・肺胞内に線維素滲出が著明になると硬度を増し(肝変期)、線維素の融解・吸収・囂oに伴い(融解期)、回復に向かう。死因は呼吸障害と細菌毒素などによる心不全で、通常肝変期に起こる。<獣医学大辞典より抜粋>N090601
旋回鶏胃虫
【せんかいにわとりいちゅう】
鶏のほか七面鳥、ホロホロ鳥、キジなどの筋胃や腺胃に寄生し、潰瘍を形成して、感染鳥は2~3週で死ぬものもある。<獣医学大辞典より抜粋>N090604
全血凝集反応
【ぜんけつぎょうしゅうはんのう】
通常、微生物感染動物の抗体調査にスライド凝集反応を応用する場合に、被検体として血液を用いる簡便法をいい、スクリーニング試験として頻用される。鳥類のヒナ白痢、マイコプラズマ症、実験動物のサルモネラ症に応用される。<獣医学大辞典より抜粋>N090604
穿孔ヒゼンダニ
【せんこうひぜんだに】
ヒトを含む哺乳動物全般に寄生し、皮膚の角質層に穿孔する習性があり、全世界に分布する。雌は坑道内に産卵するため激しい痛みと痒みを与える。<獣医学大辞典より抜粋>N090604
洗剤
【食器(皿やスプーンなど)にどのくらい洗剤の残留があるのか調べてほしい】
検査方法といたしまして、上水試験法にあります陰イオン界面活性剤を対象としたメチレンブルーによる吸光光度法がございます。標準液を使用いたしますので、特に原液が必要ということはないかと思われます。料金は25000円、納期は約3週間となっております。
潜在性子宮内膜炎
【せんざいせいしきゅうないまくえん】
慢性子宮内膜炎のなかで、異常分泌物の漏出を伴わないものをいい、多くは不受胎の検査の際に発見される。微生物感染や内分泌異常、自発性感染、医原性などによるが非臨床型で馬、牛に多い。<獣医学大辞典より抜粋>N090604
潜在性乳房炎
【せんざいせいにゅうぼうえん】
不顕性乳房炎。全身症状や乳房および乳汁には肉眼的異常がないにもかかわらず、体細胞数や細菌数などから潜在的に乳房感染が認められるもので、泌乳期の乳牛に多く、泌乳量が減少する。罹患牛は健康牛への感染源となるばかりか、しばしば臨床型に移行するので、予防対策が重要である。<獣医学大辞典より抜粋>N090604
潜在性尿結石症
【せんざいせいにょうけっせきしょう】
牛の尿結石症の病勢進行段階のうち、なんら臨床症状を呈さないが陰毛に結石の付着が認められる状態を指す。<獣医学大辞典より抜粋>N090604
先天性ミオパシー
【せんてんせいみおぱしー】
獣医学領域では胎生期中に起こった非炎症性の筋疾患群について広くこの名称が与えられ、その主なものとして、子牛および子羊の関節拘縮を伴う先天性ミオパシー、子牛における内水頭症を伴う先天性ミオパシー、子豚のいわゆるスプレイレッグなどが挙げられる。<獣医学大辞典より抜粋>N090604
セントラルドグマ
【せんとらるどぐま】
DNAは複製し、DNAから転写によりRNAができ、翻訳によりタンパク質が合成されます。この一連の流れのことをセントラルドグマといいます。 O140423
全胚性卵
【ぜんはいせいらん】
卵分割に際して動物極から植物極まで卵子全体が分割に巻き込まれる受精卵をいう。<獣医学大辞典より抜粋>N090604
前胃
【ぜんい】
鳥類では腺胃のことを前胃ともいう。哺乳類の複胃のうち胃腺を備えない胃腔をいい、反芻類の胃では第1~3胃をまとめて呼称する。<獣医学大辞典より抜粋>N090601